日本人の植物活用についてはあらゆる分野で研究が行われていますが、なかでもユニークかつ独自性が高いのが、昨今密かなブームを巻き起こしている"忍者の植物使い"です。今回は、そんな「忍者ハーブ」を和ハーブ協会の古谷暢基(ふるや まさき)さんが紹介します。
薬草に精通していた忍者たち

甲賀で医薬品会社を立ち上げたのは忍者の末裔
忍者と和ハーブ、この取り合わせを意外に思われる方も多いかもしれませんが、忍者の本場として有名な滋賀県甲賀市は、実は、医薬品会社が多い都市としても知られています。この地で明治初期に最初に医薬品会社を立ち上げた人物は忍者の末裔で、先祖代々薬草に精通していたそうです。
自然科学の達人である"忍者の植物使い"について長年研究していた和ハーブ協会でも、「忍者と薬草」について甲賀市で講演を行ったことがあります。
「修験道」から独自の発展を遂げた忍者の植物使い
忍者たちの有用植物の知恵は、山岳信仰をベースにした日本古来の宗教である修験道にルーツを持っていると思われます。
興味深いことに、それは忍術が使われる現場において独特の発展をし、ほかの分野では見られないオリジナリティあふれる和ハーブの世界が繰り広げられることになりました。
忍者の"実情"とそのルーツ

聖徳太子の配下にも「志能備(しのび)」がいた!?
「忍者」とは、江戸時代以前に活躍した、情報収集などの諜報活動や、ゲリラ戦や破壊活動などのかく乱工作などを遂行したプロフェッショナルを指します。
古くは飛鳥時代の聖徳太子が配下に抱えていたといわれる「志能備(しのび)」までさかのぼるなど諸説ありますが、政権や領地などを争うことが頻繁であった昔日においては、さまざまな局面で必要とされる存在であったと言えるでしょう。
早道者、山潜り、風魔......全国に残る「忍者」の呼び方
忍者の本場である三重県(伊賀国)の「忍者」という呼称にはじまり、北は青森県(津軽国)の「早道之者(はやみちのもの)」から、南は鹿児島県(薩摩国)の「山潜り(やまもぐり)」、神奈川県(相模国)の「風魔(ふうま)」、さらに「乱破(らっぱ)」「素破(すっぱ)」「草(くさ)」「隠密(おんみつ)」など、全国各地、様々な呼び名で忍者の存在は伝えられています。
社会に溶け込む忍者。着ていたのは「農民の作業着」
さて、一般的に忍者といえば、数多く作られた映画や小説などから、「手裏剣」「爆薬」「殺人集団」「超人的なジャンプ力」などの派手で好戦的なイメージが思い浮かびます。少し年配の方は、俳優の千葉真一さん演じる"服部半蔵"が多くの手下忍者を使って派手に活躍する時代劇を思い出されるかもしれません。
しかしながら、現実の忍者の活動は「忍(ぶ)」という漢字に表されるように、目立たず静かで、思ったより地味でした。
たとえば、忍者のユニフォームといえば「顔にマスク、頭には鉢金(はちがね:刀よけ金具が入った鉢巻き)、黒装束」が浮かびますが、実際は地域や周辺に溶け込むため、農民の作業着が主であったと言われます。
任務遂行には健康頑強な体と自然科学の知識が必須
忍者の主な任務である尾行・待ち伏せ・変装などにおいては優れた体力と健康管理能力が必要とされ、同時に携帯品や服装を効率よく軽量化するため、その素材における深い知識が求められました。
また、もう一方の重要な任務である潜入・破壊活動においては、火薬・毒薬・医薬品などの知識に精通しなければなりませんでした。
そのため、忍者は健康で長寿であったと同時に、植物や鉱物などの素材に精通した"自然科学の達人"であったといわれます。
山伏文化と忍者の共通点

こうした背景には、忍者のルーツの一つであるといわれる「修験道」の影響もあります。修験道とは、奈良時代初期に日本古来の山岳信仰や神道および大陸からもたらされた古代密教を背景に生まれた、日本オリジナルの宗教のことです。
修験道を実践する「山伏(やまぶし)」は、気候条件が厳しく険しい山を歩き回ることで自然に精通し、超人的な力をつけたといわれ、衆生(しゅじょう)の指導者的存在でもありました。
あらゆる自然環境における薬草や和ハーブに精通したことで、日本古来の和薬文化の基礎を作り、全国に広めた人たちでもあります。
忍者の自然素材に対する知識の深さは、この修験道と山伏文化から受け継がれたものであり、忍者が行っていたとされる「印」(精神統一や祈願の為に行う手指の動作)や「真言(呪文)」も修験道をベースにしたものです。
また山伏は関所がフリーパスで、全国を自由に行き来する特権を与えられていました。このことから、全国でスパイ活動を行う忍者にとって「山伏」は、半僧半俗であり剃髪の必要が無いなどの条件が似ていた「虚無僧」とともに、主たる変装対象であったと言われています。
とてもユニーク! "忍者の植物使い"
江戸時代前期に書かれた『萬川集海(ばんせんしゅうかい)』には、忍者の心構えや行動基準に始まり、忍者独自の武器の説明や使用法、さらに変装の仕方や建物への侵入法などの"The 忍術"について詳しく書いてあると同時に、"忍者流自然科学"ともいうべきさまざまなノウハウも多く掲載されています。そこにもっとも多く登場する自然素材が植物、すなわち「忍者ハーブ」です。
「忍び」の仕事の本命とも言える、見張り・潜入・待ち伏せなどに使われた小道具を紹介します。
山菜のワラビを使った"特殊軽量縄ハシゴ"で潜入

忍者はターゲットの家屋に潜入し、調査・待ち伏せ・暗殺・破壊活動などを行いました。その際、塀などを越えるために使われた携帯用の折り畳みはしごの素材に、意外にも春の山菜でおなじみの「ワラビ」が使われていました。
使用される部分は食用とする若芽ではなく、成長した大人の繊維で、とても軽く丈夫であったことから重宝されたようです。
イヌタデは忍者式カイロの燃料に

イヌタデは湿った土地などに群生する草本植物で、秋に赤い花穂や果実が目立つことから「アカマンマ」の別名で知られます。おひたしや天ぷらにして食べる地方もありますが、同じ仲間の植物でその辛味からタデ酢などに使われる「ヤナギタデ」に比較して、一般的にはあまり有用されません。
しかし忍者はこれを尾行や待ち伏せ、見張り調査など、野外で長時間待機する際、携帯カイロとして用いました。
忍者式カイロは「銅火(どうび)」と呼ばれ、文字通り銅の容器の中に熱源を入れるのですが、イヌタデは草でありながら、燃えにくい素材であることから使われたようです。
猛毒シキミを"しもやけ薬"に活用
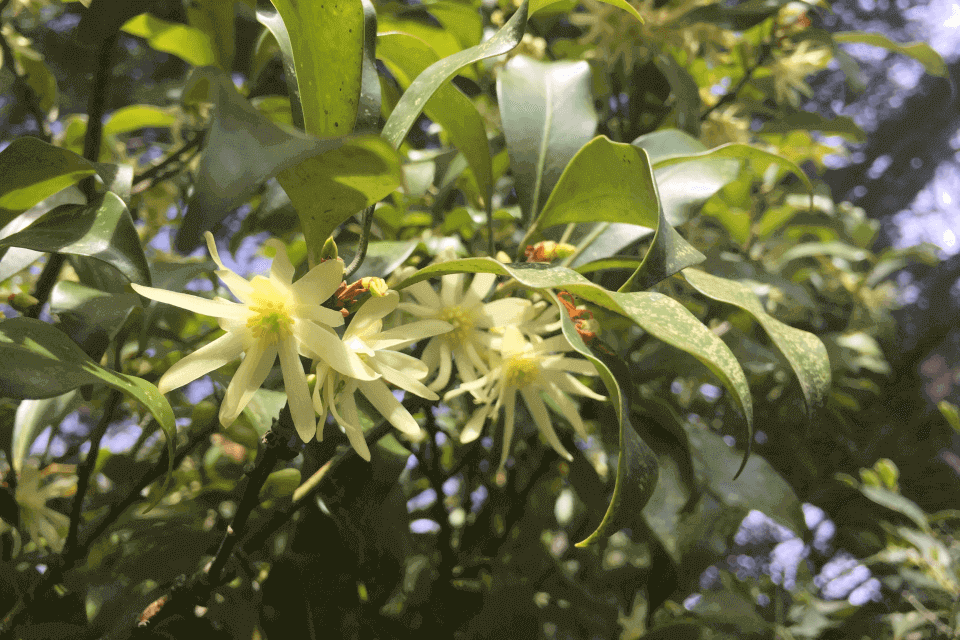
イヌタデを使ったカイロと同様、忍者には野外での長時間待機の仕事が多くあり、冬季などには手が凍傷になるなどのトラブルに見舞われました。そのときに使われたのが和のスターアニス「シキミ」です。
シキミの名の由来は「悪しき実」であり、香辛料として知られる大陸原産のスターアニス(八角)と同属で見た目もそっくりですが、全草にアルカロイドの猛毒を含みます。戦前、来日したドイツ人がスターアニスと勘違いして祖国に輸出し、多くの中毒者を出した事件が知られます。しかし忍者はこの猛毒植物をも皮膚薬として使いこなしたのです。
過去の記事
- 第12回
- 【和ハーブ連載】パスタレシピやスキンケアにも!身近な薬草ヨモギ
2022.06.06 - 第11回
- 【和ハーブ連載】江戸の花見は長かった!? 桜の歴史と生き残り戦略
2022.03.25 - 第10回
- 【和ハーブ連載】不老長寿の和柑橘「タチバナ」が伝える悲しい伝説
2022.02.15 - 第9回
- 【和ハーブ連載】「和柑橘」とは?滋養を豊富に取り入れる活用法
2021.12.10 - 第8回
- 【和ハーブ連載】「クサギ」の興味深い食文化と伝統的な食べ方
2021.10.22 - 第7回
- 【和ハーブ連載】命を支えた「かてもの」文化。誕生背景と代表食材
2021.07.09 - 第6回
- 【和ハーブ連載】いくつわかる?「和ハーブ検定(生活・文化編)」に挑戦!
2021.02.02 - 第5回
- 【和ハーブ連載】いくつわかる?「和ハーブ検定(食・薬編)」に挑戦!
2020.12.01 - 第4回
- 【和ハーブ連載】植物は丸ごといただく!人と植物の関係と活用法
2020.8.21 - 第2回
- 【和ハーブ連載】和の香りの王様クロモジと「クロモジ三兄弟」
2020.2.21 - 第1回
- 【和ハーブ連載】日本古来のハーブ「和ハーブ」の種類とクロモジ
2019.10.25
この方にお話を伺いました
(一社)和ハーブ協会代表理事、医学博士 古谷 暢基 (ふるや まさき)

2009年10月日本の植物文化に着目し、その文化を未来へ繋げていくことを使命とした「(一社)和ハーブ協会」を設立、2013年には経済産業省・農林水産省認定事業に。企業や学校、地域での講演、TV番組への出演など多数。著書は『和ハーブ にほんのたからもの〈和ハーブ検定公式テキスト〉』(コスモの本)、『和ハーブ図鑑』((一社)和ハーブ協会/素材図書)など。国際補完医療大学日本校学長、日本ダイエット健康協会理事長、医事評論家、健康・美容プロデューサーでもある。
















