和ハーブ協会の古谷暢基(ふるや まさき)さんがさまざまな和ハーブを紹介する連載記事です。今回はとても身近な植物「チャノキ」に着目。お茶文化の歴史を紐解きながら知られざる魅力に迫ります。
- 〔目次〕
- 緑茶の原料「チャノキ」は覚醒成分カフェインをもっとも多く含む植物
- ヒマラヤに生まれ、全世界に広がったチャノキ
- 江戸時代には"採取できる垣根"として活用
- "有効成分の宝庫"チャノキの意外な活用法
緑茶の原料「チャノキ」は覚醒成分カフェインをもっとも多く含む植物

"ティー文化"といえば、イギリスは「紅茶」、アメリカは「コーヒー」、中国は「烏龍茶」、そして日本では「緑茶」でしょうか。緑茶は身近過ぎて認識されにくいですが、日本伝統「和ハーブティー」の代表といえます。
この緑茶の原料となる和ハーブの正式名称は「チャノキ」。ツバキ科の常緑樹で、アルカロイド類のカフェインのほか、カテキンやタンニンなどポリフェノール類も多く含み、薬効が高い植物として重宝されてきました。
中国最古の本草書「神農本草経(しんのうほんぞうきょう)」には"薬の神である神農がさまざまな植物を試飲しながらその薬効を確かめる際、毒に当たったときにはチャノキを使って解毒した"という逸話が残されます。
特有成分のカフェインは生活では身近に感じますが、世界で25万種以上あると言われる植物のうちの60種(約0.02%)ほどしか作らないことで知られます(例えばタンニン類はほとんどの植物がつくる)。
このレア成分のカフェインですが、不思議なことに世界4大飲料の原料植物といわれる【1】チャノキ(緑茶・紅茶・烏龍茶など)【2】コーヒーノキ(コーヒー)【3】マテノキ(マテ茶)【4】カカオ(ココアなど)の全てに含まれています。どの地域・文化においても、人々が数多の植物の中から希少な覚醒成分であるカフェイン植物を見つけ出し、常用茶にしていることは、神秘的といっても過言ではありません。
なお4大飲料の原料植物のうち、もっともカフェインを多く含むものがチャノキ(玉露)となります。ただし、チャノキのカフェインは、タンニン類と結合していることで吸収が妨げられるために、一般的には人体にもたらす神経作用はコーヒーの方が強いと考えられます。
ヒマラヤに生まれ、全世界に広がったチャノキ

"お茶は日本のもの"と思われがちですが、チャノキの原産地はヒマラヤ山麓の辺り。神農様の逸話にもあるようにお茶文化は古代中国で始まり、シルクロードや大航海時代の植民地政策などにより世界中に広まっていきました。よって日本語の「チャ」、英語の「TEA」、ヒンディー語の「チャイ」などの発音は、中国語の「茶(地方によってチャ、チャー、テーなどと発音する)」が語源となっている世界共通語です。
ちなみに紅茶や烏龍茶も、緑茶と同様にチャノキが原料となる飲み物。チャノキはポリフェノール類を多く含みますが、採取後は自身が持つ酵素がポリフェノールを酸化させることで茶褐色に変化(褐変)していきます。緑茶が褐変しない理由は、採取直後に蒸すことによってポリフェノール酸化酵素を失活させるからです。
そして烏龍茶は褐変熟成途中(30~70%)に熱をかけて酵素を失活させ、同じく紅茶は熱をかけず最後まで熟成させます。各々の熟成度合いにより、色・香り・味・成分などの違いが現れるわけです。なお日本では、飲料メーカーが作ったイメージから中国においては烏龍茶が主流のようなイメージがありますが、実際は緑茶文化が全体の70%以上を占めます。
江戸時代には"採取できる垣根"として活用

伊吹山麓春日地区のチャノキ(日本導入時の原種とされる貴重種)
日本においては奈良時代以前に仏教とともにお茶文化が導入され、しばらくは貴族などの上流階級のみでたしなまれていました。その後、鎌倉時代に禅宗僧の栄西が「喫茶養生記(きっさようじょうき)」という書物にてお茶文化を紹介しました。当初は煎茶ではなく丸ごと茶葉を飲む抹茶スタイルで、カフェインが濃いことから、座禅僧の眠気覚ましや武士階層を中心に広まり、室町時代には「茶道」という日本独自の文化に発展しました。
江戸時代には、お茶文化は庶民層にも広まり、常緑で葉の密度が高いことから、農家などで "採取できる垣根"として植えられました。日本には元来、生息していないにもかかわらず、野山で野生化したチャノキをよく見かけるのは、そこに人家や人里があった証拠と考えられます。
"有効成分の宝庫"チャノキの意外な活用法

総務省の調査によれば、日本の緑茶消費量はコーヒーなどに押され一時は減少傾向でしたが、ここ10年ほどはペットボトル飲料の普及により増加傾向にあります。同時に茶葉を急須に入れて煎じる機会は、ここ20年で半数以下に減少してしまっています。時間があるときには、茶葉に直接触れながら、自分の好みの濃さや度合いで飲みたいですね。
そして茶葉の豊かな香り・旨味・薬効成分は、飲用以外にも私たちの健康や生活に彩りを添えてくれます。以下にその活用法をいくつか紹介しましょう。
1:色と香りが鮮やかな「ティーオイル」
煎じた後の茶葉は「出しがら」と呼ばれて、捨てられることがほとんど。しかし抽出されたのは水溶性成分で、茶葉には「ビタミンE」「カロテノイド」などの非水溶性成分がまだタップリ残っています。出しがらを乾燥させた後、これらをコメ油などの茶葉の香りとぶつからないクセが少ないオイルに抽出していきます。
漬け込んで3日もすれば色は鮮やかなグリーンに、香りも成分も豊かなオイルの出来上がり。サラダやパスタのドレッシング、肉・魚料理などの仕上げなどにお使いください。
2:有効成分と味・香りをまるごといただく「茶葉料理」

ミャンマー料理「ラペットゥ(発酵茶葉のサラダ)」
茶葉には多くの旨味成分とタンニンなどによる適度な渋味があるために、若葉・成葉によらず天麩羅に適した素材です。若葉は生のまま刻んでサラダに散らしたり、さっと湯がいてお浸しも美味。
"発酵の源の地"と言われるミャンマーでは、チャノキの葉を発酵させた「ラペットゥ」が常備菜として食されます。また茶葉の本場の中国で八大料理に数えられる杭州では、緑茶の一種である「龍井(ロンジン)茶」の生葉を頻繁に使い、塩炒めした川海老に摘み立ての葉を絡める「龍井蝦仁(ロンジンシャーレン)」が有名です。
3:皮膚と自律神経に効く「チャノキ入浴剤」

チャノキにはタンニン成分が多く含まれるため、皮膚への収れん作用や殺菌作用が期待できます。チャノキをやかんや鍋で別に煎じ、色と香りが移ったお湯を浴槽に足すと同時に、茶葉も捨てずにお茶パックや布で包んでお湯に浮かします。
あるいはお風呂の湯温をあらかじめ高めに設定して包んだ茶葉を放り込んでおけば、適温になる頃にはお湯に有効成分が抽出された「チャノキ風呂」の完成です。
チャノキの効能を日々の生活に取り入れてみてはいかがでしょうか?
過去の記事
- 第14回
- 【【和ハーブ連載】新クロモジ三兄弟は色違いのシロモジ&アオモジ
2023.02.06 - 第13回
- 【和ハーブ連載】ワラビが侵入道具に! 忍者の驚き薬草活用
2022.08.19 - 第12回
- 【和ハーブ連載】ヨモギの効果とは?身近な薬草の知られざる力
2022.06.06 - 第11回
- 【和ハーブ連載】江戸の花見は長かった!? 桜の歴史と生き残り戦略
2022.03.25 - 第10回
- 【和ハーブ連載】不老長寿の和柑橘「タチバナ」が伝える悲しい伝説
2022.02.15 - 第9回
- 【和ハーブ連載】「和柑橘」とは?滋養を豊富に取り入れる活用法
2021.12.10 - 第8回
- 【和ハーブ連載】「クサギ」の興味深い食文化と伝統的な食べ方
2021.10.22 - 第7回
- 【和ハーブ連載】命を支えた「かてもの」文化。誕生背景と代表食材
2021.07.09 - 第6回
- 【和ハーブ連載】いくつわかる?「和ハーブ検定(生活・文化編)」に挑戦!
2021.02.02 - 第5回
- 【和ハーブ連載】いくつわかる?「和ハーブ検定(食・薬編)」に挑戦!
2020.12.01 - 第4回
- 【和ハーブ連載】植物は丸ごといただく!人と植物の関係と活用法
2020.8.21 - 第2回
- 【和ハーブ連載】和の香りの王様クロモジと「クロモジ三兄弟」
2020.2.21 - 第1回
- 【和ハーブ連載】日本古来のハーブ「和ハーブ」の種類とクロモジ
2019.10.25
この方にお話を伺いました
(一社)和ハーブ協会代表理事、医学博士 古谷 暢基 (ふるや まさき)
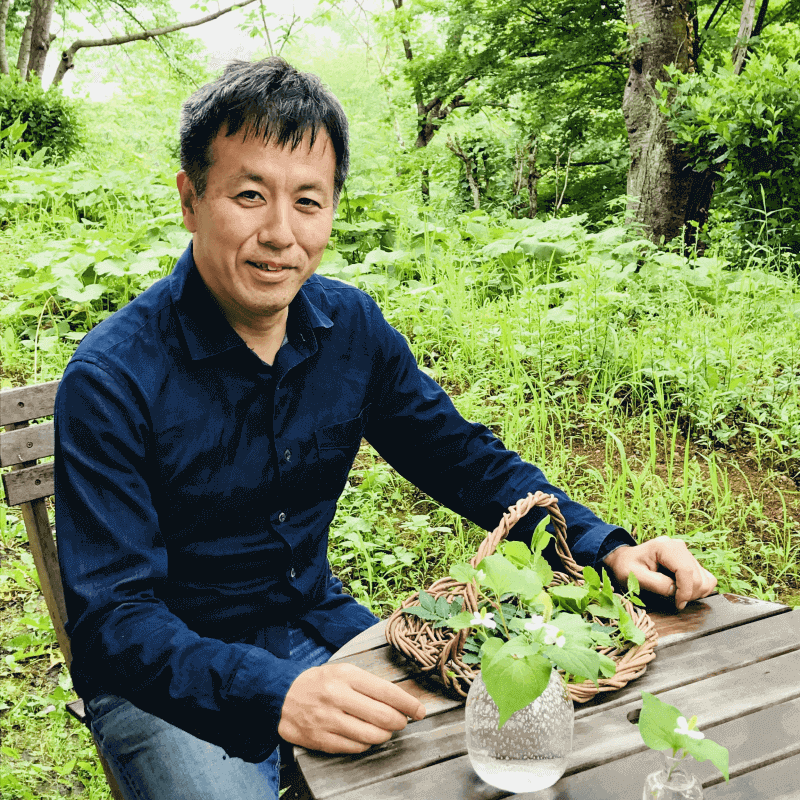
2009年10月日本の植物文化に着目し、その文化を未来へ繋げていくことを使命とした「(一社)和ハーブ協会」を設立、2013年には経済産業省・農林水産省認定事業に。企業や学校、地域での講演、TV番組への出演など多数。著書は『和ハーブ にほんのたからもの〈和ハーブ検定公式テキスト〉』(コスモの本)、『和ハーブ図鑑』((一社)和ハーブ協会/素材図書)など。国際補完医療大学日本校学長、日本ダイエット健康協会理事長、医事評論家、健康・美容プロデューサーでもある。
















