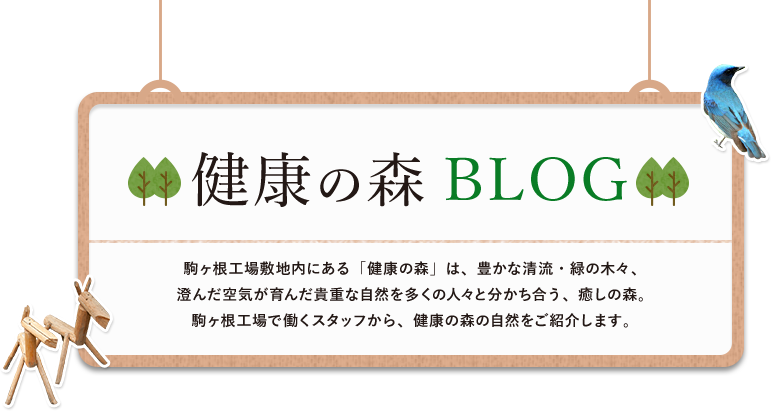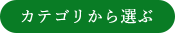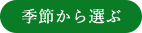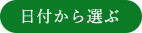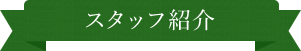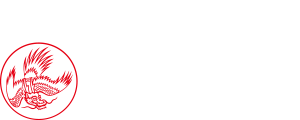植物
-
ナズナ(ペンペングサ)は、圃場の空き地で見つけました。
ゴギョウ(ハハコグサ)は、グリーンベルトの芝生の片隅で。
ハコベは、圃場のあちこちで。
ホトケノザ(コオニタビラコ)は、見つからず。
仲間の、オニタビラコは、グリーンベルトの芝生の片隅にありました。
でも、きっと食べられません。
ちなみに、セリ科のホトケノザは七草じゃありませんので、
もちろん食べません。あしからず。
スズナ(カブ)とスズシロ(大根)は、野菜なので、野山にはありませんね。
子供の時は、冬、正月の頃なんて、草はみんな枯れているものと
思い込んでいましたが、七草はほとんどが雑草で、
たくましく冬越ししていることを知りました。七草粥を食べて、正月気分も抜けたところで、
" alt="">
緑化チームも今日から、元気に森林整備が始まりました。-
七草
- 2014.01.07 森林担当 やっしん
- 今日は1月7日、「七草」の日ですね。 皆さんは、七草粥を食べましたか。 我が家では、スーパーで売られている七...
-
-
林縁部は今年の1~3月にやりましたので、今期は、森の中を
重点的にやりますよ。
現状では、樹高が25m程もあるアカマツに15~20m程度のヒノキが混じった
林になっています。下層には、カバノキ科のミズメやサクラ類、カエデ類などの
広葉樹が多く生育しています。
今回、アカマツを抜き切りして、将来的にヒノキと広葉樹が混じった森林へ
誘導します。
ヒノキの常緑と広葉樹の新緑、紅葉、山桜の花などがモザイク状になった、
色彩豊かな森になる予定です。まず伐採前の作業として、立木の調査をしました。
直径4cm以上のすべての樹木を対象に、ナンバーを付けて、樹種を同定し、
直径と樹高を測定して記録しました。
これが、木の直径を測る「輪尺(りんじゃく)」という器具です。目盛は2cm単位になっていて、胸の高さで測ります(「胸高直径」といいます)。
樹高は目測で測ります。
この場所では、足かけ2年で、1000本以上を調査しました。その後、伐採予定の木にピンクのテープを巻き付けました。
後は、安全対策のロープや注意看板を付けたら、年明けから伐採作業が
始まります。どんな森に生まれ変わるか楽しみですね。作業の様子も、アップしたいと思いますので、
" alt="">
2014年もお楽しみに。-
始まります。
- 2013.12.26 森林担当 やっしん
- 本格的な冬となり、今年も工場内の森林整備の季節がやってまいりました。 今期の作業予定場所は、工場見学の際、空...
-
-
お勧めポイントは、縄文住居周辺です。
時間は光の加減で、昼休み前後がきれいですよ。
紅葉が楽しめるのは、11月中旬頃まででしょうか?
" alt="">-
紅葉が見頃です。
- 2013.11.07 森林担当 やっしん
- ようやく紅葉が里に降りて来て、 健康の森では、今、紅葉が見頃です。 お勧めポイントは、縄文住居周辺です。 時...
-
-
健康の森の林内では、山桜(カスミザクラ)が紅葉しています。
毎年、山桜は一番早く紅葉して、落葉します。
例年では、健康の森の紅葉の見頃は、11月初旬です。林内では、ナツハゼ(ツツジ科)の実が熟していました。
" alt="">
学生の時、研究室の先生がナツハゼのジャムを作って下さって、
とても美味しくいただいた記憶がありましたので、森林整備でも積極的に
刈り残して育成しています。最近では、株もかなり増えてきました。
野生ブルーベリーといったところでしょうか。-
少しずつ秋色
- 2013.10.09 森林担当 やっしん
- 工場の後ろに見える中央アルプスでは、陵線の辺りから紅葉が始まりました。 健康の森の林内では、山桜(カスミザク...
-
-
これは、「ウワミズザクラ」です。
5月に、試験管洗い用のタワシの様な形で、白い花を咲かせていました。健康の森では、ごく普通に見られるサクラの仲間ですが、
今年は特に実の付きが良くて、遠くからでも赤い実が気になります。
実は熟すと黒くなります。健康の森に限らず、野山で見かけるウワミズザクラはどれも
実の付きが良いようで、なぜだかわかりませんが、
今年は当たり年、ということみたいです。まだまだ、暑さが続きます。
" alt="">
夏の暑さで弱った胃腸には、養命酒がお勧めです。
みなさま、お体ご自愛くださいませ。-
実が豊作です
- 2013.08.22 森林担当 やっしん
- みなさま、夏休みはいかがお過ごしでしたか? 私は、通信研修の課題レポートに苦戦しておりました。 相変わらず、...
-
-
これは「ウダイカンバ」です。カバノキ科カバノキ属で、シラカバの仲間です。
" alt="">
今後、アカマツ林を広葉樹林へ転換していく中で、是非、活かしていきたい木です。-
樹木は何種類ある?
- 2013.08.09 森林担当 やっしん
- 残暑お見舞い申し上げます。 連日の猛暑が続いておりますが、皆さまにはいかがお過ごしですか? 熱中症にはくれぐ...
-
-
今は、「オミナエシ」、「キキョウ」、「カワラナデシコ」が見頃です。
適度に、雑草を刈ってあげることで、自然な感じに仕上がってきました。
さらに、自然に生えた「ヤマオダマキ」、「ノアザミ」、「オカトラノオ」、
「ヤマホタルブクロ」、「ノコンギク」、「ノダケ」などが混成して、
賑やかになってきました。
野草が咲く草原は、日本人の心の原風景でもあるので、癒されるのかもしれませんね。
" alt="">-
半自然草原風の野草園をつくる
- 2013.08.09 森林担当 やっしん
- 突然ですが、「温暖で多湿な日本の自然の姿は”森林”」です。 ですから草原や草地というのは、定期的な草刈や火入...
-
-
今週は支障木伐採やら、駐車場周りの草刈など炎天下での作業が続き、
そんな時は本当に、川に飛び込みたくなります。
実際のところ、頭がクラクラして、川の水でタオルを絞って
クールダウンという場面もありました。暑い夏はまだまだ始まったばかり、皆さまにおかれましては、
熱中症対策を十分していただきまして、お体ご自愛くださいませ。ここ健康の森では、涼しい木陰と清流を吹きぬける爽やかな風、
" alt="">
そして、冷えたスイーツで皆様のご来場をお待ちしております。-
暑中お見舞い
- 2013.07.12 森林担当 やっしん
- 暑中お見舞い申し上げます。 週末に梅雨が明けてから、 ここ健康の森でも連日の暑さが続いておりますが、 皆さま...
-
-
その構成要素は、メインに「バッコヤナギ」と「ヤマアジサイ」。
その他に「ヒノキ」、「カンスゲ」、「ホトトギス」、
「アキノキリンソウ」、「コケ」などが確認できました。上手いものだなあ、と関心して眺めています。
" alt="">-
自然の「寄せ植え」作品
- 2013.07.09 森林担当 やっしん
- 川の流れのただ中に、自然の芸術作品とも言える「寄せ植え」 を見つけました。 その構成要素は、メインに「バッコ...
-
-

- カフェ担当のんたん
- 食べることが大好き!!
毎日スイーツに囲まれて
幸せです。
-

- 案内担当みっき~
- 毎日自然に囲まれて
いるせいでしょうか。
・・・のんびりやの私です。
-

- 記念館担当ヨメ子
- 森の小さな変化を探し
ながら、四季を楽しんで
いるナチュラル派の私です。
-

- 森林担当やっしん
- 美しい森づくりに
情熱を注ぐ、
森のエキスパートです。