寝つきが悪い、眠りが浅い、ちゃんと寝ているつもりなのに疲れがとれない...そんな悩みを抱えていませんか?
もしかすると、それらは睡眠の質の低下が原因かもしれません。睡眠の質を高めるためには、まず自分の睡眠タイプを知ることが重要です。そのうえでタイプ別の対策を試しましょう。
また、布団に入るとすぐ眠れる、寝つきには困らないなど一見すると睡眠に問題がないようにみえる人も、睡眠の質が低下している可能性があります。この機会にチェックリストを確認してみましょう。
あなたはどの睡眠タイプ?
眠れない理由は人によって異なり、「ストレス性不眠タイプ」「加齢による不眠タイプ」「思い込み不眠タイプ」の3つに分類されます。また、朝なかなか起きられない人は「ダラダラお疲れタイプ」、一見睡眠に問題がなさそうでも眠りの浅い人は「隠れ疲労タイプ」の可能性が。
自分はどの睡眠タイプに近いかチェックして、タイプ別の対策を試してみてください。
- ☑「あんなこと言わなきゃよかった」など過ぎたことをいつまでも思い悩む
- ☑胃腸がキリキリ痛むことがある
- ☑人間関係のことで悩みがある
- ☑翌日の仕事や家事の段取りが気になり寝つけない
→これらに2個以上当てはまる人は、ストレスが不眠に影響している可能性があります。ストレス性不眠タイプの原因や対策方法へ。
- ☑眠りに役立つことをいろいろ試してみるが眠れない
- ☑布団に入っても時計が気になる
- ☑早めに布団に入るようにしている
- ☑よく眠れていないわりに日中は元気
- ☑「今晩は眠れるかな?」といつも不安でいっぱい
→これらに3個以上当てはまる人は、「今夜も眠れなかったらどうしよう」という不安が不眠に影響している可能性があります。思い込み不眠タイプの原因と対策方法へ。
- ☑眠りが浅く、夜中に何度も目が覚める
- ☑朝早く目が覚めて、それから眠れない
- ☑熟睡感が得られない
- ☑食後にうたた寝することが増えた
- ☑若いころと同じように眠れなくなった
- ☑夜間の排尿の回数が増えた
→これらに3個以上当てはまる人は、加齢が影響している可能性があります。加齢による不眠タイプの原因と対策方法へ。
- ☑夜更かしをしてスマホを見たりゲームを長時間したりする
- ☑昼過ぎまでダラダラしてしまうことが多い
- ☑電車に乗ると寝過ごしてしまうことがある
- ☑朝は起きられず、ムリに起きようとすると吐き気がする
- ☑休日は二度寝して寝坊するが起きてもシャキッとしない
→これらに2個以上当てはまる人は、体内時計のずれによって寝つきが悪くなり、その結果、朝起きられなくなっている可能性があります。ダラダラお疲れ不眠タイプの原因と対策方法へ。
- ☑布団に入るとバタングーで寝る
- ☑50代を過ぎたころから、夜中に目覚めることが増えてきた
- ☑電車やバスではすぐ眠ってしまうが、短時間で目覚めるから寝過ごすことがない
- ☑休日も朝から元気に活動することが多い
- ☑朝はシャキッと起きられる
- ☑血糖値・中性脂肪値、体重が増加しやすくメタボ体型である
→これらに2個以上当てはまる人は、心身が十分に休めていない可能性があります。隠れ疲労タイプの原因と対策方法へ。
全タイプ共通! 3つの不眠改善方法
毎朝同じ時間に起き、太陽の光を浴びる
体内時計のリズムは1日24時間強で刻まれているため、毎日24時間にリセットする必要があります。
リセットスイッチとなるのは太陽の光。体内時計を整えるためには、毎朝同じ時間に起きて太陽の光を浴びることが重要です。朝の散歩がおすすめですが、時間がない人は自然と朝日を浴びられるようカーテンを開けて寝るのもよいでしょう。
また、体内時計を乱さないために、休日と平日の起床時間の差は2時間以内に。
夕方以降はカフェインを控える

コーヒーや紅茶、緑茶などに含まれるカフェインには、脳を刺激する覚醒作用があります。
カフェインの作用は摂取後5~6時間は続くため、夕方以降は控えるようにしましょう。夕食後に緑茶などを飲む習慣がある方は、ノンカフェインでリラクゼーション効果のあるハーブティーに置き換えるのがおすすめです。
ハーブティーの淹れ方については、以下の記事を参考にしてください。
たばこに含まれるニコチンにも覚醒作用があるため、寝る前の喫煙は控えましょう。
夜は強い光を避ける

睡眠は光の影響を強くうけます。夜は明るい光に当たらないことを心がけ、少なくとも寝る2時間前からは、煌々とあかりがついた部屋で過ごすことは避けましょう。室内を暖色系の間接照明にするのがおすすめ。
また、ブルーライトも睡眠の妨げになります。夜に長時間スマートフォンやパソコンの画面を見る場合は、ブルーライトカットの眼鏡をかけましょう。
睡眠の質を向上させるためのタイプ別対策
あれこれ気がかりでよく眠れない「ストレス性不眠タイプ」

ストレス性不眠タイプは、布団に入ってから過ぎたことをクヨクヨ後悔したり、先回りしてあれこれ気をもんだりする「ストレスの予習・復習」をする癖があります。その結果、悶々として寝付けなくなり、不眠を招く原因に。
一過性のストレス性不眠であれば誰しも経験しますが、長引くと精神的にも肉体的にもクタクタになってしまいます。生活習慣病やうつ病、ストレス性胃炎のリスクにも繋がるので、心当たりがある人は以下の快眠対策を試してみてください。
- 〔おすすめ快眠対策〕
- 寝る前にストレスの予習・復習をしないように心がける。
- ジャーマンカモミールとパッションフラワーのブレンドティーを飲む。リラックス効果があり、ストレス性胃炎のケアに役立つ。
- アロマバスに浸かる。粗塩に少量のリラックス系精油を混ぜて浴槽に入れるとよい。
アロマバスで使う精油は、ストレス緩和に役立つラベンダーやスイートオレンジ、ゼラニウム、ネロリ、ローマンカモミールなどがおすすめ。芳香浴をするときは、ディフューザーなどを使わず、お皿に水をはって精油を1~2滴たらし、穏やかに揮発させるとよいでしょう。
簡単に楽しめるハーバルバスについては、以下の記事も参考にしてください。
眠れるかどうか不安で寝つけない「思い込み不眠タイプ」

思い込み不眠タイプは、「今晩も眠れなかったらどうしよう」という不安がストレスになって、寝つきが悪くなっています。また「これをすれば眠れるはず」という入眠儀式にこだわりすぎると、かえってそれがプレッシャーになって眠れないことも。
眠れなかったと感じても、午前中の眠気がないのなら実際は眠れているか、1日のどこかでウトウトして睡眠不足を補えていると考えてOK。布団に入ってから30分以内に眠れるなら入眠不良ではありません。
このタイプの人は眠れないからと焦って、睡眠導入剤に安易に頼ると、薬への依存性が高くなりやすいので注意してください。
ちなみに、近年の脳科学では覚醒していると感じているときでも脳の一部が部分的に眠る「ローカルスリープ」という現象が起きているといわれています。つまり、眠れなかったと思っても、実は脳は部分的に眠っているということです。
あまり心配しすぎず、自分に合ったリズムで睡眠をとりましょう。
- 〔おすすめ快眠対策〕
- 入眠儀式がかえってストレスになるのでやめる。
- 時計を気にすると眠れなくなるので、寝室に時計を置かない。
- 眠くなるまで布団に入らず、朝は決まった時間に起きるように心がける。
- 普段しないことに取り組む。料理やスポーツ、いつもなら読まない本を読むなど、し慣れないことをあえてしてみると、脳と体が適度に疲れて自然に眠りやすくなる。
- 昼寝は午後3時までにする。夕方に寝てしまうと夜更かしの原因となり、睡眠リズムが乱れてしまう。
- 日中にリフレッシュ系のハーブティーを飲んで、日中の活動レベルを上げて、適度に体を疲れさせておく。ペパーミント、ローズマリー、レモングラスがおすすめ。
加齢による不眠タイプ

加齢と共に睡眠は浅く、短くなります。日中の生活に不都合がなければ、とりたてて不眠に悩む必要はありません。
15歳の標準的な夜間の睡眠時間が約8時間であるのに対し、65歳になると約6時間。まとまって眠る力も落ち、夜中や早朝に目覚めてしまいますが、これらは加齢による自然な変化なので安心してください。
- 〔おすすめ快眠対策〕
- 普段あまりやらないことや、やったことのないことにチャレンジする。料理やスポーツ、読書、語学教室など取り組む活動は何でもOK。
- まとめて取ろうとせず、昼寝で分割して睡眠を補う。
快眠の秘訣は脳と体に適度な疲労感を与えること。昼寝をする場合は、夜に眠れなくならないよう、午後3時より早い時間にとるのがおすすめです。
寝つきが悪く起きられない「ダラダラお疲れタイプ」
ダラダラお疲れタイプは、体内時計が後ろにずれやすいのが特徴。起床すべき時刻になっても体を活動モードにする交感神経のスイッチが入りにくく、夕方から夜にかけてようやくスイッチが入ります。
そのため、寝つきが悪く、朝も起きられない状態に。体内時計がずれた昼夜逆転生活が原因で、不登校や引きこもりになってしまう可能性もあります。また、このタイプの人は起きられないからと二度寝すると片頭痛の引き金になることも。
ただし、「起きるための気合が足りない」という精神論はNG。睡眠と覚醒をコントロールする睡眠中枢と体内時計のリズムがかみあっていないと、動きたくても体は動きません。セルフケアで質のよい眠りにつき、溜まった睡眠負債を解消しましょう。
- 〔おすすめ快眠対策〕
- 交感神経を朝からオンにするために、午前中に気分が高揚する予定を入れる。
- 体内時計をずらさないために、休日に二度寝しそうになっても、いったん起きて朝食をとり少し動いてから寝る。
- 眠気の残っている朝は、交感神経を刺激するペパーミント、レモングラス、ローズヒップなどのハーブティーや、酸味のある柑橘系ジュースを飲むとスッキリと起きやすい。
- リフレッシュ効果のあるローズマリーやティートリーの精油で、気持ちをシャキッとさせる。シャワーを浴びるとき床に垂らすか、おしぼりに染み込ませて首元にあてるのがおすすめ。
- 朝の光を毎日30分浴びる。カーテンを開けて寝るとよい。
寝つきがよく短時間睡眠でがんばる「隠れ疲労タイプ」
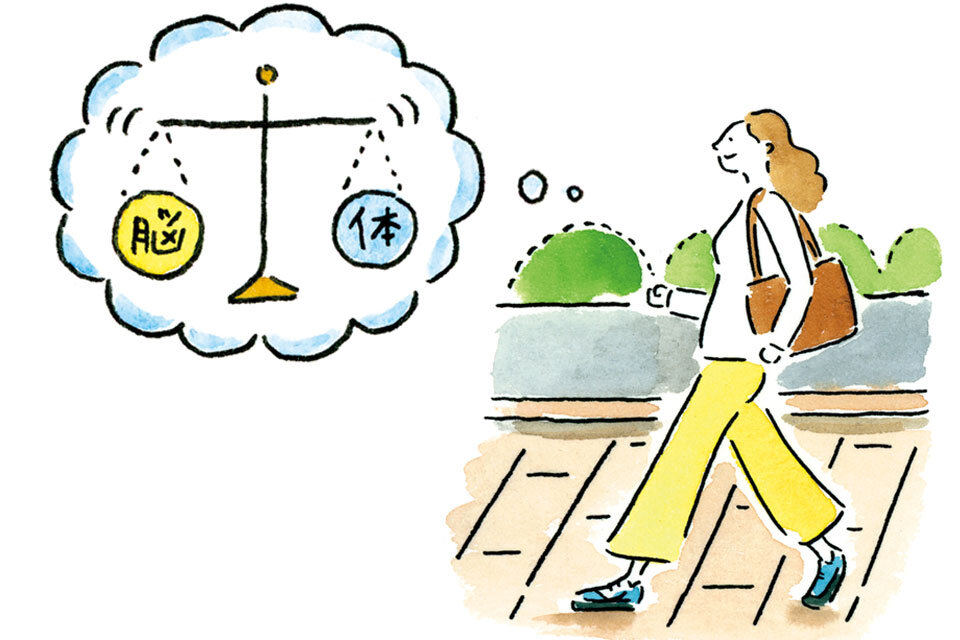
寝つきが良い隠れ疲労タイプは一見元気そうに見えます。しかし、布団に入ってバタングーで寝るのは睡眠負債が溜まっているサイン。短時間睡眠でぱっと目覚めるのは眠りが浅いためで、心身は十分に休まっていません。
疲れているという自覚はなく、何ごともてきぱきとスピーディーにこなす働き盛りのビジネスパーソンや、家事も育児も手抜きをせず長年まじめにがんばってきた主婦に多いタイプです。
このタイプの人は、交感神経が過剰に働いているので、血圧や心拍数が高くなり、心筋梗塞や脳卒中などで過労死するリスクがあります。また、大きな節目を越えた後は燃え尽きたような状態となり、うつ病になる可能性も。
眠りが浅いと睡眠中にリラックス反応が起きにくいので、血糖値、中性脂肪値、体重が増加しやすく、メタボ体型になりやすい傾向にあります。さらに、脳の老廃物・アミロイドβは睡眠中に排出が増えるので、睡眠不足が続くと老廃物が溜まってアルツハイマー病のリスクが高まることにも注意が必要です。
- 〔おすすめ快眠対策〕
- 寝室に情報機器は持ち込まない。寝際にスマートフォンなどを見ると交感神経がますます活性化してしまう。
- 森林浴と同様のリラックス効果のある樹木系の精油をぬるめのお風呂に垂らして、いつもより長めに浴槽に浸かる。ヒノキやサイプレス、シダーウッド、サンダルウッド、クロモジなどの精油がおすすめ。
- コーヒー、栄養ドリンク、チョコレートなどは夕方以降とらない。カフェインの覚醒作用は5~6時間続くため、夕方以降に飲むならリラクゼーション効果のあるレモンバーベナをベースにリンデンをブレンドしたハーブティーを。
ストレスや疲労を溜めないコツについては、以下の記事もご覧ください。
自分に合った快眠対策を日々の生活に取り入れて、質のよい睡眠をとりましょう。
■新着記事はFacebookでお知らせしています。
Facebook独自コンテンツもありますので、ぜひ「いいね!」してお待ちください♪
この方にお話を伺いました
緑蔭診療所 橋口 玲子 (はしぐち れいこ)

1954年鹿児島県生まれ。東邦大学医学部卒。東邦大学医学部客員講師、および薬学部非常勤講師、国際協力事業団専門家を経て、1994年より緑蔭診療所で現代医学と漢方を併用した診療を実施。循環器専門医、認定内科医、医学博士。高血圧、脂質異常症、メンタルヘルス不調などの診療とともに、ハーブティやアロマセラピーを用いたセルフケアの指導および講演、執筆活動も行う。『医師が教えるアロマ&ハーブセラピー』(マイナビ)、『専門医が教える体にやさしいハーブ生活 』(幻冬舎)、『世界一やさしい! 野菜薬膳食材事典』(マイナビ)などの著書、監修書がある。




















