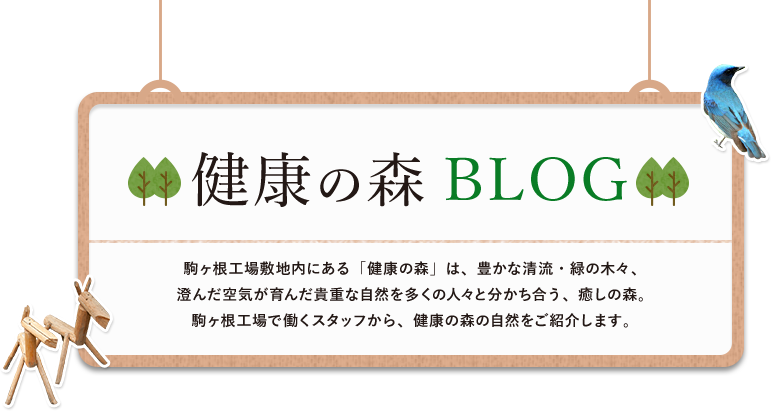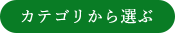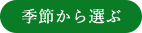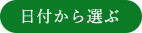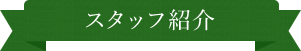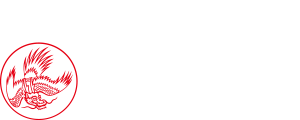植物
-
少しずつ色付き始めた森を、ぼんやり眺めていると、
なんだか時間を忘れそうです。
「そうだ、お茶しに行こう!」と思い立ったら、
" alt="">
養命酒健康の森へお出かけください。-
カフェでのんびりが気持ちいいです。
- 2012.10.21 森林担当 やっしん
- 真夏は日差しが厳しくて、 ちょっと暑かったカフェテラスですが、 朝晩、すっかり冷え込むようになって、 昼間の...
-
-
剪定後
すっきりしました。
" alt="">-
庭木の剪定
- 2012.10.20 森林担当 やっしん
- 工場見学の玄関を出て右手の庭園には、 庭木として仕立てられた松の木(アカマツ)があります。 これまで、腕に覚...
-
-
カフェテラスのデッキ周辺に咲いています。
全草に強い苦味があり、苦味健胃薬としてよく知られています。
名前も、千回煮振り出しても苦味がなくならないので、
千振(せんぶり)と名付けられてとか。
小さくと可愛い花ですよ。こちらは、
「リンドウ(リンドウ科)」(撮影日:10月5日)です。
花が重くて、大抵、横倒しになって咲いています。リンドウが咲き始めると、そろそろ花も終わりだなあと感じます。
霜が降りる頃まで咲いています。ところで、「リンドウ」は長野県の県花です。
ちなみの、長野県の県木は「シラカバ」、県の鳥は「ライチョウ」、
県の獣は「ニホンカモシカ」ですよ!ご存じでしたか?
子供の頃、社会見学で長野県庁へ行ったときのお土産が、長野県下敷きで
そこに描いてありました。懐かしいです。
今も、下敷きもらえますか??今後は、紅葉情報も発信していきます!!
" alt="">-
花情報 10月12日
- 2012.10.18 森林担当 やっしん
- 花情報もいよいよ、今シーズン最後です。 こちらは、 「センブリ(リンドウ科)」(撮影日:10月9日)です。 ...
-
-
名は、茎や葉に竜脳のような香りの揮発性の油が含まれていることから。
比較的希少で株数が少ないので、見つけたらラッキーです。
縄文から道路へ抜ける散策路沿いの林内に咲いています。
写真は、川沿いで群生していたものです。ところで、野菊の花、花といっているのは、
実は小さな花が多数集まったもので、
頭状花(とうじょうか)とか、頭状花序(とうじょうかじょ)と
呼ばれています。
先日、紹介した「ノコンギク」を分解して見ると、
外周には大きな花びらが付いた「舌状花(ぜつじょうか)」があり、
内側には、「筒状花(とうじょうか)」というのがあります。
この一つ一つが小さな花です。花占いで千切った花びらは、舌状花の一枚だった訳ですね。
ちなみに、同じキク科でも、タンポポの仲間はすべて舌状花の集まりですし、
アザミの仲間はすべて筒状花の集まりですよ。花の形もよく観察してみると、色々ですね。
" alt="">-
野菊の花 その2
- 2012.10.16 森林担当 やっしん
- 新たに咲き始める花も少なくなってきました。 こちらは、「リュウノウギク<竜脳菊>」(撮影日:10月10日)で...
-
-
名前の「野紺菊」は、野山に咲く、紺色の菊の花の意味です。
花の色は、薄紫で、白に近いものから、やや色の濃いものまで様々です。
今、健康の森で最も良く見かける花です。こちらは、「ユウガキク<柚香菊>」(撮影日:9月11日)です。
名前の「柚香菊」は、柚(ユズ)の香りがする菊の意味ですが、
実際にはあまり感じられません。
花の色は白で、花の付く茎が枝先で、四方八方に分かれるのが特徴です。こちらは、「シロヨメナ<白嫁菜>」(撮影日:9月17日)です。
構内の道路沿いの林縁部や川沿いのやや日陰に多く咲いています。
葉の付け根で、茎がくの字に折れ曲がっているのが特徴です。こちらは、「ゴマナ<胡麻菜>」(撮影日:8月31日)です。
葉っぱをちぎると、胡麻のような芳ばしい香りがします。
工場見学の玄関を出て、正面の川沿いに咲いていました。こちらは、「シラヤマギク<白山菊>」(撮影日:9月6日)です。
どちらかというと、夏の花という感じです。
葉っぱの形が特徴的です。以上、紹介した野菊の花を見分けるのは難しいですが、
" alt="">
一見同じ様に見える野菊の仲間が、実は結構種類が多いのだと
思って眺めていただけたらと思います。-
特集「野菊の花」
- 2012.10.10 森林担当 やっしん
- 野菊の花と言えば、、、 花びらを引き千切りながら、 「スキ、キライ、スキ、キライ、、、、キライ」、「もう一回...
-
-
工場見学から玄関を出た正面の河原に見えるのは、
「コバノガマズミ」の実です。
構内の道路沿いから見える、こちらは
「ガマズミ」の実です。
" alt="">
これから、森は紅葉の時期へ向かっていきますので、
少しずつ赤や黄色に彩られていきます。
楽しみですね。-
赤い実
- 2012.10.03 森林担当 やっしん
- 10月になって、空気もさわやかになり、 空にはうろこ雲が流れ、秋らしくなってきました。 庭園や森には、赤い実...
-
-
団子の代わりに、カフェの定番スイーツ「紅花とショウガの白玉ぜんざい」を
食べながら、ススキを眺めて、秋を感じるなんていかがですか?
ところで、
ススキの仲間をカヤというのは、葉を刈って屋根を葺いたので、
「刈屋根(カリヤネ)」がなまってカヤになったのだそうです。そういえば、今年は、構内にある縄文式復元住居を建て直しましたので、
まだ刈屋根が真新しいですよ。散策の途中で是非、お立ち寄りください。
構内では、秋らしく穂をなびかせている野草が他にもありましたので、紹介します。
こちらは、
「ノガリヤス(イネ科)」)」(撮影日:9月18日)です。
なんだか、シュッとしていて美しいです。こちらは、
「ヨシ(イネ科)」)」(撮影日:9月27日)です。
構内では調整池の水路沿いに生えていました。
本来、湖岸や沼、河岸に群生します。今年の夏は暑くて、日除けに葦簀(ヨシズ)が大活躍しましたね。
「ヨシ」は本当は、「アシ(葦)」の別名です。
アシが「悪し」に通じるのを嫌ってヨシと呼ぶようになったそうです。
『万葉集』以前には、ヨシという呼び名は見当たらないそうです。というわけで、河原に生えているのは、「ススキ」ではなく「ヨシ(アシ)」
" alt="">
である場合がありますので、よく観察してみてください。-
秋の七草 その7「ススキ」
- 2012.09.29 森林担当 やっしん
- 旧暦8月15日は十五夜。 この日の月は「中秋の名月」として知られています。 今年の中秋の名月は9月30日で、...
-
-
花の形はほとんどアザミですが、葉や茎にとげがありません。
葉っぱはこんな感じです。
「タムラソウ」の名前の由来は図鑑でも不明でした。
私は、田村さんという人が命名したのかと思っていました。こちらは、
「アキノキリンソウ(キク科)」(撮影日:9月24日)です。
林内のあちらこちらで見かけます。こちらは、
「シラネセンキュウ(セリ科)」)」(撮影日:9月17日)です。
この「シラネセンキュウ」などセリ科の野草には、
蝶の「キアゲハの幼虫」がよく集ります。
写真は、同じセリ科の「ノダケ」に集っていたところです。こちらは、アザミの仲間(キク科)(撮影日:9月17日)です。
山野草コースなど、構内のあちこちに沢山咲いています。
「ナンブアザミ」かと思っていましたが、図鑑と見比べると、ちょっと
違うみたいです。アザミは、種類が多くて同定が難しいのですが、
名前はもう少し調べてから、またご報告したいと思います。野草の花も、なんだか秋らしくなってきました。
" alt="">-
花情報 9月26日
- 2012.09.28 森林担当 やっしん
- 花情報をお知らせします。 お客様受付の道路沿いで、ひっそり咲いていたこの花は、 「タムラソウ(キク科)」(撮...
-
-
登山道沿いには、様々な高山植物の花を見ることができました。
こちらは、「タカネグンナイフウロ(フウロソウ科)」(撮影日:9月12日)です。
その他にも、
ミヤマアキノキリンソウ、ウメバチソウ、トウヤクリンドウ、ハクサンボウフウ、
ハクサンイチゲ、ムカゴトラノオ、ヤマハハコ、ミヤマキンポウゲ、ウサギギク、
ヨツバシオガマ、ミヤマリンドウ、クロトウヒレン、トリカブトの仲間などなど、
今年はいつもより、多くの花を見ることができました。参加者全員で5~10kg程度の荷物(椰子マットや金具など)を、
分担して背負子で背負って運びました。
今回の作業場所は、伊那前岳の八合目付近です。
普段は立ち入り禁止の場所に、作業の為、特別に入れていただきました。
右から島田娘の頭、檜尾(ヒノキオ)岳、空木(ウツギ)岳といった、
中央アルプスの峰々を遠くまで見渡すことができました。感激です。
作業風景です。
あらかじめ設計された場所に、椰子マットを敷いて、石を元あった場所に戻し、
さらに金具を打ち込んで固定して行きます。色のきれいな新しいマットが、今回の作業分です。
尾根の登山道沿いでは、「ウラシマツツジ」の紅葉が始まっていました。
今年は、天気や花に恵まれ楽しく作業することができました。
これは参加賞です。山小屋の有料トイレの利用手形になっています。
富士山では、先日、初冠雪の便りがありましたね。
中央アルプスの紅葉も間もなく、上の方から始まります。中央アルプス千畳敷の紅葉を楽しんで、ロープウエイを降りられましたなら、
少しだけ足を延ばして、是非、養命酒健康の森へお立ち寄りください。
疲れた体をオリジナルティー&スイーツと、スタッフの素敵な笑顔が
皆様をお待ちしております。健康の森の営業時間は、9:30~16:30です。
" alt="">-
養命酒の水源の峰を行く2012
- 2012.09.27 森林担当 やっしん
- 養命酒を製造する水は、中央アルプスに育まれた地下水を使っています。 だからという訳ではありませんが、 私にと...
-
-

- カフェ担当のんたん
- 食べることが大好き!!
毎日スイーツに囲まれて
幸せです。
-

- 案内担当みっき~
- 毎日自然に囲まれて
いるせいでしょうか。
・・・のんびりやの私です。
-

- 記念館担当ヨメ子
- 森の小さな変化を探し
ながら、四季を楽しんで
いるナチュラル派の私です。
-

- 森林担当やっしん
- 美しい森づくりに
情熱を注ぐ、
森のエキスパートです。