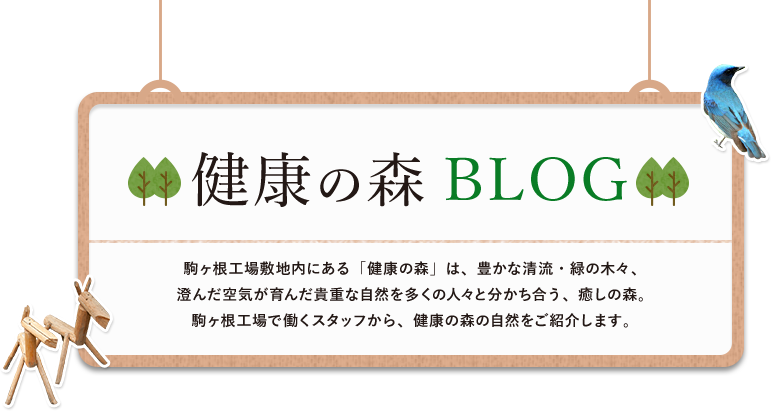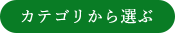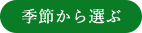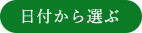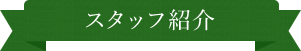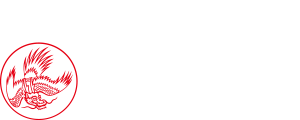秋
-
少しずつ色付き始めた森を、ぼんやり眺めていると、
なんだか時間を忘れそうです。
「そうだ、お茶しに行こう!」と思い立ったら、
" alt="">
養命酒健康の森へお出かけください。-
カフェでのんびりが気持ちいいです。
- 2012.10.21 森林担当 やっしん
- 真夏は日差しが厳しくて、 ちょっと暑かったカフェテラスですが、 朝晩、すっかり冷え込むようになって、 昼間の...
-
-
剪定後
すっきりしました。
" alt="">-
庭木の剪定
- 2012.10.20 森林担当 やっしん
- 工場見学の玄関を出て右手の庭園には、 庭木として仕立てられた松の木(アカマツ)があります。 これまで、腕に覚...
-
-
森の中で、樹液が噴き出したコナラの木にいました。こちらは、「オオゾウムシ」とのツーショット。
「オオスズメバチ」でかいです。これまで、養命酒駒ヶ根工場の森は、アカマツが密生して林内が暗く、
広葉樹もほとんど目立たない森でした。数年前からの森林整備によって、林内が明るくなり、広葉樹も活性化
して、多様な樹種からなる豊かな森に変わりつつあります。
コナラやクヌギが増えてくれば、カブトムシやクワガタなどの虫が集まって
くる期待が持てますが、当然、同じ樹液を好物にしているオオスズメバチなど
も集まって来てしまいます。また、コナラの木に人が刃物で傷を付けても、思うようには樹液は出てきません。
カミキリムシの喰痕をオオスズメバチが強力なアゴでかじることで、樹液が出て
来ます。ですから、カブトムシやクワガタが観察できる森には、オオスズメバチ
も必要な存在です。このような自然環境で、ハチやヘビなどとの共存は難しい面もありますが、
" alt="">
これからも、お客様の安全を第一に、自然豊かで魅力ある森林空間を提供して
いけるように努力していきたいと思っています。-
森が豊になると、、、。
- 2012.10.19 森林担当 やっしん
- いかにも恐ろしいこの顔、恐怖を感じる黒と黄色の縞模様、 世界の中でも最強の毒を持つ昆虫、「オオスズメバチ」で...
-
-
カフェテラスのデッキ周辺に咲いています。
全草に強い苦味があり、苦味健胃薬としてよく知られています。
名前も、千回煮振り出しても苦味がなくならないので、
千振(せんぶり)と名付けられてとか。
小さくと可愛い花ですよ。こちらは、
「リンドウ(リンドウ科)」(撮影日:10月5日)です。
花が重くて、大抵、横倒しになって咲いています。リンドウが咲き始めると、そろそろ花も終わりだなあと感じます。
霜が降りる頃まで咲いています。ところで、「リンドウ」は長野県の県花です。
ちなみの、長野県の県木は「シラカバ」、県の鳥は「ライチョウ」、
県の獣は「ニホンカモシカ」ですよ!ご存じでしたか?
子供の頃、社会見学で長野県庁へ行ったときのお土産が、長野県下敷きで
そこに描いてありました。懐かしいです。
今も、下敷きもらえますか??今後は、紅葉情報も発信していきます!!
" alt="">-
花情報 10月12日
- 2012.10.18 森林担当 やっしん
- 花情報もいよいよ、今シーズン最後です。 こちらは、 「センブリ(リンドウ科)」(撮影日:10月9日)です。 ...
-
-
子供の頃、よく捕まえたゲンゴロウには、白い縁取りがありましたが、
このゲンゴロウは全身黒い色です。
クロゲンゴロウ?、それともヒメゲンゴロウ?正式名はわかりませんが、ゲンゴロウの仲間には間違いありません。
最近、ほとんど見かけることがなくなりましたので、うれしかったです。
ミズバショウ池の周りの木を間伐して、日当たりが良くなったことが
良かったのかもしれませんね。撮影後、ゲンゴロウはミズバショウ池に返しました。
" alt="">
他にも2~3匹は見かけましたので、健康の森へ来られましたら、
ミズバショウ池まで足を伸ばして、探してみてください。-
ゲンゴロウを捕捉
- 2012.10.17 森林担当 やっしん
- ついに、幻?のゲンゴロウを捕捉しました。 昼休み、ブログネタを求めて、ミズバショウ池の 周りをウロウロしてい...
-
-
名は、茎や葉に竜脳のような香りの揮発性の油が含まれていることから。
比較的希少で株数が少ないので、見つけたらラッキーです。
縄文から道路へ抜ける散策路沿いの林内に咲いています。
写真は、川沿いで群生していたものです。ところで、野菊の花、花といっているのは、
実は小さな花が多数集まったもので、
頭状花(とうじょうか)とか、頭状花序(とうじょうかじょ)と
呼ばれています。
先日、紹介した「ノコンギク」を分解して見ると、
外周には大きな花びらが付いた「舌状花(ぜつじょうか)」があり、
内側には、「筒状花(とうじょうか)」というのがあります。
この一つ一つが小さな花です。花占いで千切った花びらは、舌状花の一枚だった訳ですね。
ちなみに、同じキク科でも、タンポポの仲間はすべて舌状花の集まりですし、
アザミの仲間はすべて筒状花の集まりですよ。花の形もよく観察してみると、色々ですね。
" alt="">-
野菊の花 その2
- 2012.10.16 森林担当 やっしん
- 新たに咲き始める花も少なくなってきました。 こちらは、「リュウノウギク<竜脳菊>」(撮影日:10月10日)で...
-
-
昼寝中です。夜行性ですから。失敬して、ちょんちょんすると、、、
にらみつけられました。ゴメンなさい。でも、よっぽど眠いのか、しばらくすると、目がトローン。
再び眠りに落ちていきました。森の中のアケビの実、食べたのはもしかして、ムササビくん?
写真の実は、葉っぱが3枚の「ミツバアケビ」の実。
ちなみに、葉っぱが5枚のものを「アケビ」といいますよ。
この場所がよっぽど気に入ったのか、後日再び登場。
でも、やっぱり昼寝中。
つんつんしたら、全身の姿を見せてくれました。
今なら、ムササビに会えるかもしれない健康の森へ
" alt="">
、是非遊びに来てください。-
健康の森の人気者
- 2012.10.15 森林担当 やっしん
- 健康の森の人気者といえば、、、 ムササビくん(ちゃん?)。 久し振りに現れました。 朝の掃除の時間、健康の森...
-
-
名前の「野紺菊」は、野山に咲く、紺色の菊の花の意味です。
花の色は、薄紫で、白に近いものから、やや色の濃いものまで様々です。
今、健康の森で最も良く見かける花です。こちらは、「ユウガキク<柚香菊>」(撮影日:9月11日)です。
名前の「柚香菊」は、柚(ユズ)の香りがする菊の意味ですが、
実際にはあまり感じられません。
花の色は白で、花の付く茎が枝先で、四方八方に分かれるのが特徴です。こちらは、「シロヨメナ<白嫁菜>」(撮影日:9月17日)です。
構内の道路沿いの林縁部や川沿いのやや日陰に多く咲いています。
葉の付け根で、茎がくの字に折れ曲がっているのが特徴です。こちらは、「ゴマナ<胡麻菜>」(撮影日:8月31日)です。
葉っぱをちぎると、胡麻のような芳ばしい香りがします。
工場見学の玄関を出て、正面の川沿いに咲いていました。こちらは、「シラヤマギク<白山菊>」(撮影日:9月6日)です。
どちらかというと、夏の花という感じです。
葉っぱの形が特徴的です。以上、紹介した野菊の花を見分けるのは難しいですが、
" alt="">
一見同じ様に見える野菊の仲間が、実は結構種類が多いのだと
思って眺めていただけたらと思います。-
特集「野菊の花」
- 2012.10.10 森林担当 やっしん
- 野菊の花と言えば、、、 花びらを引き千切りながら、 「スキ、キライ、スキ、キライ、、、、キライ」、「もう一回...
-
-
工場見学から玄関を出た正面の河原に見えるのは、
「コバノガマズミ」の実です。
構内の道路沿いから見える、こちらは
「ガマズミ」の実です。
" alt="">
これから、森は紅葉の時期へ向かっていきますので、
少しずつ赤や黄色に彩られていきます。
楽しみですね。-
赤い実
- 2012.10.03 森林担当 やっしん
- 10月になって、空気もさわやかになり、 空にはうろこ雲が流れ、秋らしくなってきました。 庭園や森には、赤い実...
-
-

- カフェ担当のんたん
- 食べることが大好き!!
毎日スイーツに囲まれて
幸せです。
-

- 案内担当みっき~
- 毎日自然に囲まれて
いるせいでしょうか。
・・・のんびりやの私です。
-

- 記念館担当ヨメ子
- 森の小さな変化を探し
ながら、四季を楽しんで
いるナチュラル派の私です。
-

- 森林担当やっしん
- 美しい森づくりに
情熱を注ぐ、
森のエキスパートです。