「疲れやすい」と感じる理由はさまざまです。改善するには、食事、運動、睡眠といった複数の生活習慣を見直すことが第一。今すぐ実践できるセルフケア方法を紹介します。
疲れやすいのはなぜ?

一口に「疲れ」といっても、その原因は1つではありません。運動後の心地よい疲労感とは異なり、私たちの日常に潜む「疲れやすさ」は、体からのSOSサインかもしれません。その原因は大きく3つに分けられます。
脳神経的なもの:体をあまり動かしていないはずなのに夜になるとぐったりするのは、情報過多やストレスによる「脳疲労」の可能性があります。
食事に由来する代謝的なもの:食後に強い眠気やだるさを感じるなら、急激な血糖値の変動、いわゆる「血糖値スパイク」が関係していることがあります。
身体的なもの:階段を上るだけで息が切れたり、体を動かすのが億劫に感じられたりする場合は、単純な体力不足が考えられます。
現代社会では、頭はフル回転なのに体は動かさないという「心身のアンバランス」が、自律神経の乱れを招き、慢性的な疲労感の大きな引き金となっています。まずは疲れがどこからきているのか、その原因を探ることから始めましょう。
食生活の乱れ

疲れにくい体づくりの基本は、毎日の食事にあります。胃腸の働きが弱っていたり、食べ方に問題があったりすると、せっかく食べたものから十分に栄養を吸収できず、エネルギー不足に陥ってしまいます。
例えば、冷たいもののとりすぎは胃腸を冷やして機能を低下させますし、早食いやよく噛まない習慣は消化に大きな負担をかけます。
また、朝食を抜くと1日の活動エネルギーが不足しますし、だらだらと間食を続けることは内臓に休ませる暇を与えません。さらに、栄養バランスの乱れも深刻です。
特にエネルギー代謝に必要なビタミンB群や、全身に酸素を運ぶ鉄が不足すると、体はエネルギーを効率良くつくれなくなり、慢性的な疲労感や倦怠感の原因となります。女性は月経により鉄を失いやすいため、鉄欠乏性貧血にも注意が必要です。
運動不足
「疲れているから動きたくない」と感じるかもしれませんが、実はその逆で、「動かないから疲れやすい」体になっている可能性があります。
運動不足や加齢によって筋肉量が減少すると、基礎代謝が低下し、血行が悪くなります。血行不良は、体中に栄養や酸素を届け、老廃物を運び去るシステムを滞らせるため、エネルギー産生の効率が落ち、疲労物質がたまりやすくなるのです。
また、運動不足により筋力が低下すると、階段の上り下りといった日常の何気ない動作でさえ、すぐに疲れを感じてしまいます。
質の低い睡眠

私たちの体や脳は、寝ている間に日中の活動で受けたダメージを修復し、疲労を回復させています。特に、眠り始めの深いノンレム睡眠中には、細胞の修復や再生を促す成長ホルモンが盛んに分泌されます。
また、脳は睡眠中に、日中の活動でたまった老廃物を洗い流すという重要なメンテナンスを行っています。しかし、睡眠時間が不足していたり、夜中に何度も目が覚めるなど睡眠の質が低かったりすると、これらの重要な回復プロセスが十分に行われません。
その結果、「たくさん寝たはずなのに、朝から疲れている」という状態に陥ってしまうのです。このような状態が続くと、心身の疲労が借金のように積み重なる「睡眠負債」という状態になり、日中の集中力低下や気分の落ち込みなど、「脳疲労」の症状にもつながります。
疲れをとるためには、単に長く寝るだけでなく、いかに質の高い睡眠を確保するかが鍵となります。
精神的なストレス
仕事のプレッシャーや人間関係の悩み、環境の変化など、私たちが日常的に感じる精神的なストレスも、疲れやすさの大きな原因です。
ストレスを感じると、私たちの体は「闘うか逃げるか」の戦闘モードに入り、自律神経のうち活動を司る「交感神経」が活発になります。
交感神経が優位な「アクセル全開」の状態が続くと、心身を休息させ、修復する役割の「副交感神経」が働く時間が奪われてしまいます。その結果、体は常に緊張状態でエネルギーを消耗し続け、十分に回復できず疲弊してしまうのです。
対策が大事! 疲れやすい人におすすめの改善法

疲れやすい体質を改善するには、食事、運動、睡眠などを組み合わせて生活習慣を見直し、日々の暮らしの中で「養生」を意識することが、健やかな毎日を取り戻すための鍵となります。今から始められる具体的な改善法を紹介します。
食事に関する改善

健康な体は、バランスの取れた食事からつくられます。自分の活動量に見合ったエネルギーを摂取し、体が必要とする栄養素を過不足なくとることが、疲労回復と健康増進の基本です。何を食べるかだけでなく、どう食べるかも大切です。胃腸に負担をかけず、栄養をしっかり吸収できる食生活を心がけましょう。
とるべき栄養素と食べ物
疲れにくい体をつくるためには、エネルギーを生み出し、体の調子を整える栄養素が必要です。特に意識してとりたい栄養素と多く含まれる食品を紹介します。
- 〔糖質〕
- 体と脳を動かす主要なエネルギー源。不足するとガス欠状態になり、思考力や体力が低下します。多く含む食品は、ご飯、パン、麺類などの穀類、いも類、果物など。
- 〔タンパク質〕
- 筋肉や血液、ホルモンなど、体のあらゆる組織の材料。体力維持や疲労した体の修復に不可欠です。多く含む食品は、肉類、魚介類、卵、大豆製品、乳製品など。
- 〔脂質〕
- 効率のよいエネルギー源であり、細胞膜やホルモンの構成成分。とりすぎは禁物ですが、良質な脂質は健康維持に必要です。多く含む食品は、青魚、ナッツ類、アボカド、オリーブオイルなど。
- 〔ビタミンB群〕
- 糖質や脂質、タンパク質をエネルギーに変える際の潤滑油のような役割を担います。特にB1、B2、B6は疲労回復に大切です。多く含む食品は、豚肉、レバー、うなぎ、卵、納豆、玄米など。
- 〔ビタミンC〕
- ストレス対抗ホルモンの生成を助け、鉄分の吸収を高めます。活性酸素を除去する抗酸化作用があります。多く含む食品は、パプリカ、ブロッコリー、じゃがいも、キウイフルーツなど。
- 〔ビタミンE〕
- 強い抗酸化作用で細胞の老化を防ぎ、血行を促進します。血流がよくなることで、全身に酸素と栄養が届きやすくなります。多く含む食品は、アーモンドなどのナッツ類、かぼちゃ、アボカド、植物油など。
胃腸にやさしい食事法を
胃腸が疲れていると、どんなに栄養のあるものを食べてもうまく吸収できず、かえって負担になってしまいます。疲れを感じるときこそ、以下のような胃腸をいたわる食べ方を実践しましょう。また、胃腸の調子が優れないと感じたら、思い切って食事の量を減らし、内臓を休ませるのも有効なセルフケアです。
消化の悪いものは避ける:消化に時間のかかる脂っこいものや、刺激の強い香辛料、硬い食べ物は避けるのが賢明です。
温かいものをとる:冷たい飲食物は胃腸の働きを鈍らせるので、なるべく温かいものを選びましょう。水分補給の際も、冷たい水を一気に飲むのではなく、常温以上のものを10分に100ml程度、ゆっくり飲むのがおすすめです。
食べやすく調理する:食材を細かく切ったり、繊維を断つように切ったりすることで消化しやすくなります。加熱する際は、「煮る」「蒸す」「茹でる」といった油を使わない調理法が胃腸への負担を減らします。
よく噛んでゆっくり食べる:唾液の分泌が促され、消化を助けると共に、食べ過ぎを防ぐことにもつながります。
以下の記事では、消化にいい食べ物やレシピを紹介しています。参考にしてみてください。
疲れやすい人ほど適度な運動を
「疲れているのに運動なんて... 」と思うかもしれませんが、実は疲れやすい人ほど、適度な運動が心身のコンディションを整える鍵となります。
適度な運動は、全身の血行を促進します。筋肉や脳に新鮮な酸素と栄養が効率よく届けられ、疲労物質の排出もスムーズになります。継続することで筋肉量が増えれば、基礎代謝が上がり、エネルギーを生み出しやすい、疲れにくい体質へと変わっていきます。
大切なのは、無理をしないこと。自分の体力に合わせて、心地よいと感じる程度の強度と時間から始めましょう。例えば、ウォーキングや、ゆったりとしたヨガ、ストレッチなどがおすすめです。
特別な運動時間を設けなくても、エレベーターを階段に変えたり、一駅手前で降りて歩いたりするなど、日常生活の中で体を動かす機会を増やすだけでも効果はあります。運動はストレス解消にもつながり、心身をリフレッシュさせてくれます。
質の良い睡眠を
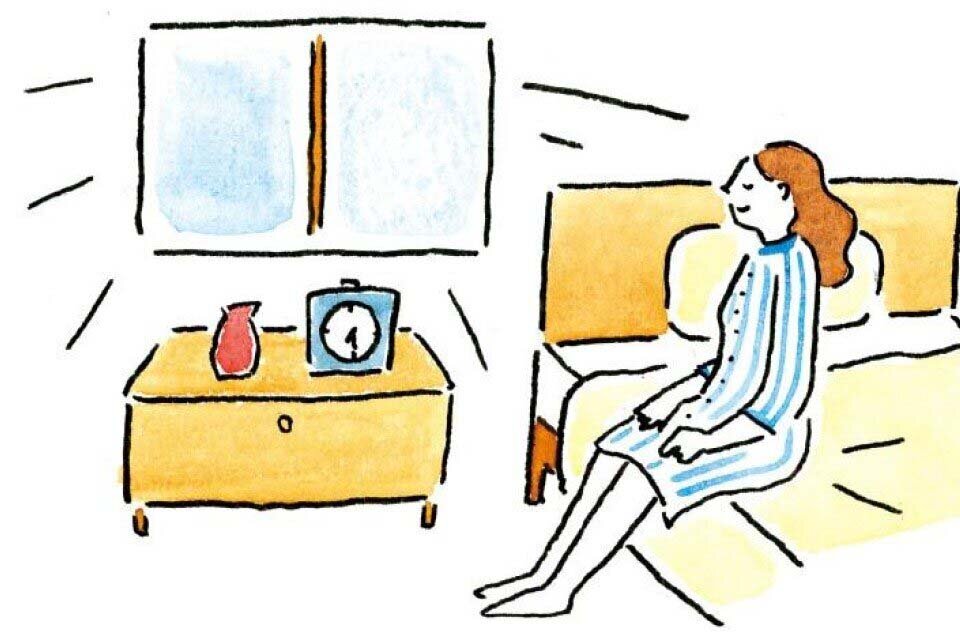
疲労回復において、睡眠はもっとも重要です。私たちは眠っている間に、日中の活動で傷ついた細胞を修復し、脳の疲労をリセットしています。ただ長く寝るだけでなく、「睡眠の質」を高めることが、すっきりとした目覚めには不可欠です。質の良い睡眠を得るためには以下のような方法があります。
就寝時刻の1~2時間前に入浴する:就寝1〜2時間前にぬるめのお湯にゆっくり浸かると、一時的に上がった深部体温が下がるタイミングで自然な眠気が訪れます。
就寝前の行動を見直す:寝る直前の食事やカフェイン、アルコールの摂取は睡眠を浅くします。また、スマートフォンやテレビの光は脳を覚醒させてしまうため、就寝1〜2時間前には控えるのが理想です。
寝室の環境を整える:部屋はできるだけ暗く、静かにし、寝具は季節に合った心地よいものを選びます。
起床後すぐに日光を浴びる:朝起きたらすぐにカーテンを開けて太陽の光を浴びる習慣は、体内時計をリセットし、夜の快眠につながります。
以下の記事では、睡眠を深くする習慣について紹介しています。
外出してリフレッシュ
気分が晴れず、なんとなく体が重いと感じるときは、思い切って外に出てみるのがおすすめです。外出は自然と体を動かす機会となり、気分転換にもなります。近所を少し散歩するだけでも、屋内にこもっているのとは気分が大きく変わります。
外出先で人と会って会話を楽しむことも、同様に心を軽くし、ストレスを解消できます。心と体の疲れを感じたら、十分な休養をとってから、一歩外へ踏み出してみましょう。
血行をよくして代謝を活発に

血行がよくなると、体の隅々の細胞まで酸素と栄養がしっかりと届けられ、エネルギーが効率よく産生されていきます。同時に、疲労の原因となる老廃物もスムーズに回収・排出されるため、疲れがたまりにくくなります。
これまでに紹介した食事、運動、入浴、ストレスケアといった改善法は、すべて「血行をよくして代謝を促す」という点で共通しています。さらに毎日の習慣に薬用養命酒をプラスするのもいいでしょう。生薬の力が血行を促し、体を内側から温めることで、冷えや肉体疲労といった不調を改善する助けとなります。
- 第2類医薬品 薬用養命酒
- 〔効能・効果〕肉体疲労・冷え症の滋養強壮に
- 〔用法・用量〕1日3回、食前・または就寝前に20mLずつ
すぐに疲れることが病気のサイン?

生活習慣を改善してもなかなか疲れが取れない、あるいは日常生活に支障が出るほどのだるさが続く場合は、その背後に何らかの病気が隠れている可能性があります。
疲れやすさは、多くの病気に共通する初期症状でもあるため、安易に「いつものこと」と放置せず、注意深く自分の体調を観察することが大切です。
例えば、以下のような病気が、疲れやすさの原因となっている可能性があります。
- 貧血(特に鉄欠乏性貧血)
- 慢性疲労症候群(筋痛性脳脊髄炎)
- 甲状腺機能低下症
- 糖尿病
- 自律神経失調症
- うつ病
- 更年期障害
- 睡眠時無呼吸症候群
また、肝臓や腎臓、心臓の病気、がんなどが潜んでいる場合もあります。
眠れないほどの不調やセルフケアを試みても改善しないひどい疲れが続く場合は、自己判断せずに必ず医療機関を受診してください。
肉体疲労の滋養強壮に「薬用養命酒」

薬用養命酒は14種類の生薬の薬効成分を、アルコールの抽出作用で引き出した「薬酒」です。胃腸虚弱、食欲不振、血色不良、冷え症、肉体疲労、虚弱体質、病中病後の滋養強壮に効果的で、体の基本的な働きや体質を整えながら、健康に導きます。個人差はありますが、毎日飲み続けて2カ月くらいで効果が感じられるようになります。
- 第2類医薬品 薬用養命酒
- 〔効能・効果〕肉体疲労・冷え症の滋養強壮に
- 〔用法・用量〕1日3回、食前・または就寝前に20mLずつ
この方にお話を伺いました
養命酒製造 健康情報局

薬用養命酒愛飲家向け健康情報誌『養命酒だより』や会員向けメールマガジン『元気通信』を発行。
医師や専門家の監修のもと、健康に関する情報発信を行っている。



















