山や森などで深呼吸すると、スーっと気持ちがラクになったり、爽快な気分になったりしますよね。そんな森林浴の効果について、6月4日に開催したクロモジ研究会のメディア向けのツアーで、東京大学名誉教授の谷田貝光克先生に教えていただきました。
近年の研究で、森林浴をすると、疲労回復や睡眠改善などのさまざまな効果が得られることがわかってきています。
なかでも、日本全国の森に自生する「クロモジ」のストレス軽減や精神を安定させる香気成分や、その他の機能性成分が注目を集めています。
詳しくききました。
森林浴と香りの関係
「香りはまず鼻腔の上にある粘膜を経て、すばやく脳を刺激します。それだけでなく、気道から血管に乗り、体内を循環。こうしたことから、香り成分はたとえ微量でもさまざまな形で人の体に影響を与えます。
森の香り成分としてもっとも有名なのは、α-ピネン(アルファ-ピネン)という成分。含有量の差はありますが、ほとんどの木に含まれているため、森に入ったとき最初に香るのがこの成分です。」
日本でよく見られる木々の香りと効能
[クロモジ]
爽やかさとほのかな甘さを併せもつ香り。鎮静作用や抗不安作用がある成分を多く含むため、ストレスの緩和や心身のバランス調整に最適。

[スギ]
軽やかな森林の香り。森林浴効果が高く、リラックスやリフレッシュ、疲労回復などに有効。

[ヒノキ]
温かみのある木の香り。免疫力を高める香り成分「a-ピネン」が含まれる。疲労回復、安眠、リラックスの他、やる気アップにも◎。

[ゆず]
日本に伝わったのは飛鳥時代から奈良時代の頃。香り成分「リモネン」は血行をよくし、体を温める効果がある。気持ちを落ち着けたい時にもよい。

森林浴によって得られる睡眠改善効果
「多くの木に含まれているα-ピネンは、質のいい睡眠を促すと考えられています。
睡眠改善効果があるといわれているラベンダーの精油と、入眠するまでの時間や睡眠効率(就床時間に対する睡眠時間の割合)について比較した実験では、ラベンダーに比べてα-ピネンの方が早く入眠し、睡眠効率も高いという結果もでています。」
◯香り別・入眠するまでの時間比較
◯香りによる睡眠効率
出典元:恒次祐子「Cosmetology」vol.26、2018年
こうした研究から、枕などの寝具に森の香りを活用した商品が開発されたり、情操教育に木造校舎が取り入れられたりしているそうです。
「それぞれの木、特有の香り成分も注目です。たとえば、スギの精油に多く含まれる成分には、胃潰瘍の進行を抑えることが実証されています。また、近年注目を集めつつあるのがクロモジという樹木です。」
クロモジについて
「クロモジは、スギ林の下によく見られるクスノキ科の低木で、日本全国広い地域に自生する落葉樹です。
クロモジから採れる精油の主成分は、抗炎症や鎮静作用のあるリナロールやゲラニオール。ゲラニオールはバラの香りの主な成分です。そしてα-ピネンも含まれています。」
◯クロモジの精油成分
クロモジの効能とは
「クロモジ精油を嗅いだときの人への影響を測定した研究では、副交感神経の働きが優位になり、緊張状態を示す脳のβ波(ベータ波)が減少するという結果が得られました。この実験の結果からクロモジの香りが、ストレス解消や精神安定につながると期待できます。
また、クロモジから作ったエキスに含まれるポリフェノールの一種がウイルスの増殖を抑えるとして、看護師の男女134名を対象に行ったインフルエンザ予防への効果を報告した研究*もあります。」
*伊賀瀬道也「薬理と治療」vol.46、2018年
クロモジの使われ方
「クロモジは香りが良いため、昔から和菓子を食べるときなどに使われる楊枝に使われてきました。宮沢賢治も自身の作品の中で、クロモジの香りの良さについて度々触れています。
神様に供える榊(サカキ)が育成しない北の地域では、かつて代わりにクロモジを使ったといい、民俗学者の柳田国男はクロモジを「神の木」と称しました。クロモジは、昔の日本人の生活風景の中に深く息づいていた植物といえるでしょう。」
「近年では、白神山地や奥多摩などでも、一般の方向けの森林セラピーツアーを行うようになり、また東京でも、青森や岐阜のクロモジ精油を見かけるようになりました。」
クロモジは、シンボルツリーとして自宅で栽培することも可能です。
日本全国に自生するクロモジをはじめ、森の木々それぞれに注目し香りを比べてみれば、より充実した森林浴の時間が過ごせそうですね。
この方にお話を伺いました
東京大学名誉教授/理学博士 谷田貝 光克 (やたがい みつよし)
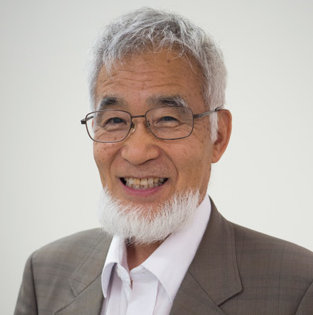
1943年栃木県生まれ。1971年東北大学大学院理学研究科博士課程修了。米国バージニア州立大学化学科及びメイン州立大学化学科博士研究員、農林省森林総合研究所生物活性物質研究室長、同森林化学科長などを経て、1999年東京大学大学院農学生命科学研究科農学国際専攻教授。2006年より東京大学名誉教授。2011~18年フレグランスジャーナル社「香りの図書館」館長。専門は天然物有機化学。


















