「寝ても疲れが取れない」「眠気が取れない」「朝からだるい」。そんな経験はありませんか? 1日ですぐ回復するなら問題ありませんが、それが慢性疲労のように感じるなら、もしかしたら「脳疲労(または「脳の疲れ」)」に陥っているのかも。
現代人に多い脳疲労とは何か、体がスッキリしない原因とその対処法などを医師が解説します。
- 〔目次〕
- いくら寝ても疲れが取れない... 原因は「脳疲労」かも?
- 脳疲労を引き起こす原因をチェック!
- 寝ても疲れが取れないときの対処法は?
- 病気が隠れているかも? 改善しない場合は医療機関の受診を
- 疲れ・睡眠不足は、老化や太る原因に!?
いくら寝ても疲れが取れない... 原因は「脳疲労」かも?
脳疲労とは、ストレス過剰が続いたために脳が適応できなくなり、働きが低下してしまう状態です。
常にメールやLINEをチェックしないと気が済まないなど、四六時中スマートフォンが手放せない人は、脳が情報過多状態。体は疲れていなくても脳は疲れていて、脳が休養不足状態に陥っています。
また、仕事や家事の段取りが常に気になる人、気をつかい過ぎる人も脳の休養不足に陥りやすいといえるでしょう。
脳疲労が起こると睡眠を取っても疲れが抜けず、日中も眠気や倦怠感に襲われ、集中力が続かなかったり判断力が鈍ったりしてしまいます。それが続くと、体を使っていないのにヘトヘトになったように感じたり、気持ちが沈んでイライラしたりと、日常生活や人間関係にも悪影響を及ぼしてしまうので注意が必要です。
脳疲労を引き起こす原因をチェック!
脳疲労を引き起こす原因は1つではありません。以下のような日常の生活習慣や環境が、複合的に影響し合って蓄積されます。心当たりがある項目が1つでもある人は注意しましょう。
睡眠不足
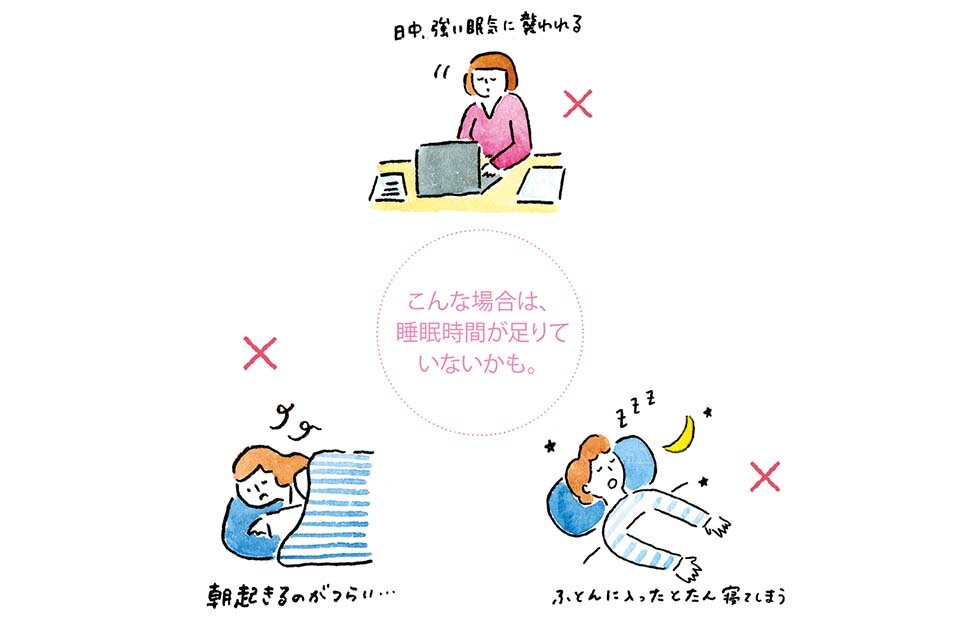
ふとんに入ったら数分で寝てしまうという人は寝不足です。その他、朝起きるのがつらい、日中強い眠気に襲われる場合も睡眠不足の可能性があります。
睡眠には、記憶を整理して傷ついた細胞を修復し、脳や体の疲労を回復して体の成長を促すという重要な役割があります。十分な睡眠が取れないと脳の疲労が蓄積され、集中力や思考力が低下して仕事や日常生活に支障をきたすことに。
また、肥満や高血圧、糖尿病、心疾患、脳血管疾患などの生活習慣病になる危険性も高まることもわかっています。
睡眠不足は睡眠時間が足りない場合だけでなく、睡眠の質が悪い、睡眠リズムが崩れているなどの場合にも引き起こされます。
栄養不足
私たちの脳は、重さにすると全体重の約2%にすぎませんが、食事などから得るエネルギーの約18%を消費しています。脳がこれほど大量のエネルギーを必要とするのは、千数百億個といわれる膨大な数の神経細胞の活動を支えるためです。
そんな脳が栄養不足になると、エネルギーが不足して脳疲労の原因に。神経伝達物質のバランスも崩れるため、イライラや落ち込み、意欲の低下など、心の状態も不安定になります。
運動不足
運動不足になると筋肉量が低下し、新陳代謝が悪くなります。すると、血液や水分の循環も悪くなり、疲れがたまりやすい体になってしまいます。
適度な運動は寝つきを良くして睡眠の質を高めますし、ストレスを解消する効果もあります。運動不足になることで、これらの効果も得られなくなり、脳疲労が悪化しやすくなってしまうのです。
ストレスなどによる自律神経の乱れ
脳の疲労が蓄積すると、起床後の副交感神経から交感神経への切り替わりがスムーズにできなくなり、気だるさが続きやすくなります。逆に、自律神経を酷使することによって脳が疲労する場合もあります。
例えば暑い日に、屋外と冷房が効いた室内を行き来していると、体温調節のために血管の拡張や収縮も担っている自律神経が酷使されます。すると自律神経中枢も酷使されるので、脳疲労のリスクも高まるのです。
この他、過剰な運動による疲労や長時間のデスクワークなどによる精神作業疲労も自律神経が酷使されるシーン。パソコン画面など近距離を見続けることも、交感神経の過剰反応を招きます。
スマホやパソコンの見過ぎによる情報過多
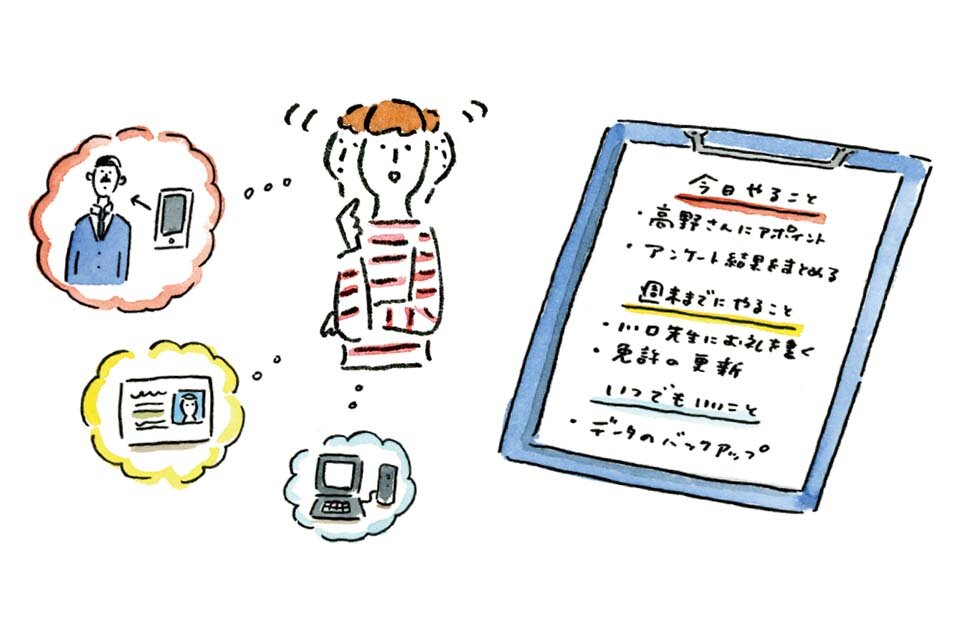
脳のキャパシティはある程度決まっていて、一度にインプットできる情報量や、情報処理能力には限りがあります。
しかし現代は、インターネットやスマートフォンで、いつでもどこでも情報を収集できる環境にあり、脳の容量を超える情報がインプットされることに。
その結果、体は疲れていなくても脳は疲れていて、脳疲労に陥ってしまうのです。
体内時計の乱れ
1日は24時間ですが、人間の体内時計は24時間よりも少し長めです。このズレを修正するのに重要なのが「光」です。
夜遅くまで明るい照明の下で起きていたり、朝遅い時間まで寝て太陽の光を浴びるのが遅くなったりしていると、時刻が同調できずに体内リズムが乱れてしまいます。
そうした生活を続けていると、寝付くのが遅くなって睡眠不足になったり、深い睡眠が減って睡眠の質が悪くなったりして、結果的に脳疲労の蓄積を招いてしまうのです。
ホルモンバランスの乱れ
女性は生理周期によってホルモンバランスが変動するため、「眠れない」「眠りが浅く、すぐに目が覚めてしまう」「いくら寝ても眠い」など、不眠や過眠の症状に陥る人が少なくありません。女性ホルモンの分泌量が大きく低下する更年期にも、不眠に悩まされることが多々あります。
すると、日中に強い眠気や疲労感が生じ、それが重なることで脳疲労に繋がります。また、甲状腺ホルモンが増えすぎたり、減りすぎたりする病気も慢性的な疲労の原因となる可能性があります。
カフェインやタバコの影響
コーヒー豆や茶葉などに含まれる食品成分「カフェイン」には、中枢神経に刺激を与え、眠気を覚ます作用があります。コーヒーなどを日中に飲みすぎたり、寝る直前まで飲んだりしていると、睡眠の質が低下して脳疲労に繋がる可能性が。
タバコに含まれるニコチンにも覚醒作用があり、入眠を困難にしたり、中途覚醒しやすくなったりします。これも脳疲労の回復を阻害する一因といえるでしょう。
寝ても疲れが取れないときの対処法は?
今日からすぐに生活に取り入れられる対処法をご紹介します。
睡眠時間の確保・睡眠の質の改善
必要な睡眠時間は個人差がありますが、成人の場合は6〜8時間が目安と考えられています。一般に、睡眠時間が6時間未満の人は疲れをためやすいので、睡眠時間をしっかり確保すること。そして、睡眠の質も同時に高めることが「寝ても疲れが取れない」状態を改善するポイントです。
そのためには、まず体内時計を整えること。朝起きたらカーテンや雨戸を開け、自然の光を部屋の中に取り込みましょう。反対に、夜に強い照明を浴びすぎると睡眠に悪影響が出るので注意しましょう。
睡眠の質を上げるには、睡眠環境を整えることも大切です。快眠のための寝室の温度は個人差がありますが、夏は28℃以下、冬は16℃以上、湿度は夏・冬ともに50%〜60%といわれています。
エアコンや加湿器などを上手に利用して快適な温湿度にし、自分に合った枕やマットレスを選びましょう。
就寝1.5~2時間前に38~40度くらいのお風呂に浸かると、入浴後、熱が放散されやすい体になり、スムーズな入眠につながります。寝室はテレビなどはつけずに静かな環境にし、遮光カーテンで暗くするなど、心地よく眠れる工夫を。
寝る時間から4時間以内のカフェイン摂取は睡眠の質を下げる可能性があるのでやめましょう。
心を落ち着かせる作用のあるアロマエッセンシャルオイル(精油)などを活用するのはおすすめです。下記記事では、安眠におすすめのアロマを紹介しています。こちらもあわせて参考にしてください。
栄養バランスの良い食事をとる
脳の疲労回復には、三大栄養素(炭水化物(糖質)・脂質・タンパク質)が必要で、ほかにも脳の働きをサポートするビタミンや鉄をとることが大切です。
炭水化物は糖質と食物繊維から構成されていて、糖質はブドウ糖に消化され血液中に取り込まれます。脳がエネルギー源として利用できる栄養素は、ほぼこのブドウ糖のみ。
そのため、食事で炭水化物をしっかりとり、エネルギー供給が滞りなくできる状態を維持することが大切なのです。炭水化物は、ご飯、パン、麺類、いも類、砂糖、果物などに多く含まれています。
脂質は肉類の脂肪分や魚の油、ナッツ類、乳製品、調味に使う油脂類などに多く含まれる栄養素。消化管で吸収された脂質はタンパク質と結合し、ホルモンなどの材料やエネルギー源として使われます。
タンパク質は消化されてアミノ酸となり、筋肉や骨、皮膚、毛髪、血液、ホルモンなど、人体の新陳代謝に使われるほか、脳の神経活動の伝達に不可欠な神経伝達物質をつくる働きもしています。
食品としては、肉や魚(脂身以外)に多く含まれています。
そして、糖質からエネルギーをつくるのに不可欠な栄養素がビタミンB1です。ビタミンB1は体の中でつくることができないため、食品など外から摂取しなければなりません。豚肉、うなぎ、玄米、豆類などに多く含まれています。
鉄は健康維持に欠かすことのできない必須ミネラルの1つ。赤血球のヘモグロビンの構成成分となり、酸素を全身の組織に運搬する重要な働きをしています。女性は生理によって鉄が不足しやすいので、意識してとるようにしましょう。
また、妊娠中や授乳中の人、成長期の子ども、食が細い高齢者、出血性疾患のある人なども鉄が不足しやすいので意識的な摂取が必要です。
適度な運動をする
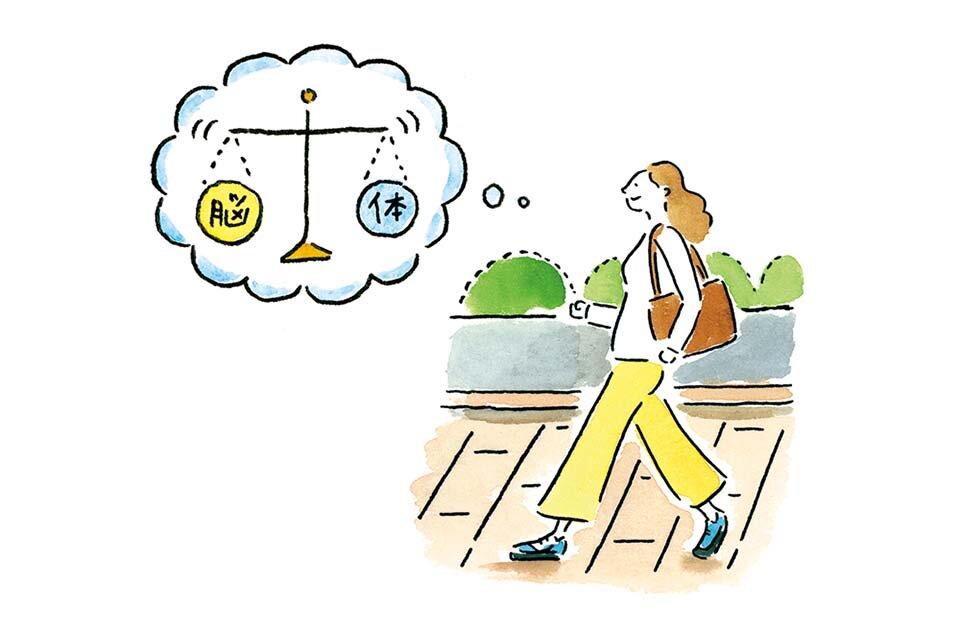
疲れが取れないからといって動かずにいると、副交感神経の優勢な状態が続き、脳と体ともに疲労回復が遅くなってしまいます。かといって、キツイと感じるほどの運動をしてしまうと、さらに疲労がたまってしまいます。
そこでおすすめなのが「積極的休息(アクティブレスト)」。疲労時に軽く体を動かすことで血流の改善を図るもので、疲労物質の排出を促すことができます。また、筋肉を動かすことで、精神を安定させる働きがある神経伝達物質「セロトニン」の分泌も促されるため、リラックス効果が期待でき、ストレス解消にも役立ちます。
具体的にはストレッチ、ウォーキング、軽いジョギングなど、平日にも取り入れやすい有酸素運動がおすすめ。1日20〜30分でもいいので、できるだけ毎日続けると効果的です。
ただし、就寝前の激しい運動は、交感神経を優位にしてしまい睡眠の質を下げるため避けましょう。
ハーブやアロマを活用して自律神経を整える
ハーブティーには副交感神経の働きを高める作用が期待できるので、自律神経を整えるセルフケアにおすすめです。
例えば、ジャーマンカモミールやパッションフラワー、リンデンは鎮静作用に優れており、自律神経の乱れを改善する効果があるといわれています。レモンバームやローズマリーは、料理から医療まで幅広く利用されている有名なハーブで、心身を癒やしてくれる爽やかな香りが特徴です。
下記記事ではカモミールの詳しい効能・効果と、日常生活での活用法をご紹介。こちらも参考にしてください。
また、アロマオイルにも体のバランスを回復し、心身をリフレッシュする効果があります。特にラベンダーはリラックス系アロマの代表といわれており、日常使いや眠れない夜などにぴったり。
交感神経に働きかけて血流の増加や気分を向上させる作用があるグレープフルーツや、神経を落ち着かせて緊張や不安を軽減するイランイランなどもよいでしょう。
ティッシュやハンカチに1~2滴垂らして部屋に置けば手軽に香りを楽しめますし、お風呂に数的たらして芳香浴を楽しむのもおすすめです。
スマホやパソコンを使いすぎない
スマートフォンやパソコンなどのデジタルデバイスの使用時間を減らす「デジタルデトックス」も、脳疲労の解消・予防に有効です。
スマホが手元にあると、どうしても通知やメールが気になってしまうもの。そこでまずはお風呂やトイレにはスマホを持ち込まない、食事中にもスマホを見ないなどと決め、スマホを使用する時間を減らすことから始めましょう。
同時に、読書や編み物、料理など、デジタルデバイスを使わずにできる楽しみを見つけるとデジタルデトックスを加速しやすくなります。
また、夜にブルーライトを多く浴びると体内時計の調節が乱れ、睡眠リズムだけではなく睡眠の質も悪くなります。就寝1~2時間前にはデバイスの使用をやめ、「寝室にスマホを持ち込まない」「通知を切る」「寝る直前に返信をしない」などのルールを決めるとよいでしょう。
規則正しい生活を心がける
起床時間や寝る時間が毎日違う不規則な生活は、睡眠の質を低下させます。できるだけ毎日同じ時間に起きて太陽の光を浴び、食事を3食とり、同じ時間に寝ることを心がけ、規則正しい生活をしましょう。こうすることで自律神経のバランスが整って疲れにくくなります。
仕事で夜が遅い方は、早く起きることよりも「毎日同じリズムで生活する」ことを心掛けるとよいでしょう。
休日に寝だめをしようとする人も多いと思いますが、休日に寝すぎると体内時計のリズムが前進し、翌週前半に時差ぼけのような状態を引き起こしてしまいます。平日も休日も、変わらない生活を心がけることが大切です。
寝だめをした上で夜も眠れるという人は、相当寝不足をためてしまっています。ちなみに寝不足のつけは休日に長く寝ればある程度取り戻せますが、前もって寝だめという貯金はできません。
病気が隠れているかも? 改善しない場合は医療機関の受診を
「寝ているつもりだが日中寝てしまう」「寝ても寝ても眠い」「起きたときから疲れている」といった症状が改善しない場合は、病気が隠れている可能性もあります。
例えば、睡眠中に呼吸が繰り返し止まる「睡眠時無呼吸症候群」は、深い睡眠ができないため、自分では寝ているつもりでも日中に過度の眠気に襲われたりします。
また、うつ病や不安障害も精神疲労から「疲れているのに眠れない」「寝ても寝ても眠い」状態を引き起こす重要な要因です。
先述したセルフケアを2週間~1カ月試しても改善が見られない場合は、こうした病気の可能性も。病院の受診を検討することをおすすめします。
かかりつけ医に相談するほか、症状に合わせて内科、精神科・心療内科、睡眠専門医などに相談するとよいでしょう。
疲れ・睡眠不足は、老化や太る原因に!?

疲れはどんな⼈でも感じるもので、休養と栄養をとることで回復すれば何の問題もありません。しかし、気づかずに疲れを放置すると、⽼化や体重増加の原因にも。
疲れを放置し睡眠不⾜になると、体重も中性脂肪値も⾎糖値も上がり、体内の酸化やメタボリック症候群を介して加齢変化を速めることになります。
寝ないでいるとエネルギー消費が多そうな気がしますよね。しかし、睡眠不⾜の状態が続くと脳から体に「戦いや逃⾛に備えておけ」という指令が出て、エネルギー消費を抑えるので太ってしまうのです。この話を知って、ようやく休養をとる⼈もいるのだとか...。早めのケアを心がけましょう。
この方にお話を伺いました
緑蔭診療所 橋口 玲子 (はしぐち れいこ)

1954年鹿児島県生まれ。東邦大学医学部卒。東邦大学医学部客員講師、および薬学部非常勤講師、国際協力事業団専門家を経て、1994年より緑蔭診療所で現代医学と漢方を併用した診療を実施。循環器専門医、小児科専門医、認定内科医、医学博士。高血圧、脂質異常症、メンタルヘルス不調などの診療とともに、ハーブティやアロマセラピーを用いたセルフケアの指導および講演、執筆活動も行う。『医師が教えるアロマ&ハーブセラピー』(マイナビ)、『専門医が教える体にやさしいハーブ生活 』(幻冬舎)、『世界一やさしい! 野菜薬膳食材事典』(マイナビ)などの著書、監修書がある。


















