食べ過ぎや消化の悪い食事をしたときに起こる消化不良。実はストレスや生活習慣の乱れなどもその原因になります。胃腸を健康に保つため、消化不良の予防策と"なってしまったとき"の改善法を紹介します。
消化不良や胃腸の不調の主な原因とは?
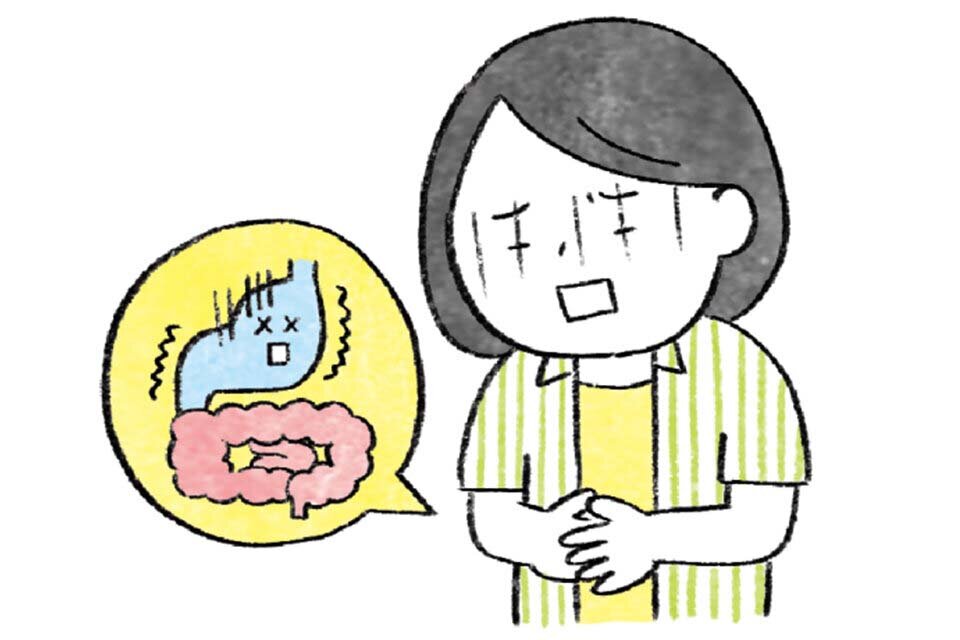
消化不良や胃腸の不調の主な原因として、自律神経の乱れや食べ方が影響する一時的なもの、病気によるものが挙げられます。
不規則な食事時間・睡眠不足
不規則な食事時間や睡眠不足は体内時計を乱し、自律神経のバランスも崩れて胃腸の働きを低下させます。食事時間の乱れは胃酸や消化酵素の分泌のリズムの乱れにもつながり、消化不良を起こすこともあります。
ストレスや疲労
ストレスを感じていたり疲労がたまっていたりするときは、その対処として自律神経のうち交感神経が優位になります。
胃腸の働きは、副交感神経とかかわりが深く、交感神経が優位な状態では胃腸の血流が減ってその働きが鈍くなり、不調を起こしやすくなります。また、過度なストレスによって胃酸が過剰に分泌されると、胃の粘膜が痛んで消化不良を起こすこともあります。
病気や疾患

機能性ディスペプシアや過敏性腸症候群、逆流性食道炎、ヘリコバクター・ピロリ感染胃炎、胃や十二指腸の潰瘍、胃がん、すい臓や胆のうの炎症、胃下垂やそれに伴う胃アトニーなどが原因で消化不良が起こることがあります。
食べ過ぎや早食い
食べ過ぎると、胃酸や消化酵素の分泌が乱れ、消化不良が起こりやすくなります。また、早食いでは食べ物をよく噛まないことが多く、そのため消化を助けたり胃酸を中和したりする唾液の分泌量が減少し、胃に負担がかかります。
消化の悪い食事

脂っこいものや食物繊維の多いもの、硬いものなどは消化しづらく、食べると消化不良を起こしやすくなります。
肥満
運動不足などで肥満になると、逆流性食道炎を起こしやすくなったり、自律神経に影響して胃腸の働きが悪くなったりします。
内服薬やピロリ菌の影響
胃酸抑制剤を服用している人は、胃酸の分泌が低下しているため消化に時間がかかります。また、ピロリ菌によって萎縮性胃炎が起こると胃に不快な症状があらわれます。
消化不良など胃腸不調の症状は?

胃もたれ・膨満感
消化不良が起こると食べ物が胃の中に長く滞ったり、未消化のものが腸に送られると腸でガスがたまったりするため、胃もたれや膨満感が起こりやすくなります。
胸やけ
胃酸の分泌が乱れて食道への逆流が起こりやすくなり、胸やけが生じます。
吐き気・嘔吐
胃酸の分泌の乱れや、胃に食べ物がとどまることや腸にガスがたまることによる圧迫感で、吐き気を催すことがあります。
下痢・便秘
未消化のものが大腸に送られると、ガスが発生したり水分を吸収できなかったりして下痢を起こします。また、腸内環境が乱れると便秘になることもあります。
食欲不振
消化不良によって胃もたれ・胸やけ・吐き気などの症状が起こると、食欲不振の原因にもなります。
食欲不振の際におすすめの食べ物はこちらの記事で紹介しています。
げっぷがでる
胃に食べたものがとどまっていると、胃の中で異常な発酵が起こってガスが生じてげっぷが出やすくなります。また、胃酸の分泌過多や逆流性食道炎もげっぷの原因になります。
消化不良など胃腸の不調を起こしたときの改善法

消化不良などで胃腸が不調なときは、胃腸に負担をかけないように過ごすことが大切です。
消化不良の改善法は、消化の良い食べ物を心掛けることや食後の過ごし方に気をつけること、十分な睡眠をとるなどがあります。以下で具体的な方法を紹介します。
消化の良い食べ物を食べる
消化に良い食べ物を食べて、胃腸を休めることが大切です。消化に良い食べ物とは、「食物繊維と脂質が少なく、胃腸に負担がかかりにくいもの」や「消化酵素を含み、胃腸の働きを助けるもの」。具体的には以下の通りです。
- 〔消化の良い食べ物〕
- 大部分が炭水化物であるうどんやおかゆ
- 脂の少ないささみや白身魚
- 消化酵素を含む大根やバナナ
- 消化しやすく胃粘膜を守る働きもある牛乳やヨーグルトといった乳製品
中でもやわらかめのうどんは、消化しやすく、体に必要なエネルギーにもなるのでおすすめです。逆に、乳製品はお腹を壊しやすい人も多いので、冷たい牛乳をゴクゴク飲むことは控えましょう。乳糖不耐症の人も注意が必要です。
消化に良い食べ物やレシピは以下の記事でも紹介しています。
よく噛んでゆっくり食べる

ゆっくりとよく噛んで食べると、消化を助けたり過剰な胃酸を中和したりする唾液の分泌が増えると共に、食べたものが細かく噛み砕かれることで消化酵素が働きやすくなります。また、ゆっくり食べると満腹感を得やすくなり、食べ過ぎも防げます。
食後の過ごし方に気をつける
体を起こした状態にしていると、重力で食べたものが流れやすくなり消化が促されます。反対に食べてすぐに横になると、流れるのに時間がかかるのに加え、胃酸が逆流しやすくなります。食後30分~1時間は座っていたほうがよいでしょう。
食べてすぐに体を動かすと、胃腸に集まるべき血液が筋肉に集まってしまうため、消化に影響が出てしまいます。また、食べ物がお腹の中にある状態なので吐き戻してしまうことも。食事を終えて30分ぐらいは体を休め、その後に散歩などで軽く体を動かすと、基礎代謝が上がり胃の働きも活性化します。
また、食後にストレスを感じるような予定があると胃腸の働きが低下してしまうため、緊張を伴う用事などは入れないようにするとよいでしょう。
食後の正しい運動方法については以下の記事で解説しています。気になる方はチェックしてみてください。
白湯を飲む
白湯を飲むと副交感神経の働きが高まり、リラックスモードになって胃の調子が整います。また、胃が温まって血流がよくなり、消化が促されるほか、過多になっている胃酸の中和にも役立ちます。
十分な睡眠をとる
まずは、よく眠ることを意識しましょう。睡眠不足や質の低い睡眠では疲れが蓄積しやすく、自律神経が乱れて胃腸の働きが損なわれ、免疫力の低下にもつながります。
胃腸は副交感神経と関わりが深く、リラックス時や睡眠時といった副交感神経が優位なタイミングで消化活動が活発になります。逆に睡眠不足の状態では、交感神経が活発になり、胃腸の働きは低下します。
市販薬を服用する
「胃酸の分泌を抑える」「胃酸を中和する」「消化を助ける」「胃粘膜を修復する」など、医薬品にはさまざまな効能があります。大切なのは、何を飲むかということ。安易に自己判断はせず、ほかに服用している薬との飲み合わせなども鑑み、薬剤師や登録販売者に相談して利用しましょう。2~3日使ってみて症状が改善しないようなら医師に相談してください。
消化不良など胃腸の不調を起こさないための予防法

腹八分目を心がける
食べ過ぎは胃腸に負担をかけます。腹八分目を心がけると、食べ物が胃にとどまる時間も短縮できるでしょう。
心身ともにストレスをためない
生きていれば避けることのできないストレスですが、ストレスは胃腸の働きを低下させます。ストレスの原因は人それぞれです。その原因を明らかにし、距離をとったり、気持ちを落ち着かせる行動をとったりするなど、自分なりのストレス軽減法に取り組みましょう。
タバコ・アルコールを控える
タバコに含まれるニコチンの働きにより、胃腸の血流が低下し消化不良が起こりやすくなります。また、アルコールは、胃の粘膜を傷付けたり胃酸を過剰に分泌させたりすることがあります。胃腸の健康を守るためには、どちらも控えることをおすすめします。
適度な運動をする
運動は、血行を促し、胃腸と関係が深い自律神経の調整や免疫の活性化に役立ちます。また、気分転換やリラックスにつながり、ストレスの発散にも有効です。散歩程度でいいので体を動かす習慣を身につけるよいでしょう。
十分な睡眠をとる
よく眠ることを意識しましょう。胃腸は副交感神経とかかわりが深く、リラックス時や睡眠時といった副交感神経が優位なタイミングで消化活動が活発になります。
消化不良に関するQ&A

消化不良など胃腸が不調なときに避けるべき食べ物は何?
以下のような胃腸に負担をかけるものは避けたほうがよいでしょう。
- アルコールや香辛料、酸っぱいものといった刺激が強いもの
- 揚げものなどの脂っこいもの
- きのこ類など食物繊維が豊富なもの
- 味付けの濃いもの
- 消化に時間がかかるタンパク質
また、冷たい飲み物の一気飲みやとり過ぎは、胃腸を冷やし、その働きを低下させるので控えてください。
消化不良など胃腸の不調のときに考えられる病気は?
機能性ディスペプシアや過敏性腸症候群、逆流性食道炎、ヘリコバクター・ピロリ感染胃炎、胃や十二指腸の潰瘍、胃がん、すい臓や胆のうの炎症、胃下垂やそれに伴う胃アトニーが考えられます。
機能性ディスペプシアや過敏性腸症候群は、胃腸の不調が続いているものの検査をしても原因として説明できる疾患がなく、よく似た別の病気の可能性が除外されて、初めて診断されるものです。診断される人やそれに近い症状の人は多いので、心当たりがある場合は医師に相談することをおすすめします。
この方にお話を伺いました
聖マリアンナ医科大学消化器内科教授、大学病院消化器内科医長、大学病院内視鏡センターセンター長、大学病院臨床研修センター副センター長、教授、医学博士 前畑 忠輝 (まえはた ただてる)

『決定版! 胃腸を強くする名医のワザ』を監修。近年は、内視鏡診断・治療技術の高度化に加え、VRを用いた医療技術教育や腸内細菌研究による大腸がん早期発見にも取り組み、臨床・研究・教育を通じて次世代医療の発展を目指している。


















