自分ではなかなか気づくことができない体臭。
体臭は、知らないうちにストレスや生活習慣の乱れ、加齢などによって変化することがあります。身近な人や街中でほかの人のにおいが気になって、自分も心配になった...という経験はありませんか?
そこで、においの種類別に体臭の原因をご紹介。あわせて、チェックリストで自分の体臭の元になりそうなポイントを確認し、今日から対策を始めましょう。
体臭の原因と基本的な仕組み
体臭の原因は、汗の成分や皮膚の常在菌です。
皮膚には皮脂や汗が分泌されており、これらが混ざり合うことで皮脂膜がつくられ、肌を保湿しています。
ところが、時間が経って皮膚の常在菌や雑菌が作用すると、汗や皮脂、アカに含まれる成分が分解され、不快なにおいのするガス(揮発性成分)を発します。これが「体臭」と呼ばれるものです。
汗には大きく分けて「エクリン汗腺から出る汗」と「アポクリン汗腺から出る汗」の2種類があり、それぞれ発生するにおいが異なります
エクリン汗腺から出る汗ははじめは無臭
エクリン汗腺はほぼ全身の皮膚表面にあり、体温を調節し,皮表に適当な湿度を与える仕事をしています。分泌される汗は水分と塩分、ミネラルなどで構成されており、無臭です。
しかし、放っておくと脂肪酸やアカ、皮膚の常在菌と混ざって嫌なにおいを発するようになります。
アポクリン汗腺から出る汗は強いにおいのもとに
アポクリン汗腺は、主に脇や性器周辺などにあります。出る汗は白く濁っていて、脂質やタンパク質、アンモニアなどにおいのもととなる成分を多く含んでいます。
もともとはフェロモンの役割を果たしていたともいわれています。
汗が表皮の常在菌に分解されると、エクリン汗腺の汗よりも強いにおいを発します。
体臭にはどんな種類がある?
体臭の原因は汗や皮脂だけでなく、加齢や不規則な生活習慣、腸内環境の悪化などさまざま。
最近では、ストレスが原因となるにおいや、若い人でも増えている早期加齢臭と呼ばれるにおいもあるそうです。におい別に、その原因を確認しましょう。
酸っぱいにおい
酸っぱい体臭は、弱った汗腺からベタベタの汗が分泌されることで起こります。
そもそも、人間の汗の99%はにおいのない水分。通常ミネラルは汗腺から再吸収されますから、汗にはほんの少しのミネラルしか含まれていません。ところが、汗腺の機能が低下していると再吸収が行われにくくなり、ミネラル成分の多いベタベタ汗に。
ベタベタ汗をかくと、汗がなかなか乾かず、皮膚の常在菌がミネラルやアカなどをえさにして繁殖します。その結果、常在菌が発する酸っぱいにおいが体臭となって出てしまうのです。
酸っぱいにおいが気になる場合は、運動や入浴で汗腺を鍛える対策をしましょう。
ストレス臭

ストレス臭は、日頃のストレスや疲れ、緊張によって起こります。
ストレス臭は、さまざまなにおい物質による複合臭。議論がヒートアップしている会議室に遅れて入ったときに、汗の中に混じるSTチオジメタンというネギのようなにおいや、アンモニアのようなにおいを感じたら、それらがストレス臭です。
ストレスを感じた際に発生する活性酸素の影響による皮脂の酸化や、慢性的な疲れ・ストレスや緊張などによる自律神経の乱れが、体臭の原因となることが分かっています。
また、緊張して交感神経の働きが優位な状態では、手のひらや足の裏からの発汗量が増加。高温多湿の状態となった足の裏で増殖した常在菌は、納豆や銀杏のようなにおいがします。
これらが複合して、独特なストレス臭となっているのです。
ストレス臭が気になる方は、ハーブを活用して自律神経のバランスを保つことがおすすめです。
生ゴミのようなにおい(キャベツ臭)
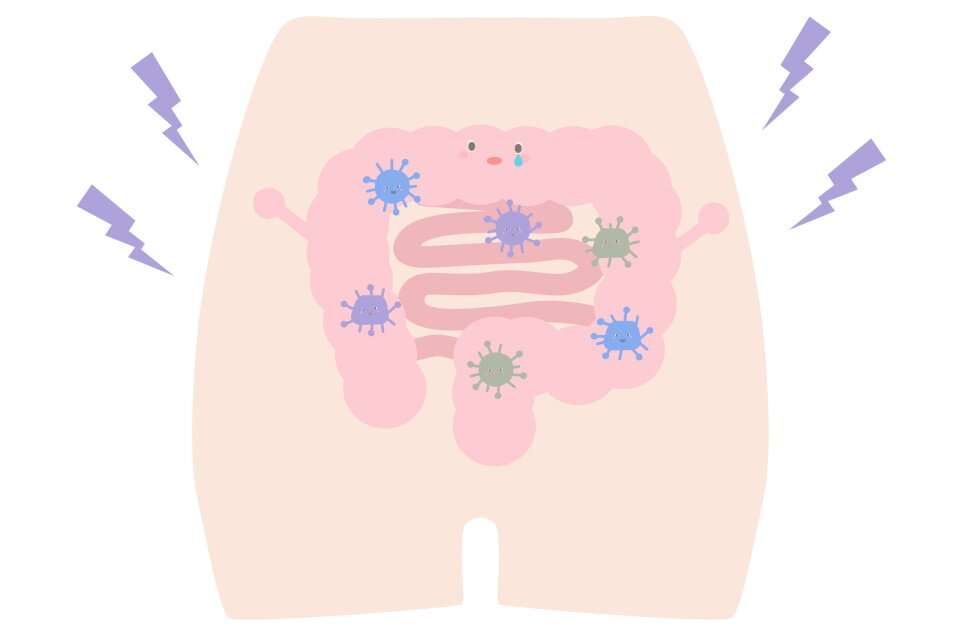
生ゴミのようなにおいの「キャベツ臭」は、腸内環境の悪化や肝機能の低下によって起こります。
胃腸機能の低下による消化不良から腸内環境が悪化すると、腸の中で食べ物(主に動物性タンパク質)が腐敗してしまうことがあります。
そのような場合も、通常は腸内で発生したにおい成分は肝臓で分解・無臭化されます。しかし、アルコールの過剰摂取や生活習慣病などによって肝機能が低下していると、そのにおい物質を処理できず、血液中にあふれることが。
その結果、呼気を通してキャベツのような生ゴミに似たにおい(ジメチルサルファイド)が、口臭として発生。さらに、アンモニアが処理しきれないと、汗の中にもアンモニアがあふれてきます。
生ゴミのようなにおい(キャベツ臭)が気になる方は、食生活を見直すことがおすすめです。
加齢臭
加齢臭は、年齢を重ねることで皮脂の中にパルミトレイン酸という脂肪酸と、過酸化脂質という物質が増加することで起こります。このパルミトレイン酸が過酸化脂質や皮膚の常在菌によって分解・酸化されると「ノネナール」という、ひなびたにおいが発生します。
加齢臭は、男性は40〜60代、女性は個人差がありますが、女性ホルモンが低下する閉経前後の年齢から強くなる傾向があります。このにおいは年齢を感じさせるものの、いわゆる悪臭ではありません。
加齢臭を不快に感じる方は少ないのでご安心ください。
どうしても加齢臭が気になる場合は、こまめに汗を拭き取る、体を洗って湯船に浸かるなど、体を清潔に保つように心がけましょう。
早期加齢臭

近年増えている「早期加齢臭」は、糖質の多い食生活や劣化した油のとり過ぎで起こります。このような食生活を続けていると、皮脂が過剰分泌・酸化し、加齢臭に似た脂くさいにおいが発生します。
実は、皮脂の原料となるのは中性脂肪。糖質をとり過ぎると、血中に余った糖が中性脂肪となるほか、精製された白いご飯や小麦などの炭水化物および白砂糖のとり過ぎによる血糖値の上昇、さまざまな加工食品に含まれている異性化糖(果糖を多く含む糖)のとり過ぎも中性脂肪を増やす原因に。
その結果、皮脂の分泌が過剰になり、20代でも加齢臭が発生してしまうのです。
早期加齢臭にも、食生活を見直す対策が有効です。
まくら臭(ミドル脂臭)

使い古した油のようなまくらのにおい。40代をピークに発生するミドル脂臭とも呼ばれますが、年齢のためだけではなく、シャンプーのし過ぎによる頭皮の乾燥など、皮脂の増加を起こしやすいライフスタイルによって起こります。
頭を洗い過ぎると頭の皮脂が過剰に取れて頭皮が乾燥し、頭皮を守るためにかえって皮脂の分泌量は増加します。そして、皮脂の中の中鎖脂肪酸と汗から発生するジアセチルという成分が合わさって汗と皮脂の混合臭(まくら臭)が発生するのです。
まくら臭(ミドル脂臭)には、頭皮を弱酸性に保つ対策が有効です。
体臭の対策方法を詳しく紹介!
体臭の種類と原因を確認したところで、自分のにおいの元をチェックし、自分の何が体臭の元になるのかを把握しましょう。それぞれのタイプ別の体臭対策もご紹介します。
ただし、におい対策の基本は「かいた汗をにおわせない対策」をすることで、これは全タイプ共通です。制汗剤で汗を抑えたり、こまめに汗を拭いたりして、におい成分を分泌する常在菌が繁殖しやすい環境をつくらないようにしましょう。
殺菌成分入りのデオドラント剤は、肌を守っている常在菌まで抑制してしまい、肌荒れの原因に。脇などにおいが強いところにポイント使いするだけにとどめるのがおすすめです。
運動や入浴で汗腺を鍛える
- 〔こんな方に効果的〕
- □ 運動習慣がなく、普段汗をかかない
- □ 入浴はシャワーが多く、湯船に浸からない
- □ 汗をかくと肌がベタベタして不快に感じる
汗腺は汗をかくほど鍛えられ、におわない汗をかけるようになります。運動習慣や湯船に浸かる習慣をつけましょう。入浴の際は40℃前後のお湯に15〜30分浸かること。
入浴剤はエプソムソルト(硫酸マグネシウム)がおすすめ。血管が開きやすく、保温効果が高まるため、汗をかきやすくなります。
入浴前に水分をコップ1杯以上とることも忘れずに。
おすすめの入浴法については、以下の記事も参考にしてください。
食生活を見直す
- 〔こんな方に効果的〕
- □ 野菜や海藻などの食物繊維が不足しがち
- □ 胃の調子が悪い、便秘がち
- □ 肉をよく食べる
- □ アルコールをよく飲む、または肝機能が悪い
- □ 健康診断で中性脂肪値が高いと指摘される
- □ 朝昼夕の3食以外に間食や甘い飲み物を毎日とっている

腸内環境を悪化させる過剰な肉食や、肝機能を低下させる過度な飲酒、皮脂を増やす糖質の過剰摂取をしていないか、1週間の食生活を振り返ってみましょう。
糖質は炭水化物だけでなく、さまざまな食品に含まれています。清涼飲料水や菓子、調味料などに含まれている果糖ブドウ糖液糖などの異性化糖から知らず知らずにとり過ぎている場合も。食品を選ぶ際は原材料も意識しましょう。
主食は「白」より「黒」のものを意識して、白米や食パン、うどんより精製度の低い玄米やライ麦パン、そばを選ぶようにするとよいでしょう。また、糖質の吸収、血糖値の上昇を抑える食物繊維をしっかりとりましょう。
おすすめの食材は、食物繊維が豊富で腸内環境を整える野菜や海藻類、皮脂の酸化を抑える抗酸化食材(ナッツや植物油、アボカドなど)。積極的に食卓に取り入れるとよいでしょう。
ハーブを活用して自律神経のバランスを保つ
- 〔こんな方に効果的〕
- □ ストレスが多いと感じる
- □ 生活が不規則、睡眠不足
- □ 慢性的に疲れている

いい香りでリラックスして、自律神経のバランスを整えるのも体臭対策に有効。リラックスタイムにお部屋で香りを楽しむのがおすすめです。
また、精油(エッセンシャルオイル)と天然塩(またはエプソムソルト)を混ぜたものを湯船に入れ、リラックスしながら発汗を促し、汗腺を鍛えても◎
リラクゼーション効果のある精油にはラベンダー、カモミール、ゼラニウムなどがありますが、大切なのはそのときに自分が心地よいと感じる香りを取り入れること。苦手な香りはかえってストレスになってしまいます。
頭皮を弱酸性に保つ
- 〔こんな方に効果的〕
- □ シャンプーは1日2回する
- □ エアコンの効いた部屋にいることが多い

頭皮のにおいが気になる場合は、皮脂を取り過ぎず、刺激が少ないアミノ酸系のシャンプーを使用しましょう。
それでも改善しない場合は、2日に1度はシャンプーを使用せず、40℃以下のぬるま湯で頭皮をマッサージしながら汚れを洗い流してみるとよいでしょう。
体臭の原因を知り、日常生活の中でコツコツ対策していきましょう。
この方にお話を伺いました
内科医・認定産業医 桐村 りさ (きりむら りさ)

愛媛大学医学部医学科卒業。tenrai株式会社代表取締役医師。治療よりも予防を重視し、「ホンマでっか!?TV」やWebメディアにてヘルスケア情報を発信。著書に『日本人はなぜ臭いと言われるのか〜体臭と口臭の科学〜』(光文社)などがある。

















