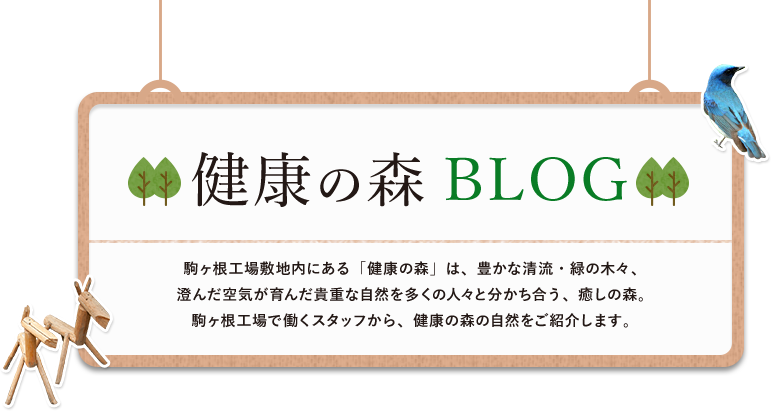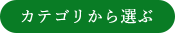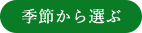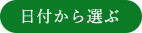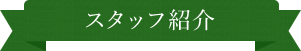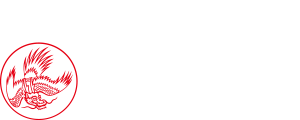植物
-
鳥たちはこの実を秋には食べず、冬になると食べます。
冬、完熟すると渋味が取れて、美味しくなることを知っているんですね。
干し柿と同じというわけです。
" alt="">
こちらは、「コバノガマズミ」の実です。
ガマズミの仲間ですがが、葉っぱが小さいので、
「小葉(こば)のガマズミ」というわけです。
実の付きも、ガマズミに比べると疎らですね。-
気になる木の実 その3
- 2014.10.06 森林担当 やっしん
- これは、「ガマズミ」の実です。 鳥たちはこの実を秋には食べず、冬になると食べます。 冬、完熟すると渋味が取れ...
-
-
名前の由来は、花・実が垂れ下がることによる。
秋になると、果実が割れて、中からのぞいた赤い種(たね)が美しいですね。
" alt="">
こちらは、「イチイ」の実。
子供の頃、学校の帰り道、生垣のイチイの実を取って食べませんでしたか?
実は、種(たね)の方には毒(アルカロイドのタキシン)があるので、
果肉を食べた後、種は飲み込まないように気を付けましょう。-
気になる木の実 その2
- 2014.10.06 森林担当 やっしん
- これは、「ツリバナ」の実。 名前の由来は、花・実が垂れ下がることによる。 秋になると、果実が割れて、中からの...
-
-
" alt="">
紅葉した葉から、どんどん落葉していくので、
道路に落ちている葉っぱは、今はカスミザクラが多いですね。-
山桜の紅葉は一足早い。
- 2014.10.03 森林担当 やっしん
- 中央アルプス駒ケ岳の紅葉は、ロープウエイの終点、 千畳敷辺り(2500m以上)が見頃になっているようです。 ...
-
-
これは、記念館の脇に生えている、「ウダイカンバ」の大木の種です。

高さは20m以上、目の高さの直径も50cm以上のなかなか立派な大木です。
この「ウダイカンバ」はシラカバの仲間(カバノキ科カバノキ属)の中で、
葉っぱが一番大きく、秋には黄色に色付きます。
材は高級家具材として使われ、林業の世界では、
いわゆる有用広葉樹といわれるものの代表格です。記念館の周りには、この大木が玄関の正面と、南側に2本あります。
そして、森林整備で明るくなった森の中には、たくさんの稚樹が見られるように
なりました。この、写真は芽生えて1~2年めのものです。
明るい所が好きなシラカバの仲間の種は、林内に十分に陽が差し込むと、
目覚めて発芽します。こちらの写真は、芽生えて4~5年めのものです。

成長が早いので、高さはすでに3m超えです。
「養命酒 健康の森」では、森づくりの中で、現状のアカマツ林を、
色彩豊かで多様な広葉樹林へと、転換を進めています。この「ウダイカンバ」は、将来の森の主役になる木といっても
" alt="">
いいでしょう。
そういう思いを込めて、大切に育成しています。-
未来へつながるタネ
- 2014.09.24 森林担当 やっしん
- 朝、記念館の周りを掃除していると、舗装の上にたくさんの 小さな種(タネ)が散らばっています。 これは、記念館...
-
-
これは、クロウメモドキ科の「イソノキ」です。調べてみましたら、ハーブの恵みに入っている、
「ナツメ」もクロウメモドキ科の樹木でした。
こちらは、記念館の駐車場の林縁や、縄文住居近くの散策路沿い
で見つけました。
これは、ブルーベリーと同じ、ツツジ科スノキ属の「ナツハゼ」の実です。
以前、「ナツハゼ」のジャムを食べたことがありますが、
まさに森のブルーベリーですね。森には木の実が実り始めて、季節は、夏から少しずつ秋ですね。
" alt="">-
気になる木の実
- 2014.09.02 森林担当 やっしん
- 記念館から駐車場へ降りる階段の右側脇に、 黒い実を付けた木があります。 これは、クロウメモドキ科の「イソノキ...
-
-
裏玄関にも。

そして建物からはみ出した、この緑といったらどうでしょう!?

建物の中、露天吹き抜け階段の踊り場には、2つの緑地があります。
「信州の庭」と、

「生命の庭」です。

どちらも庭というより、「くらすわの森」状態になってきました。
2つの緑地も、樽の鉢植えも、植えられている樹木のほとんどが、
「養命酒 健康の森」(駒ヶ根工場)から移植されたものです。ちょっとボーボーになり過ぎたので、先日手入れに入って来ました。
整備後の写真は撮り忘れてしまいましたので、是非、くらすわに来て見て
ください。現在、諏訪湖ではサマーナイトファイヤーフェスティバルが開催中で、
" alt="">
毎晩20:30頃から約15分程、花火が楽しめます。
くらすわの屋上では、ナイトカフェがオープンしていますので、
生ビール片手に花火はいかがでしょうか?-
くらすわに森?、くらすわの森!
- 2014.08.26 森林担当 やっしん
- 諏訪湖のほとりにある養命酒のショップ&レストラン「くらすわ」には、以外と緑が多いのです。 正面入り口や、 裏...
-
-
「コオニユリ」
信州の夏は短い。
昼間は暑くても夜はすっかり涼しくなりました。草むらからは秋の虫の声が聞かれるようになりました。
というわけで、夏の疲れを癒しに、
" alt="">
「養命酒 健康の森」へいらっしゃいませんか?-
残暑お見舞い。
- 2014.08.25 森林担当 やっしん
- 残暑お見舞い申し上げます。 まだまだ暑い日が続きますので、どなた様もご自愛ください。 「コバギボウシ」 「コ...
-
-
キク科フジバカマ属の「ヒヨドリバナ」です。健康の森では、林内でも見ることができます。
石垣の中に咲いているのは、勝手に種が飛んで来て芽を出したものです。
秋の七草のひとつ「フジバカマ(藤袴)」の仲間で、
" alt="">
渡りをする蝶として知られる「アサギマダラ」が好んで、
蜜を吸いに訪れる花でもあります。-
気になる花は?
- 2014.08.11 森林担当 やっしん
- エントランスのガラス越しに見える、庭園の中で咲いている花は、 キク科フジバカマ属の「ヒヨドリバナ」です。 健...
-
-
これは、ミカン科キハダ属の「キハダ」という木の内樹皮です。
健胃整腸剤としても使われます。夏、水分をたくさん取って胃が弱ってしまう私は、この「キハダ」の
" alt="">
皮を小さく切って、いつもなめています。
ちょっと苦いですが、胃の調子が良くなるので助かります。-
真夏の必需品!
- 2014.08.06 森林担当 やっしん
- 今年も、私の夏の必需品を手に入れることができました。 これは、ミカン科キハダ属の「キハダ」という木の内樹皮で...
-
-

- カフェ担当のんたん
- 食べることが大好き!!
毎日スイーツに囲まれて
幸せです。
-

- 案内担当みっき~
- 毎日自然に囲まれて
いるせいでしょうか。
・・・のんびりやの私です。
-

- 記念館担当ヨメ子
- 森の小さな変化を探し
ながら、四季を楽しんで
いるナチュラル派の私です。
-

- 森林担当やっしん
- 美しい森づくりに
情熱を注ぐ、
森のエキスパートです。