「体力をつける」といっても運動能力だけを指すのではありません。運動が苦手な人でも無理なく実践できる、食事や生活習慣の見直しによる、疲れにくい体のつくり方を紹介します。
体力をつけるための食べ物・食事
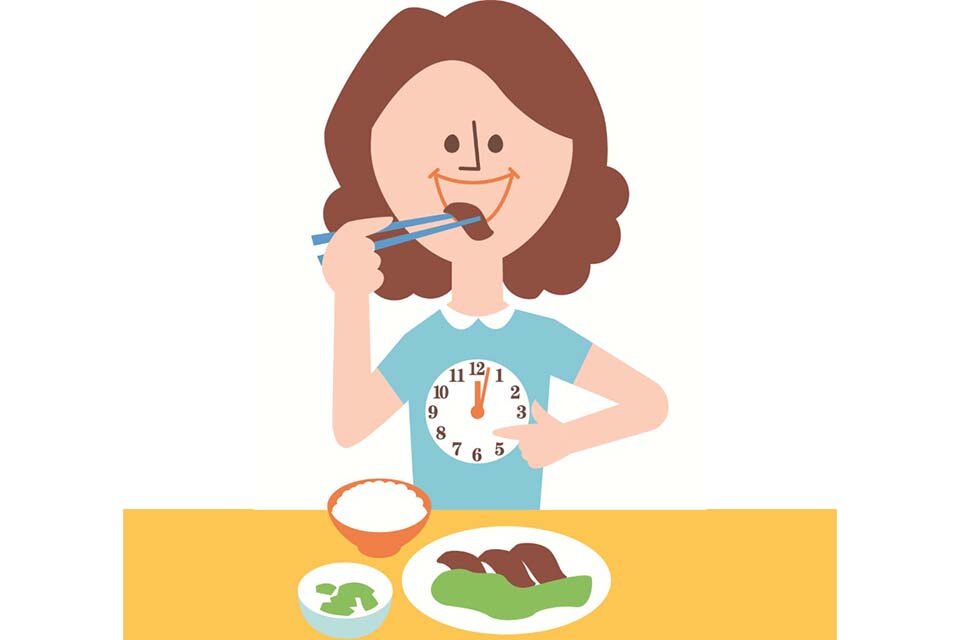
体力をつけるためには、ハードな運動だけでなく、日々の食生活を見直すことも非常に効果的です。ここでは、体力を内側から支える食事のポイントを紹介します。
バランスの良い食事とタイミング
体力をつけるための食事の基本は、多彩な食材を組み合わせた栄養バランスのよいメニューを、1日3食、規則正しくとること。食事のリズムを整えることで、体内時計も整い、エネルギーを効率よく使えるようになります。
なお、ウォーキングやランニングなど体を動かした後は、筋肉の修復が活発になります。特に、運動後30〜45分以内にタンパク質をとると、筋肉の合成が促され、効率的に筋力アップが期待できるのでおすすめです。
どうしても食欲が湧かないときは、無理にたくさん食べようとせず、ヨーグルトやチーズ、果物など栄養価の高い間食を取り入れるのも良い方法です。また、家族や友人と一緒に食卓を囲んだり、彩り豊かな盛りつけを工夫したりと、食事そのものを楽しむ工夫も食欲増進につながります。
体力向上に役立つ栄養素
体力を向上させるためにはバランスのよい食事が基本ですが、その中でも特に意識してとりたいのが「タンパク質」と「ビタミンB群」です。
タンパク質
タンパク質は筋肉や内臓、血液、免疫細胞など、私たちの体をつくる主成分です。重要なのは、体内にタンパク質を貯蔵しておくことができないという点です。そのため、一度にまとめてとるのではなく、朝・昼・晩の3食でこまめに補給する必要があります。
特に注目したいのが朝食でのタンパク質摂取です。睡眠中は食事をとらないため、体内のアミノ酸(タンパク質の構成要素)が枯渇しがちです。朝食でしっかりタンパク質を補給することで、筋肉の分解を防ぐことができます。
ビタミンB群
ビタミンB群は、食事からとった糖質や脂質、タンパク質をエネルギーに変える際に不可欠な栄養素。体内のエネルギー工場の潤滑油のような役割を果たします。ビタミンB群が不足すると、せっかく食事をしてもエネルギーを効率良くつくり出せず、疲労感や倦怠感につながってしまいます。
「薬用養命酒」を飲んで体力をつけよう

「薬用養命酒」は、滋養強壮を目的とした第2類医薬品です。配合されている14種類の自然の生薬とアルコールの力が、体本来の力を引き出す手助けをします。
その作用の基本は、血行を促進し、新陳代謝を活発にすることにあります。血の巡りがよくなることで、体中に栄養素が効率よく運ばれると同時に、肉体疲労の原因となる老廃物の排出もスムーズになります。また食欲増進効果も期待できるので、食欲がないときに、食前酒として「薬用養命酒」を飲むのもおすすめです。
- 第2類医薬品 薬用養命酒
- 〔効能・効果〕肉体疲労・冷え症の滋養強壮に
- 〔用法・用量〕1日3回、食前・または就寝前に20mLずつ
養命酒については以下で詳しく紹介しています。ぜひチェックしてみてください。
体力をつけるには生活習慣が大切

体力は、体を動かし、活動するための「行動体力(=体を動かす力)」と病気やストレスから体を守り、健康に生活するための「防衛体力(=病気から体を守る力)」の2つの側面に分けられます。体力をつけるには、食事と同様に、日々の生活習慣も大切です。
質の高い睡眠で体力を保つ
睡眠は、単なる休息ではありません。心身を積極的に回復させるための重要な時間です。睡眠中、特に深いノンレム睡眠の間に「成長ホルモン」が分泌され、日中の活動で傷ついた筋肉や体の組織が修復されます。
また、脳も休息し、疲労物質が取り除かれます。一方、浅い眠りのレム睡眠中は筋肉の緊張が緩み、肉体的な疲労回復が進むと考えられています。
このように、質の高い睡眠を確保することは、体力の回復だけでなく、ストレスの軽減や気分の安定にもつながります。さらに、睡眠は免疫機能とも密接に関わっています。しっかり眠ることは「防衛体力」を高めることにもなるのです。
運動を継続して行う
体力を維持・向上させるためには、やはり体を動かすことが欠かせません。しかし、大切なのは運動の強度よりも継続すること。短時間でもよいので、運動を習慣化することが、体力づくりにはもっとも効果的です。
嬉しいことに、筋肉は何歳になってもトレーニングによって鍛えられ、増やすことができます。無理なく楽しく続けられることを見つけるのが、モチベーションを保つ秘訣です。ウォーキングなどの軽い運動から始め、体力がついてきたら少しずつ負荷を上げていくとよいでしょう。
ゆっくりと湯船に浸かる
1日の終わりに湯船にゆっくり浸かることは、手軽で効果的な体力回復法です。体が温まり、水圧がかかることで血行が促進され、筋肉にたまった疲労物質の排出が促されます。
さらに、就寝の1〜2時間前に入浴すると一時的に体の深部体温が上がります。入浴後にその深部体温が徐々に下がっていく過程で、自然な眠気が誘発され、寝つきがよくなって深い眠りを得やすくなります。
ただし、熱すぎるお湯や長時間の入浴は、かえって体力を消耗してしまうこともあるため注意しましょう。
家でもできる! 体力をつけるための運動方法

体力をつけるには、筋肉を維持するための「筋トレ」と、心肺機能を高める「有酸素運動」を組み合わせるのが理想的です。
スクワットやヨガなどは家でも手軽にできる運動方法でしょう。
体力をつけるためのトレーニング方法については以下の記事で詳しく紹介しているので、ぜひ参考にしてください。
体力が落ちる原因とリスク

体力が低下すると、疲れやすくなるだけでなく、病気にかかりやすくなるなど、心身にさまざまな影響が及びます。ここでは、体力が落ちてしまう主な原因と、それに伴うリスクについて解説します。
体力が落ちる原因
体力が低下する背景には、主に「栄養不足」「運動不足」「加齢」という3つの要因がかかわっています。
栄養不足
食事の量が減ったり、特定の食品ばかり食べるなど栄養が偏ったりすると、体はエネルギー不足に陥ります。特に、筋肉や血液、免疫細胞の材料となるタンパク質が不足すると、筋力が直接的に低下し、体力の衰えにつながります。
運動不足
健康と密接に関連している全身持久力が低下します。筋肉は使わなければ衰えてしまいます。また、運動不足が続くと筋肉量が減少し、基礎代謝も低下します。全身持久力が衰えると疲れやすさにつながり、血行が悪くなることで、体中に酸素や栄養素が届きにくくなって、疲労物質もたまりやすくなるため、体力が低下します。
加齢
年齢を重ねることも体力低下の一因です。加齢に伴い、筋肉量は自然と減少し、柔軟性や神経の伝達機能も衰えていきます。また、内臓や骨、関節といった体の各器官の機能が少しずつ低下することも、総合的な体力低下につながります。
体力が落ちることのリスクとは

体力が落ちると、以前は楽にできていた家事や通勤といった日常的な動作でも疲れを感じやすくなります。疲労感が原因で動くのが億劫になり、さらに活動量が減ってしまうという悪循環に陥りがちです。
高齢者の場合は特に注意が必要です。運動不足は骨密度の低下を招き、骨がもろくなる原因となります。筋力やバランス能力が低下していると、つまずいたときにとっさに体勢を立て直せず、転倒して骨折などの大怪我につながる危険性が高まります。
また、「防衛体力」が低下すると、体を守る「免疫機能」が弱まり、風邪やインフルエンザなどの感染症にかかりやすくなります。体力の低下は、単に「疲れやすくなる」だけではなく、日常生活の質(QOL)を大きく損ない、さまざまなリスクを抱えることにつながります。
この方にお話を伺いました
養命酒製造 健康情報局

薬用養命酒愛飲家向け健康情報誌『養命酒だより』や会員向けメールマガジン『元気通信』を発行。
医師や専門家の監修のもと、健康に関する情報発信を行っている。


















