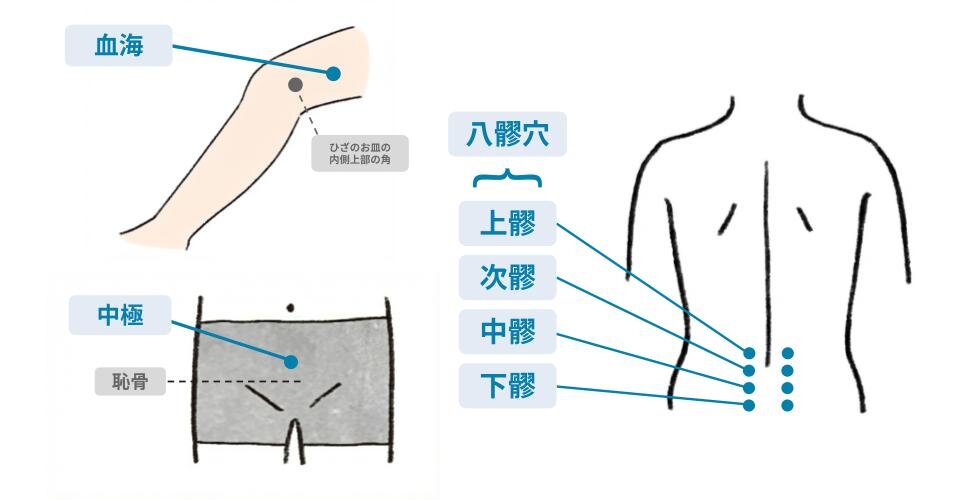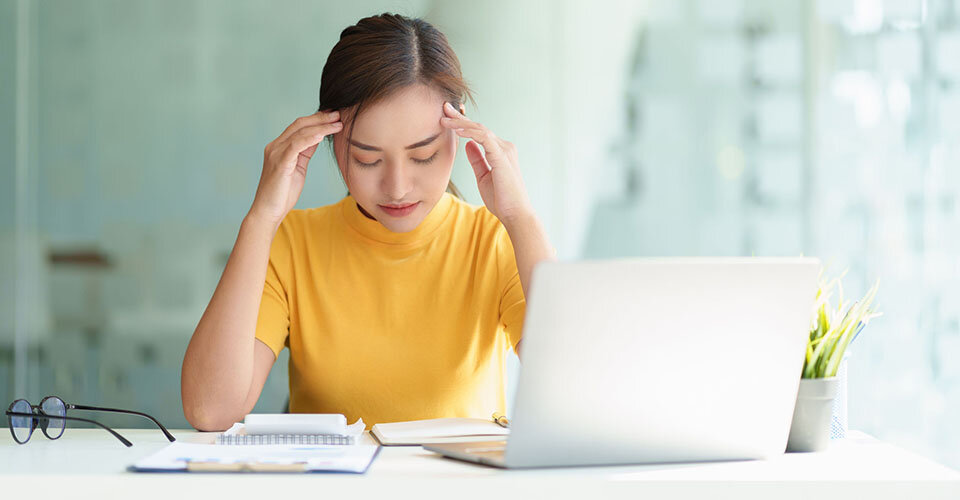風邪の原因はさまざまですが、風邪をひきやすい人には共通の特徴があります。免疫力低下につながる生活習慣や免疫が落ちやすい時期を知り、予防・対策に役立てましょう。
いわゆる風邪とは「急性上気道炎」のこと

いわゆる風邪(かぜ症候群)とは、微生物に感染して鼻から咽喉にかけての上気道に炎症が起こる「急性上気道炎」のこと。くしゃみ、鼻水・鼻づまり、喉の痛みや咳といった症状が現れます。
原因としては、ライノウイルス、コロナウイルス、RSウイルスをはじめとするウイルスが80~90%を占めるといわれています。ウイルス以外では、一般細菌やマイコプラズマなどの特殊な細菌も原因となります。
風邪をひきやすい人の特徴

1:免疫力が低下している
免疫機能が低下していると、体に侵入してくるウイルスや細菌を排除できなくなり、風邪をひいてしまいます。免疫力を低下させる生活の中の注意点には次のようなものがあります。
食生活が乱れている
腸は、免疫細胞が多くすんでいる重要な免疫器官です。栄養バランスの悪い食事や、食事のリズムが乱れた食生活で腸の働きや腸内細菌叢(ちょうないさいきんそう)が乱れると、免疫力も低下することに。また、栄養のバランスが偏っていると、体が必要とする栄養素が十分にとれず、免疫力低下につながります。
睡眠不足
粘膜に含まれ、ウイルスや細菌の侵入を防ぐ働きをもつ免疫物質にIgA(アイジーエー)があります。睡眠が不足すると、このIgAの分泌量が低下することが分かっています。
運動不足
運動が不足して筋力が低下すると、血液やリンパ液の巡りが悪くなります。体温や基礎代謝も低下し、免疫力が下がる原因に。ただし、適度な運動は免疫力を高めますが、過度な運動は逆に免疫力を下げてしまうので注意しましょう。
アルコールを過剰摂取している
度数の強いお酒や大量の飲酒は、喉の粘膜を刺激してその免疫機能を低下させてしまいます。さらに、アルコールそのものや、アルコールが肝臓で分解される際に生成されるアセトアルデヒドも、免疫細胞の働きに悪影響を及ぼします。
喫煙している
煙と共に体内に入る一酸化炭素の影響で、体内の酸素量が不十分になり、免疫力が低下します。また、ニコチンによる血流の悪化、喫煙による唾液の減少やビタミンCの消費なども免疫力低下の原因に。
冷え性(症)
冷えはさまざまな病気が起こる前の「未病」に該当するもの。体が冷えていると血行が悪くなり、血液中の免疫細胞が十分に機能しなくなって免疫力が低下します。
以下記事では、冷え性(症)の原因と対策について解説しています。ぜひ確認してください。
過度なストレスを感じている
忙しさや環境の変化などで心身に強いストレスがかかると、自律神経が乱れて免疫物質のIgAの分泌量が低下したり、腸内細菌のバランスが変化して腸の免疫器官としての働きが低下したりすることがわかっています。
2:ウイルスと接触しやすい環境にいる
風邪の主な感染経路は、飛沫感染と接触感染です。感染している人の近くにいると、その人の咳やくしゃみ、会話などで口からの飛沫がかかり、感染するリスクが高まります。また、感染している人に直接触れたり、生活の中で共有するもの(ドアノブやテレビのリモコンなど)に触れたりすることでも感染します。
職場や学校、公共交通機関、商業施設、飲食店など、人が集まる所はリスクが高い環境といえるでしょう。小さなお子さんがいる家庭では、お子さんが保育園や幼稚園で感染し、家族にうつってしまう「家庭内感染」も多く見られます。
3:頻繁に風邪を繰り返す場合はほかの病気が潜んでいる可能性も
繰り返し風邪をひいてしまう場合は、甲状腺の病気などが隠れている可能性も。 また、症状がなかなか改善しない、どんどん重くなっていく場合は早急に医療機関を受診しましょう。
特に女性は要チェック! 風邪をひきやすい時期とは

季節の変わり目や秋・冬
季節の変わり目は、気温や気圧の急激な変化が起こりやすく、その対応のために漢方医学で生命エネルギーを指す「気」が消耗し、自律神経が乱れて、免疫力も低下しがちに。特に春は、環境の変化も加わるので注意が必要です。
また、秋や冬は、寒さや空気乾燥によって鼻や喉の免疫機能が低下し、かぜをひきやすくなります。
生理中・生理前・更年期
女性の場合、女性ホルモンの分泌量やバランスの乱れやそれに伴う体調の変化が免疫力の低下につながり、風邪をひきやすくなります。
妊娠中~産後3カ月
おなかの中の赤ちゃんを異物として攻撃しないようにするため、妊娠中は免疫力が低下します。さらに、妊娠による体調の変化や疲労、ストレスも免疫力に影響します。
産後は睡眠不足や疲労、体力低下などによって風邪をひきやすくなります。
風邪を予防する対策6選
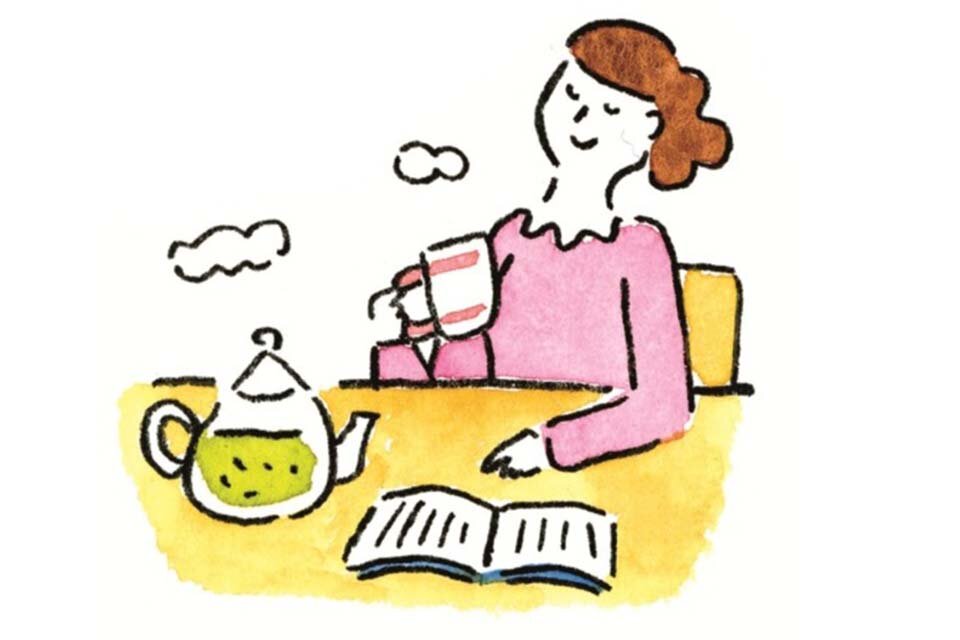
風邪予防によい食べ物を意識してバランスのよい食事をする
栄養が偏らず、しっかりととれる食事を心がけましょう。緑黄色野菜なども取り入れたカラフルな料理にすると、栄養のバランスがとりやすくなります。風邪の予防には、特に次の栄養素を意識してとることをおすすめします。
- 〔風邪予防にとりたい栄養素〕
- ビタミンA ...... 鼻や喉の粘膜を守りウイルスや細菌の侵入防止を助ける
- ビタミンB1 ...... 糖質からエネルギーをつくるのをサポートする
- ビタミンB2 ...... 細胞の新陳代謝を助け、皮膚や粘膜を守る
- ビタミンB6 ...... タンパク質の合成を助け、鼻や喉の粘膜を強くする
- ビタミンC ...... コラーゲンの合成を助け、体の免疫機能を活性化する
- ビタミンE ...... 抗酸化作用で免疫力の低下を防ぎ、血流を改善する
- タンパク質 ...... 筋肉や臓器など体をつくる主成分で、免疫細胞の材料
- 糖質 ...... 体のエネルギー源になる
- 亜鉛 ...... 新陳代謝をサポートし免疫力も高める
また、漢方医学では、体を潤すもの、体を温めるものをとると風邪の予防によいと考えます。
- 〔漢方医学が考える風邪の予防によい食材〕
- 乾燥対策に体を潤すもの ...... れんこん、ゆり根、白きくらげ、豆腐、梨など
- 冷え対策に体を温めるもの ...... 羊肉、にら、にんにく、長ねぎ、生姜、唐辛子、こしょうなど
免疫力と関係の深い腸内環境を整えるために、納豆やぬか漬けなどの発酵食品をとるのもいいでしょう。
質の良い睡眠をとる
睡眠の質と時間は、免疫と深く関係しています。十分な睡眠時間を確保するのに加え、就寝直前に食事をとらない、就寝の1~2時間前に入浴する、寝室にスマホを持ち込まないなどを心がけ、睡眠の質を高めましょう。
適度な運動をする
適度な運動は全身の血流と新陳代謝を高め、心身の疲労を回復させます。体を動かすと体温が上昇するので、免疫細胞の活性化も期待できます。ただし、過度な運動はストレスとなり、逆に免疫力を低下させてしまうので注意しましょう。
ストレス解消を心がける
ストレスの原因を明らかにし、その問題を解消する、あるいは原因との距離を見直すといった対処をとったり、自分に合ったリラックス法や発散法を取り入れたりして、ストレスとうまく向き合っていくようにしましょう。
夜は、自分にとって心地よい環境を整えることがリラックスへの近道に。また、ため息をつくように長くゆっくりと息を吐き出すと、副交感神経が活性化されストレスが和らぎます。
感染予防を心がける
風邪をひいている人にはあまり近づいたり接したりしないようにしましょう。感染症が流行しているときや、大事な予定が控えているときなどは、人が集まる場所などに出かけるときはできるだけマスクをつけ、うがいや手洗いを徹底するとよいでしょう。
子どもが風邪にかかった場合は、看病などで接触する人を限定し、家庭内感染の広がりを防ぎましょう。
快適な温度や湿度を保つ
体が冷えると、血流が滞り、免疫力が低下します。また、湿度が下がって鼻や喉の粘膜が乾燥すると、ウイルスなどに感染するリスクが高まります。寒さや乾燥は秋・冬だけでなく、夏の冷房でも注意が必要です。
快適な室温と湿度の目安は、季節や活動時、睡眠時などによって異なりますが、一般的には室温18~28℃、湿度40~60%が理想とされています。しかし、快適に感じる温度には男女差や個人差も大きいため、過度な冷暖房には気をつけて調整しましょう。
風邪をひいたときの対処法3選

1:水分をこまめにとる
水分をとることには、発熱や発汗などで奪われた水分を補うのに加え、粘膜を潤すという役割もあります。特に鼻づまりなどがあると口が乾きやすいので、こまめに水分をとるとよいでしょう。
2:体を温める
漢方医学では、寒気をともなう風邪の原因となる「風邪(ふうじゃ)」「寒邪(かんじゃ)」という邪気を追い出すには体を温めるとよいと考えます。体温が上がればそれだけ免疫力も高まり、風邪も長引かせずに済みます。
寒気は発熱前のサインのことが多く、部屋を暖かくして布団や着衣で体を温め、しっかりと汗をかくと熱が下がりやすくなります。生姜やシナモンなど体を温める働きのあるものを加えた飲み物・食べ物で、体を中から温めるのも有効です。
風邪のときでも、倦怠感がなく高熱でなければ、ぬるめのお風呂に入浴して体を温めて問題ありませんが、湯冷めには注意してください。
3:漢方薬を飲む
薬はできるだけ飲みたくないという人もいるでしょう。しかし、体に合った薬を飲めば、治りが早く、体力の消耗を防ぐこともできます。
漢方薬は「喉が痛い」、「寒気がする」といった症状や、風邪の初期かどうかの時期、発熱や発汗の有無、「胃腸が弱い」「もともと体温が低く高熱が出にくい」など、体質を見極めながら処方されます。体調の変化を少しでも感じたタイミングで、できるだけ早く適切な漢方薬を飲むと効果的です。
この方にお話を伺いました
医療法人祐基会帯山中央病院理事長、医学博士、日本東洋医学会漢方専門医 渡邉 賀子 (わたなべ かこ)

北里研究所に日本初の「冷え症外来」を開設、慶應義塾大学病院漢方クリニックに「漢方女性抗加齢外来」を開設、「麻布ミューズクリニック」院長などを経て現職。『オトナ女子のためのホッと冷え取り手帳』(主婦の友社)、『医師がすすめる漢方生活 365日の養生』(Gakken)など著書多数。