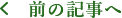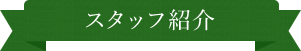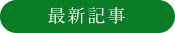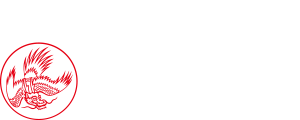皆さんは、「秋の七草」というのをご存じですか?
私、不勉強でして、存じないのですが、
万葉集に、山上憶良の「秋の野の花を読める二首」
というのが、載っているそうです。
秋の野に咲きたる
花を指折り(およびおり)
かき数ふれば
七種(ななくさ)の花
萩の花尾花葛花
なでしこの花
女郎花また藤袴
朝貌(あさがお)の花
ハギ(萩 マメ科)、ススキ(尾花 イネ科)、
クズ(葛 マメ科)、カワラナデシコ(撫子 ナデシコ科)、
オミナエシ(女郎花 オミナエシ科)、フジバカマ(藤袴 キク科)、
キキョウ(朝貌 キキョウ科)などが、秋の七草として、
奈良時代の世から親しまれていたそうです。
「朝貌(あさがお)の花」はキキョウというのが定説です。
ヒルガオ科のアサガオは、熱帯アジア原産で、日本へは
平安時代に渡来したからだそうです。
私の印象としては、秋の七草といっても、梅雨明け頃から
咲き始めるものも多く、夏の花、あるいは盆花という感じです。
今回は、「秋の七草」 その1 として、
「キキョウ(キキョウ科)」を紹介します。
最近では、花屋や野草園、家の庭先でも良く見かけるキキョウ
ですが、野生では絶滅危惧種(VU:絶滅危惧Ⅱ類)です。
生育地である、山地草原が少なくなっているからです。
というわけで、健康の森でも、キキョウが咲き始めました。
こちらは、山野草コースです。
こちらは、カフェテラスの西側の林内です。
アカマツ林の伐採で明るくなった所を、山地草原のイメージ
でキキョウを植えてみました。
花を良く観察してみますと、
こちらは、咲いたばかりの花。
雌しべを5本の雄しべが包んでいます。
しばらくすると、雄しべが先に熟して、
花粉を飛ばし、倒れます。
雄しべが花粉を出し終わると、真中の花柱(雌しべ)が
5裂して、他の花から花粉を受けます。
これは、自家受粉を防ぐためのシステムで、他の花から
花粉を受け取ることで、遺伝的多様性が高まります。
以下の写真は、私の自宅の庭のキキョウです。
たくさん種を播きましたら、
花色に様々なバリエーションが現れました。
これも遺伝的多様性ですね。
今後も、秋の七草を、順次紹介していきます。