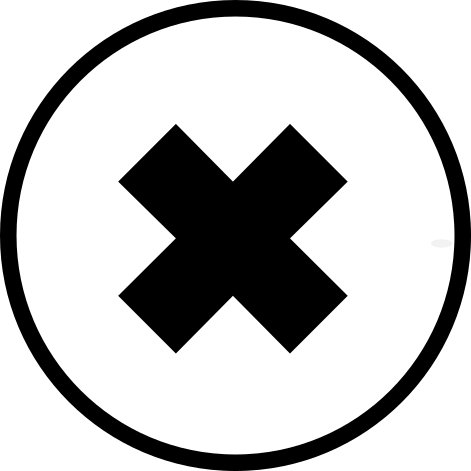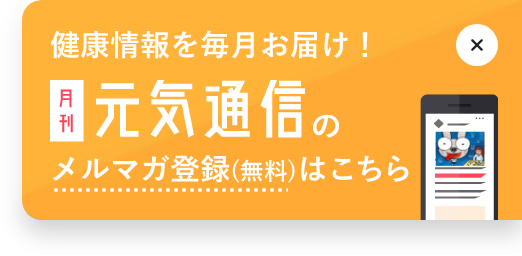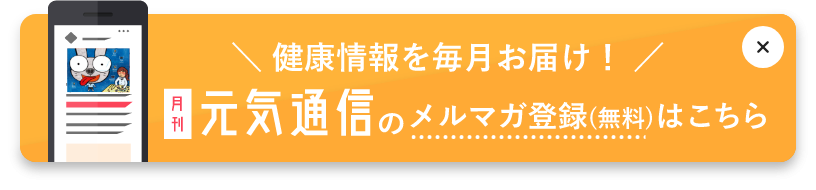成熟すると果肉内に強い繊維が網状に発達する
太陽をさえぎり天然のクーラーとして涼を与えてくれたヘチマ棚も、秋が近づくと長く大きな実を結びます。ヘチマといえば、年配の方は化粧水やヘチマたわしを連想する人が多いのではないでしょうか。「ヘチマ野郎」という言葉や「世の中は、何のヘチマと思えども、ぶらりとしては暮らされもせず。」など生活の例えに使われてきたように、日本人の生活と深く結びついてきた植物です。
ヘチマはインドや熱帯アジア原産で、各地で栽培されるウリ科の一年生蔓植物です。茎は緑色で角があり、巻ひげがあってほかのものに絡みながら長く伸びます。夏から秋にかけて黄色の花を雌雄同株に付け、果実は緑色の長大な円筒型で長さ30〜60cm程度ですが、ナガヘチマだと1〜2mになるものもあります。
成熟すると強い繊維からなる網状組織が果肉中に発達するので、乾かして色々と利用します。また、秋に茎を地上50cmほどで切断し、溢れ出る液を集めて化粧水にします。
日本へは慶長年間(1596〜1615年)に長崎に渡来したとされ、林羅山の『多識編』(1630年)に「倍知麻(ヘチマ)」の名前が見られます。江戸時代には化粧水としての利用が多く、小石川御薬園の献上帳に、「ヘチマ水(糸瓜水)」を大奥用に一石一斗三升(約200ℓ)届けたと記録があります。詩歌に詠まれるのは江戸時代になりはじまりました。

植物名は江戸時代の『物類称呼』(1775年)によると、ヘチマを指す糸瓜が略されて「トウリ(と瓜)」となり、「と」はいろは歌では「へ」と「ち」の間にあるため、「へちま(へち間)」となったとあります。
薬用は痰、咳、利尿によいとされてきました。そのほか、化粧水やヘチマたわし、垢すり、石鹸の代用など生活の中で幅広く使われています。
食用としては、蕾や若葉を天ぷらに、若い果実の皮をむいて揚げ物や汁の実、田楽、油炒めなどに用います。また、皮をむいて干した「干し瓜」は保存食になります。種子は油を多く含み食用油や石鹸の原料、灯油などとして利用されてきました。
花言葉は、「悠々自適」です。
出典:牧 幸男『植物楽趣』