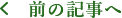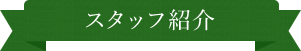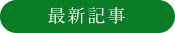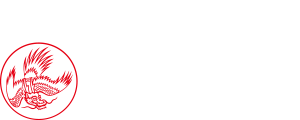夏休みに北八ヶ岳の縞枯山~茶臼山を歩いてきました。
ここは標高2000m以上の亜高山帯針葉樹林で、モミの仲間の
シラビソーオオシラビソが優占する天然林です。
山の名前にあるように、樹林が縞状に立ち枯れて白い横縞模様が
現われる「縞枯現象」が見られます。
これは、酸性雨でもなければ、森林破壊でもなく、
気象条件等による自然現象であり、
立ち枯れ木の下には無数の稚樹が生えていることからも、
森林の天然更新(自然の力で世代交代すること)の一つの姿
だとされています。
天然林の老齢林には、衰退した老大木や立枯れ木、倒木などが
あることで、様々な動物に採餌、営巣、休息の場を提供したり、
また倒木上の苔の上には、稚樹が生育する良い条件が整う
ことからも、生物多様性が高い環境であるといわれています。
構内の森林整備では、「美しい里山の森」をつくるとい目標のもと、
アカマツ林を伐採して、四季の変化が美しい広葉樹林への転換を
進めています。そこでは、伐採した丸太はすべて林外へ搬出し、
また枝葉も粉砕したり、林外へ運び出したりして、
仕上がりの綺麗さを意識して来ました。
これから先、さらに森林整備が進む中では、お客様の安全と景観に
配慮しながら、可能な場面では、立枯れ木や倒木(伐採木)を林内
残すことで、多様な森林空間を創出することで生物多様性がより
高まるような森林環境が作り出せたら良いと思っています。