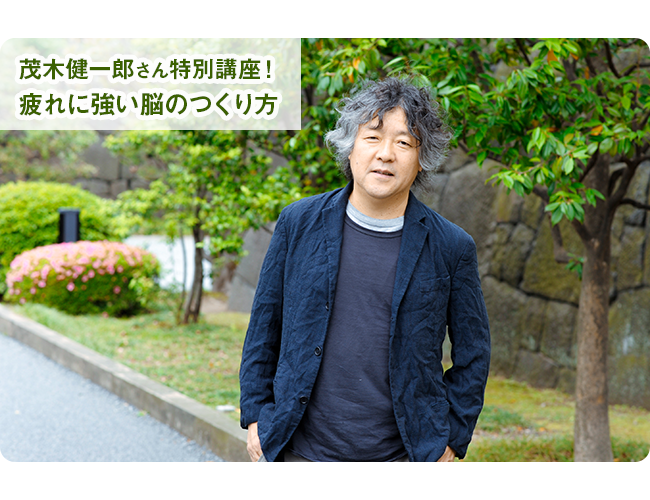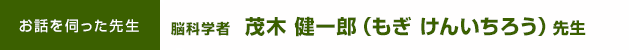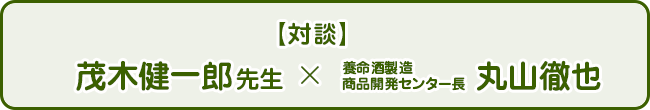ストレス社会に生きる現代人は、脳がとても疲れています。そこで、人気脳科学者の茂木健一郎さんを講師に迎え、「疲れに強い脳のつくり方」と題した養命酒製造×朝日カルチャーセンター特別講座を開催しました。今月の元気通信は、脳の健康を維持するために役立つ茂木さんの講座を大公開!

2016年8月10日に千葉三井ガーデンホテルにて、養命酒製造×朝日カルチャーセンター特別講座が開催されました。
1962年東京生まれ。東京大学理学部・法学部卒業後、同校大学院理学系研究科物理学専攻課程修了。理学博士。理化学研究所、ケンブリッジ大学を経て現職。専門は脳科学、認知科学。「クオリア」(感覚の持つ質感)をキーワードに脳と心の関係を研究するとともに、文藝評論、美術評論などにも取り組んでいる。NHK『プロフェッショナル 仕事の流儀』でキャスターを務めるなど、幅広い分野で活躍。
脳がいつまでも若いと、人生を謳歌できる!

「私の両親は80歳を過ぎていますが、とても元気にしています。医師の日野原重明さんは、今年で105歳になるそうですが、手帳に10年先の予定まで書いていらっしゃるようです。すごいですよね!ただ、私たちはどんなに長生きしても、脳の健康を維持できないと、生活の質を保てません。例えば認知症になると、せっかく楽しい体験をしても、記憶に残りませんし、性格も変わってしまいます。
じゃあ、いつまでも脳を若々しく保つにはどうすればよいのでしょう?
それは、脳にいい生活習慣を続けていくことです。そうすれば、70歳でも80歳でも脳の若さを持続できるんです」
何歳になっても脳の若さを保つ秘訣はドーパミン!
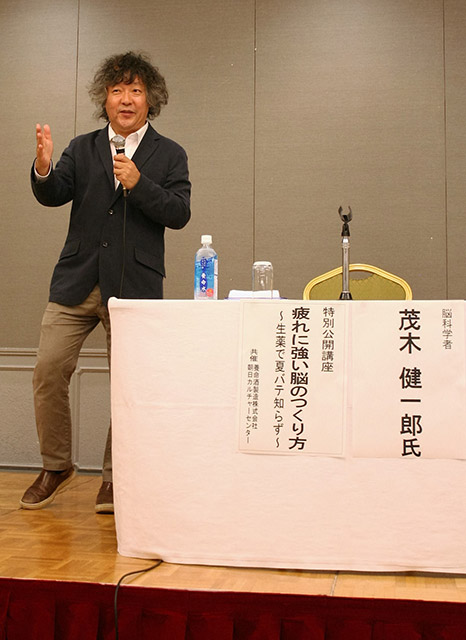
身振り手振りを交えてユーモラスに話す茂木さん。
「脳の若さを保つためには、脳の前頭葉を活性化してドーパミンをたくさん出すことです。…というと、『ドーパミンを増やせる食べものを教えてください』なんて聞かれたりするんですが、ドーパミンは、楽に出てくるものではありません。必死の努力に対する脳からのごほうびとして出されます。
例えばアスリートは、血のにじむような試練を重ねた結果、脳から『がんばろうね!』とドーパミンが出ます。また、比叡山延暦寺の千日回峰行を2度も行った僧侶の酒井雄哉さんは、その中で9日間飲まず食わずでお堂にこもって修行しています。そのように極限までがんばる人の脳からは、ドーパミンが出るのです」
初めての体験をするとドーパミンがアップ!
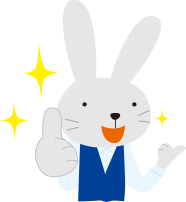
「生まれて初めて花火を見た時、成人して初めてビールの味を知った時、ドキドキわくわくしたり、感動したりしませんでしたか?ドーパミンはそんな風に好奇心を刺激されると出ます。子どもの脳が元気なのは、好奇心をくすぐる初めての体験が多く、ドーパミンが出る機会が多いからです。
しかし、大人になると知識や経験値が高くなる分、あまりものごとに動じなくなります。ドーパミンを出すには、好奇心を持って行ったことのない所に足を伸ばし、初めて出会う景色や人に触れるといったことを積極的に行うのがおすすめです」
できなかったことができた時、ドーパミンがマックスに!

「今までできなかったことができるようになった時もドーパミンが出ます。子どもの頃、五十音表や九九を初めて見た時、『こんなの覚えられるわけがない!』と思いませんでしたか?子どもはできないことも、次々に乗り越えて成長していきますが、チャレンジに年齢制限はありません。埼玉にある『原爆の図丸木美術館』の創設者の母である丸木スマさんは、70歳を超えてから初めて絵筆をとり、日本美術院展でも入選しています。
私も52歳の時に初めて東京マラソンに挑戦しましたが、完走できた瞬間はドーパミンが出ていましたねぇ。NHKの朝の連続ドラマ『花子とアン』に出演して初めて役者体験をした時も、『茂木さん、棒読みでしたねえ』っていわれましたが(笑)、自分ではすごくドーパミンが出ていたと思います」
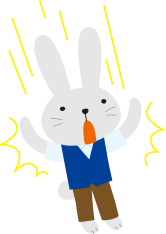
新しいことを続けて、脳のアンチエイジングを!

「“むちゃぶり”という言葉がありますが、何か新しいことをやると決めて動き出しちゃうと、脳のアンチエイジングになります。例えば、今まで水墨画に憧れながら一度も書いたことがなかったなら、今年の秋に水墨画展を開催すると決めて、近所の公民館などに予約を入れてしまいましょう。もっと小さなことでもかまいません。今までと違う道を通ってみるとか、今までと違う駅で降りてみるとか、今までと違う新しいことを続けることで、脳が若返りますよ」
継続は力なり!

「最近の脳の研究では、成功する人の共通点は才能ではなく、継続できることだといわれています。イチロー選手は『そんな打ち方じゃダメだ』といわれながらも、ずっと努力し続けてきたことで3000本安打を達成できたのではないでしょうか。マラソン選手の有森裕子さんも、『体が硬いから向いていない』といわれて学生時代は鳴かず飛ばずでした。しかし、ずっと努力し続けた結果、2大会連続でオリンピックメダリストになりました。
大切なのは、習慣化することです。3日坊主になっても、また再開すればいいんです。3日も続いたことは、継続できると考えましょう」
ストレスは脳の敵!自分の個性を受け入れることが幸せな脳を育む
「脳にとってストレスは1番の大敵です。アメリカのビッグデータによると、結婚の有無やお金の有無が人の幸福感を左右しないという結果が出ていますが、人はとかく誰かと比べてないものねだりをしがちです。しかし、他人と比べることは不幸の元であり、脳にとっても大きなストレスになります。自分のありのままの個性を『偶有性(ぐうゆうせい)』といいますが、これを受け入れることが幸せにつながり、脳の健康によいといえます。
私は落ち着きがないという短所がありますが、短所は長所と表裏一体なので、切り替えが早いという長所にもつながっています。脳の前頭葉にはミラーニューロンという神経細胞があり、自分の個性を映す鏡は他人の中にあります。他人の反応を通して自分の個性を知ることも、脳の健康のために大切なことです」
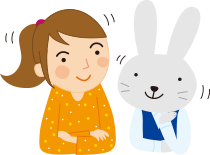
第二部は、茂木先生と養命酒製造の丸山徹也商品開発センター長との対談です。
「ぼくが子どもの頃、お祖父ちゃんはいつも相撲中継を観ながら、養命酒を飲むのが日課でした」という茂木さんは、薬用養命酒に含まれる生薬や効能について、丸山センター長に興味津々で質問。

「養命酒は1日3回、食前や夜寝る前に飲んでください」いう丸山センター長に、「ぼくのお祖父ちゃんは晩酌みたいにチビチビ飲んでいたなあ。」と笑う茂木さん。

会場では希望者に薬用養命酒を試飲。「生薬というと漢方薬のようなイメージを想像しますが、養命酒はまろやかで飲みやすいですね!」と驚く茂木さん。
参加者にもマイクを向ける茂木さん。参加者には病後に飲み始めたという方や、長年薬用養命酒を飲み続けているという方も。




会場には「薬用養命酒」に含まれる14種類の生薬や、さまざまな生薬やハーブを使った人気商品を集めたコーナーも。生姜の風味が上品な「琥珀生姜酒」は、甘さ控えめでスッキリした味わい。ソーダ割りやお湯割り、ジンジャーチャイなど、さまざまな飲み方が楽しめます。
脳の健康に役立つポイントをユーモアたっぷりに話してくださった茂木健一郎先生。ぜひ脳の前頭葉を鍛えてドーパミンが出るような生活習慣を続けましょう!