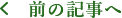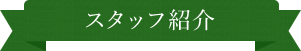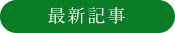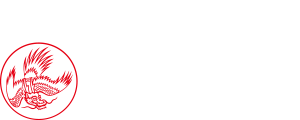蛇が鎌首をもたげた姿にも見えるこの植物は、
茎の模様が蛇のマムシに似ていることから、
一般的に「マムシグサ(蝮草)」と呼ばれています。
植物には雄花(おばな)だけが咲くオスの株と、
雌花(めばな)だけが咲くメスの株が別々に分かれてのものがあります。
これは雌雄異株(しゆういしゅ)という性質ですが、
多年草である「マムシグサ」は一つの株が年によって,
雄(おす)なったり、雌(めす)になったりすることから、
性転換する植物と言われています。
オスの株には雄花が咲いて、花粉を出します。
雄花を訪れた昆虫は、花粉を身に付けて総苞(そうほう)の下にある
出口から出て行きます。総苞はマムシの頭の部分のことです。
メスの株には雌花が咲いて、訪れた昆虫から花粉を受け取ります。
雌花の総苞の出口は小さくて、昆虫はなかなか外に出ることができず、
その間に昆虫に付いていた花粉がめしべ付き、受粉が行われます。
オスの株はメスの株に比べて、小さくて弱々しいですが、
総苞の中を覗き込んで花を確認するか、総苞の出口の様子を
確認することで、外からでもある程度わかりますよ。
サトイモ科の「マムシグサ」は汁に触れるとかぶれることが
ありますので、肌の弱い方は注意して観察してくださいね。