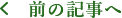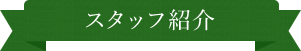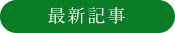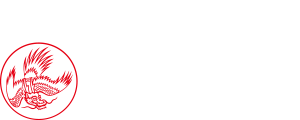最近の花情報をお知らせします。
この時期、花は次々咲いては終わって行きます。
なかなかタイムリーにという訳にいきませんので、
今回は、最近、撮影したものをまとめてご紹介します。
撮影日を追加しましたので参考にしてください。
「コバノガマズミ(スイカズラ科)」です。
<散策路沿いの林内>(撮影日:5月16日)
林内の至るところで、白い花を咲かせています。

「ツルカコソウ(シソ科)」です。
<散策路沿い>(撮影日:5月16日)
花が終わる頃から、地面を這う走出枝(ランナー)を出すので、
ツルという名がついてます。
今の所、構内では毎年同じ場所に一株しか確認していませんので、
もし見つけられましたら、ラッキーですね。

「マイヅルソウ(ユリ科)」です。
<散策路沿い>(撮影日:5月18日)
「舞鶴草」は、葉を2個広げた姿を鶴の舞う姿に
たとえています。葉がハート型なので、葉っぱ
だけ群生している様も愛嬌があります。

「レンゲツツジ(ツツジ科)」です。
<散策路沿いの林内>(撮影日:5月21日)
シラカバと並んで、信州の高原の景観を象徴する花木です。
今、信州の山林では、ニホンジカによる樹木や高山植物の
食害が深刻ですが、ニホンジカはこのレンゲツツジを好んで
食べないので、レンゲツツジだけが残っているというところもあります。
塩尻市~岡谷市の高ボッチ高原や鉢伏山が名所として有名です。

「ヤマツツジ(ツツジ科)」です。
<散策路沿いの林内>(撮影日:5月21日)
山桜が終わった後、新緑の林内を彩ります。

「エビネ(ラン科)」です。
<山野草コース>(撮影日:5月22日)
「ヒメシャガ(アヤメ科)」です。
<山野草コース>(撮影日:5月22日)
「ナツトウダイ(ドウダイグサ)」です。
<川沿いの散策路沿い>(撮影日:5月25日)
花にしてはかなり地味ですが、葉の付き方が面白く、
色合いにバリエーションがあって、結構目立っています。
名前に「夏」がついているのに、春先から咲き始めます。
写真では、もう実が付き始めています。
「オオヤマオダマキ(キンポウゲ科)」です。
<山野草コース>(撮影日:5月25日)
ヤマオダマキとの違いは、花の背の部分(上側)に突き出した
距(きょ)といわれる部分が、内側に強く巻き込んでいるのが
特徴です。
「フタリシズカ(センリョウ科)」です。
<山野草コース>(撮影日:5月25日)
名の由来は、ヒトリシズカが、花を平家物語の静御前の美しい舞姿にたとえたもの。
そして、フタリシズカが、花を静御前の亡霊2人の艶美にたとえたもの、だそうです。
ここで、私が農学部の学生時代、野外の樹木分類実習での先生と学生の会話
学生「先生、この花は何ですか?」
先生「フタリシズカじゃ!、ほれ、ヒトリシズカというのがあるじゃろ、
これは、花穂が2本だからな。」
先生「それじゃ、花穂が3本のやつは、何ていうかわかるか?」
学生「???、まさか三人静・・・・。」
先生「カシマシイ、じゃ。」
学生「カシマシイ??。」
先生「ほれ、娘(むすめ)三人揃えば、かしましい(やかましい)と言うじゃろ!」
学生「・・・」
※注意:野草には、「カシマシイ」も「三人静」もありません。
「ニガナ(キク科)」です。
<日当たりの良い構内のいたるところ>(撮影日:5月25日)
名前の末尾に「ナ(菜)」が付く草には、食べられるものが多いです。
例えば、ノザワナ、アブラナ、ソバナなど。
「ニガナ(苦菜)」は、葉や茎を切ると、苦い乳液が出るからです。
「ミツバウツギ(ミツバウツギ科)」です。
<管理棟から記念館へ向かう道沿い>(撮影日:5月25日)
昨年、構内から移植しました。
白い花が咲く低木には、何とかウツギという名前が多いですが、
以外と違う仲間のものが多いです。
「マムシグサ(サトイモ科)」です。
<散策路沿いの林内>(撮影日:5月28日)
ちょっと、キモチ悪いと評判です。
こちらも同じ「マムシグサ(サトイモ科)」ですが、
葉に斑が入った、めずらしいタイプです。
でも、なぜか、こちらに背を向けて立っています。
<南道路沿いの林内>(撮影日:5月25日)
「アマドコロ(ユリ科)」です。
<散策路沿い>(撮影日:5月28日)
見た目がよく似ている仲間に、「ナルコユリ」というのが
ありますが、見分け方は、茎を触ってみたとき
茎が丸いのが、「ナルコユリ」
茎に稜(りょう)があって、角張っているのが「アマドコロ」です。
そっと、触ってみてください。
「ヂシバリ(キク科)です。
<散策路沿いなど日当たりの良い場所>(撮影日:5月28日)
名は、細い茎が地面を這い、地面を縛るように見えることから。
雑草扱いされがちですが、一斉に咲くとなかなかきれいです。
地面の土を早く隠したい時など、うまく育てると有効です。
「ミヤマナルコユリ(ユリ科)」です。
<散策路沿いや南道路沿い>(撮影日:5月28日)
花が葉に隠れるように付いているのが特徴です。
長々とお付き合いありがとうございました。
特別に貴重であったり、珍しい花でなくても、
ちょっと視線を変えて眺めると、奥深く楽しい
花の世界をこれからも紹介していきたいと思います。