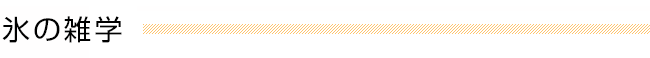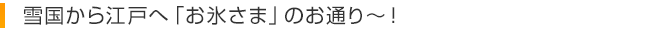いにしえの殿上人たちを魅了した氷のおもてなしって? 雪国から江戸へひた走った「お氷さま」とは? アイスリンクの氷はどうやって作るの?今月は氷の雑学をご紹介!
冷凍庫などまだなかったはるか昔の日本では、氷は身分の高い殿上人にしか許されない特別な存在でした。『日本書紀』には、仁徳天皇の兄弟の皇子が、奈良の山中で冬にできた氷を氷室で夏まで保存し、酒に氷を漬けて飲んでいるという人物に出会ったという記述があり、当時からオンザロックで酒をたしなむ粋人がいたことがうかがえます。ちなみにその氷を仁徳天皇に献上したところ、大変喜ばれたそうです。
平安時代になると、天皇やその侍従に氷を献上するのが習慣化したようです。清少納言は『枕草子』で、「削り氷に甘葛入れて新しき金鋺に入れたる」のは「あてなるもの」である——現代風に訳すと「削った氷に甘い葛の汁をトロッとかけて、金のお椀に盛ったひんやりスイーツって、上品よねえ」と語っています。
『源氏物語』の「常夏」の項でも、光源氏が宮中で夕涼みをしているシーンで、「大御酒参り、氷水(ひみず)召して 水飯など とりどりにさうどきつつ食ふ」——つまり「冷え冷えの氷を溶かした水や飯を振舞ったら、みんなこれはイケるって喜んでくれたよ」と語っています。今でこそ当たり前の氷ですが、当時は貴重なおもてなしの逸品だったのです。

北陸新幹線が開通して、金沢〜東京間はわずか2時間半弱で行ける時代になりましたが、江戸時代に金沢から江戸まで行くには、最短でも片道約480kmの「下街道」を、ひたすら徒歩で行くしかありませんでした。
当時は、旧暦の6月1日(今の7月上旬)になると、雪国北陸の大名前田家は城内にある氷室の氷を江戸幕府に献上するのがならわしでした。といっても、クーラーボックスなどない時代ですから、笹の葉とむしろで何重にもくるんで桐箱に詰めた氷(雪塊)を、大名お抱えの飛脚が4人がかりで担ぎ、下街道を「エッホ、エッホ」と全速力で走って届けていたといいます。照り付ける夏の日差しの下、飛脚たちは汗みどろになりながら、氷が溶けないかヒヤヒヤしていたのではないでしょうか。
この飛脚による氷献上のことを江戸庶民は「お氷さま」のお通りと呼び、「こころざし水にせぬうちお裾分け」といった当時の川柳にも、「氷をちょっとでもいいから欲しい」という、庶民にとって高嶺の花である氷に対する憧れがにじみ出ています。
そんな貴重な「お氷さま」も、幕府に無事献上された頃には既に溶けて小さくなっていたうえ、雪塊には土ぼこりなども混じっていたので、将軍が実際に口にすることはなかったのだとか。氷献上は幕府に対しての忠誠を確かめる形式的なものだったようです。飛脚の苦労を思うと空しいけれど、それだけ「お氷さま」の価値が高かったということですね。
フィギュアスケートなどでおなじみのアイススケートリンク。大会会場となるのは、バレーボールなどの競技大会やコンサート会場などに使われる大型の体育館ですが、スケート大会の時だけフロアが巨大なアイススケートリンクに変身し、大会が終わるとまた元通りになるのは、とても不思議ですよね?
実はこれは専門の設営業者が、特殊な防水、冷却、散水技術を使い、何十人もの人海戦術によって、一週間ほどかけてリンクを設営しているのです。
例えば、フィギュアスケートの会場によく使われる代々木第一競技場第一体育館の場合、まず木造床に防水シートが敷かれ、さらに結露防止の断熱材、荷重が偏らないようにする床補強パネルなどがミルフィーユのように幾層にも重ねられ、リンク全体を冷やす冷却管がびっしり敷き詰められます。そこに散水して、1回に0.3〜0.5mmずつ厚みを増していき、昼夜約120時間かけて厚さ約8cmの氷ができ上がります。徐々に氷を厚くしていくことで、きめ細かで強度のあるアイスリンクが完成するのです。「そんなに氷が厚いと、アイスリンクを撤去する時は水浸しになるのでは?」と思いきや、冷却管を20℃弱に加温して氷を溶かし、溶けた水をポンプで排水溝に流すので、水浸しにはなりません。競技者たちがどんなにジャンプをしてもヒビひとつ入らない頑強なアイスリンクは、まさに縁の下の力持ちですね。