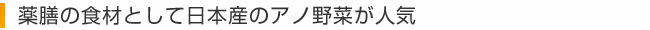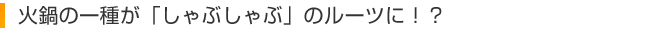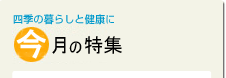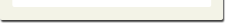HOME > 健康の雑学 > 【2011年2月号】薬膳の雑学
薬膳の素材として海外でも重宝される日本産野菜とは?しゃぶしゃぶのルーツは北京料理にあった?今月は、薬膳に関する雑学をお送りいたします。
|
|
 薬膳料理ブームは、日本に限ったものではありません。本場中国をはじめ台湾でも、薬膳はもてはやされています。
薬膳料理ブームは、日本に限ったものではありません。本場中国をはじめ台湾でも、薬膳はもてはやされています。そんな薬膳料理の材料として、ある日本産の食材が活躍しています。それは、ナガイモ。特に台湾では、日本からナガイモを輸入する動きが顕著です。現地でも生産されていますが、日本産と比べるとアクが出やすく、シャキッとした歯ごたえに欠けるのだとか。さらに日本産食品の高い安全性が、現地で受けている理由のひとつといえそうです。 さらにいうと、滋養強壮をつかさどるナガイモは台湾においても人気の健康食品とみなされています。「山薬」と呼ばれ、漢方薬と位置づけられることもあるほどです。その山芋を駆使した薬膳料理が、健康志向の人々のハートを掴んだといえます。また、日本ですとナガイモといえば、すりおろして「とろろ」にし、ご飯やお蕎麦にあしらって食べることが一般的。他にあまりコレといった料理法は普及していないといえますが、台湾ではちょっと変わった食べ方をしています。中でも驚くのは、「ナガイモのジュース」です。ナガイモをミキサーにかけて、砂糖などを使って甘くした飲み物。なかなか想像できないと思いますが、けっこうイケるんだとか。確かにあの食感で甘いということは、「シェイク」のような感覚になるかもしれませんね。 食料自給率の低い日本でありながら、逆に「メイド・イン・ジャパン」として世界に広まりを見せる野菜があるということ、なんだかちょっと誇れる気分になりますね。 |
 昨今、巷で薬膳を謳い文句にする料理店に、必ずといっていいほど提供しているメニューが「火鍋」です。「薬膳火鍋」などの名前、目にしたことのある方も多いと思います。
昨今、巷で薬膳を謳い文句にする料理店に、必ずといっていいほど提供しているメニューが「火鍋」です。「薬膳火鍋」などの名前、目にしたことのある方も多いと思います。“火”とつくものの、火鍋とは中国の寄せ鍋料理全般を指すことば。一般の鍋料理と、さして変わるものではありません。ただし鍋の形状は、中央に煙突があり、その中に炭火などを入れて熱するようになっていることが一般的です。鍋には仕切りがあり、白湯のスープと、赤くてピリ辛の麻辣スープ、2つの味が楽しめるようになっているものも多くみられます。 そのルーツには諸説あり、モンゴル高原の南部一帯地域で羊の肉を鍋で煮たことが始まりともいわれています。その後、各地に広まり、四川風や北京風などにアレンジされていきます。北京料理のひとつである「シュワンヤンロウ」という料理は、羊の肉を鍋の湯にくぐらせて食べるもの。一説には、これが日本における「しゃぶしゃぶ」のルーツではないかといわれています。 ちなみに、日本の冬に欠かせない料理である「おでん」は、アジア諸国でも幅広い人気を誇っています。台湾ではおでんのことを「黒輪」と言い、読みは「オーレン」です。日本と同様に、コンビニエンスストアでも販売しています。煮たまごやしらたき、昆布や練り物など、日本と似通った具に加え、冬瓜などがあるのも面白いところ。台湾へ行く機会があるならば、コンビニを覗いてみても楽しいですよ。韓国での呼び名は、そのままズバリ「オデン」です。具としては、魚の練り物を串にさしたものが主流。おでんのダシ自体を、焼酎のつまみにする人も珍しくありません。 「冬の寒さには鍋料理」という感覚は、万国共通のものといえそうですね。 |
|
薬膳という言葉は、さも古くから伝わっているような印象を受けがちですが、言葉そのものが登場し始めたのは1980年代になってからと言われています。ただ、薬膳の元になる考え方は、ずいぶんと古くから存在しています。 中国の古典的な医学書に『黄帝内経 (こうていだいけい)』というものがあります。この本が書かれたのは、中国の戦国時代。今から2300年も前です。現在も意訳版が数多く出版されており、中医学を学ぶ際には欠かせない超ロングセラーの本といえるでしょう。 『黄帝内経』は、時の権力者だった黄帝が、岐伯(ぎはく)ら当時の医師たちと健康についての会話をしているスタイルで書かれています。薬膳の考え方のもとにある漢方、さらに鍼灸、気功などについても書かれていますが、基本的には“病気になってから”治すというより、“病気になる前に”どんな身体を保っておくべきか、を説いたものです。黄帝と医師たちとのやりとりに中にも「聖人は、すでに病になっているものを治すのではなく、未病を治す」という一説があります。この「未病(病気へ向かっている状態)」という言葉が最初に登場したのも、この『黄帝内経』といわれています。 『黄帝内経』をはじめとした中医学の本に書かれていることの中には、現在にも相通じる発想が随所に盛り込まれている点も興味深いところ。たとえば「一物全体」という考えは、現在でいうところの「ホールフード」、つまり食材は捨てるところを極力減らし、丸ごと食べるという考えです。食べる部分と食べない部分を、暗にわけないということですね。 お米にしても、精米して“白米”とするよりも、栄養価の高い胚芽部分などを残した“玄米”を食べることを勧めたり、果物のみかんにしても、胃腸の熱を取る実の部分はもちろん、皮を干すと“陳皮(ちんぴ)”という生薬になります。生きているもの、食材をすべて使いきるという発想ですね。皆さんも、調理する際にはなるべく「一物全体」の考えを頭のすみに置いてみてはいかがでしょう。 |