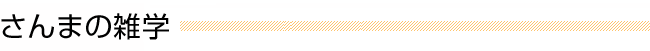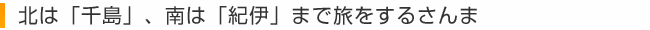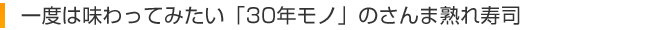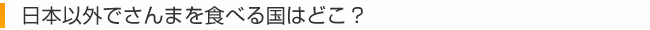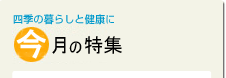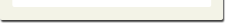HOME > 健康の雑学 > 【2009年10月号】さんまの雑学
さんまはどんなルートを辿り、いつ「旬」を迎えるのか?日本以外でさんまを食べる国は?さんまについての雑学をお送りいたします。
|
|
 さんまは日本近海からアメリカ西海岸まで、太平洋に生息しています。とりわけアジア側に多いため、日本沿岸はまさにうってつけの漁場。さんまが多く食べられているのもうなずけます。
さんまは日本近海からアメリカ西海岸まで、太平洋に生息しています。とりわけアジア側に多いため、日本沿岸はまさにうってつけの漁場。さんまが多く食べられているのもうなずけます。さんまの「生まれ」は四国や紀伊半島南部の黒潮。春になると、さんまは水温の低い海域を目指して、日本の太平洋側を北上します。千島近辺の海域で餌を食べてすくすくと成長したさんまは、夏の終わりごろになると南下を始めます。産卵を控えたこの時期が、脂が乗って美味しい「旬」のさんま。8月頃になると北海道の東で獲れ始め、そこから三陸沖、常陸沖と、いわゆる「さんま前線」といったぐあいに「旬」が南下してくることになります。 南下を続けたさんまは、長旅の疲れ?もあって、だんだんとやせ細り、脂が落ちていきます。 そこでたどり着くのは紀伊半島沖。今となっては道東や三陸で水揚げされたプリプリのさんまが食卓に上りますが、かつては輸送手段も漁法も発展していなかったため、なかなか全国区になることはありませんでした。それにひきかえ紀伊半島では、比較的沿岸でさんまを獲ることができたことから「さんまの名産地」でもありました。海流や水温が今と昔では若干異なることも、紀伊がさんまの名産地だった理由のひとつです。 |
干物としては、さんまが北上する前、つまり稚魚の段階で獲り、丸干しにした「針子(はりこ)」が有名。伊豆半島沿岸部の名産品でもあります。逆に、成長を遂げて南下したあとのさんまは開きなどにして干物となります。かつて江戸の庶民の間で流行した「お伊勢まいり」の際、伊勢神宮の門前市でおみやげにさんまの干物を買う、といったことも多くあったといい、今でも名物のひとつになっています。
そして、お寿司。さんま寿司は三重県の南部から和歌山の熊野灘沿岸にかけての名物料理です。酢で浅めに漬けたさんまの姿寿司も有名ですが、この地方独特なのは、晩秋に獲れるさんまを糠に漬け込んだ「なれずし」。独特の風味を持ち、お正月などの「ハレの日」の料理として振舞われました。
現在、もし熊野方面に旅行する予定のある方にオススメしたいのが、新宮市にある「東宝茶屋」。ここでは、この地方特有の「頭ごと、まるまる漬け込んだ」さんま寿司を味わうことができます。さらに同店でしか味わえないといえるのが、なんと30年もの間熟成させた熟れ寿司。当然ながらさんまの姿をとどめておらず、ヨーグルトのような質感になっています。まさに珍味中の珍味。さんまの濃厚な旨味だけが、長い時を経て凝縮されたような味わいです。
 海外在住の日本の方にとって、やはりさんまは「懐かしの味」。アメリカなどでも日系のスーパーに行けば入手できることもありますが、やはり日本のさんまより痩せていたり、冷凍輸入モノが大半であるため、どうしても味は落ちがちとなります。
海外在住の日本の方にとって、やはりさんまは「懐かしの味」。アメリカなどでも日系のスーパーに行けば入手できることもありますが、やはり日本のさんまより痩せていたり、冷凍輸入モノが大半であるため、どうしても味は落ちがちとなります。しかしながらアジア圏では、さんまを食べる文化があります。中国において、さんまは日本ほどポピュラーな食材ではありませんが、日本と同じく「秋刀魚」と書き、中華料理の食材として駆使されることもあります。 一方、韓国においてさんまは「コンチ」と呼ばれ、辛味を加えた煮物にしたり、鍋に入れたりして食べられていますが(さすがに刺身は馴染みがないようですが)、海に面した浦項(ポハン)市には、秋に獲れたさんまを潮風にさらして干した「クァメギ」と呼ばれる名産品があります。もともとはニシンで作られていたそうですが、60年代以降は漁獲量が減ったため、代替品としてさんまで「クァメギ」が作られるようになりました。いわゆる一般的な魚の干物よりも脂のノリがよく、身を割いてチョコチュジャン(酢入りの唐辛子味噌)やにんにくスライスなどを乗せ、海苔やエゴマの葉などで包んで食べます。 |