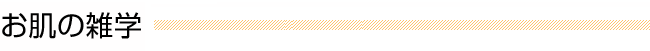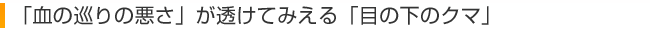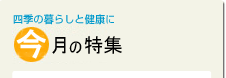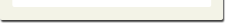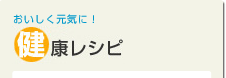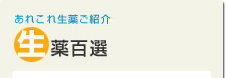HOME > 健康の雑学 > 【2009年9月号】お肌の雑学
人種による肌タイプの違いは?日本古来のスキンケア用品とは?お肌とスキンケアに関する雑学をご紹介します。
|
|
 さて、今月の特集では「夏の紫外線」がお肌のさまざまなトラブルの原因になることを説明しましたが、紫外線は「100%」悪者ではありません。骨を形成し、強くするといわれているビタミンDは、皮膚が紫外線を浴びることで作られます。最近はあまり耳にしなくなりましたが、日光を浴びない幼児が「クル病」になるといったこともありました。
さて、今月の特集では「夏の紫外線」がお肌のさまざまなトラブルの原因になることを説明しましたが、紫外線は「100%」悪者ではありません。骨を形成し、強くするといわれているビタミンDは、皮膚が紫外線を浴びることで作られます。最近はあまり耳にしなくなりましたが、日光を浴びない幼児が「クル病」になるといったこともありました。昨今では、1日に15分程度、日光に浴びさえすれば必要なビタミンDが作られるというデータが出ていますが、そんなデータがない頃、ちょうど高度成長期の頃には「日焼け」「小麦色の肌」がちょっとしたブームになり、数多くのサンオイルが世に出回りました。紫外線の影響がだんだんとわかりはじめ、「美白の肌」こそが美しいという価値観が顕著になったのは80年代に入ってからといえます。 さて、少し大きな視点から、肌と紫外線の関係について述べてみましょう。もともと人類が誕生したといわれているのが東アフリカです。当初は森などで暮らしていた人々が、日光をさえぎるものが少ない平原で生活するようになり、長い時をかけて人類の肌はメラニン色素の影響で黒くなったといわれています。それは同時に、紫外線をこれ以上受け付けないためのシールドにもなっていました。 そして人びとはヨーロッパに広がります。ここでは紫外線の量が少ないため、摂取するために肌が白くなったといわれています。欧米人の多くは表皮が厚く、真皮が薄い肌質を備えています。紫外線を防ぐ機能が弱いため、日光浴などをすると黒くなるのではなく赤くなり、若者であってもシミやシワなどが生じやすいといえます。その一方で私達アジア人は真皮が厚いため、欧米人に比べて肌のトラブルが生じにくい、ともいわれています。 |
 今では実にたくさんのスキンケア用品が世に出回っていますが、昔の日本はどうだったのでしょうか?さまざまな天然素材がお肌に試される中で、よく知られている3つをご紹介してみましょう。
今では実にたくさんのスキンケア用品が世に出回っていますが、昔の日本はどうだったのでしょうか?さまざまな天然素材がお肌に試される中で、よく知られている3つをご紹介してみましょう。まずは「へちま水」。いつの時代も女性は美しくありたいもの。江戸時代の「大奥」において、今でいうところの化粧水として尊ばれていたといわれているのが「へちま水」です。「へちま水」を取るのは9月頃。地上30センチほどのところでツルを切って、その先を容器の中に垂らしておくと貯まります。化粧水のほか、咳止めやむくみなどに対処する薬としても売られていました。ちなみに東京・上野と谷中の境にある浄名院では、毎年十五夜の日になると「へちま供養」が行なわれ、この日にお参りすると咳や喘息によいといわれています。
次は「米ぬか」。そのまま肌に塗るのではなく、木綿などの袋に入れて、カラダをゴシゴシとこすったり、湯殿に浮かべたりして使用していました。こちらは汚れを取るとされていましたから、今でいえば石鹸にあたりますね。江戸の銭湯では番台で米ぬかを売っているところもあったとか。汚れを取るほかにも、角質が取れることからくすみ予防になったり、潤いを保つともいわれています。
さらに、ご存知の方もいらっしゃると思いますが「うぐいすの糞」。今でいえば洗顔料でしょうか。糞に含まれた酵素が、肌にキメ細かさをもたらし、美白効果があるといわれていますが、昔の人は酵素など知りえませんから、最初に使った人は勇気がありますよね。もともと衣類のシミ抜きとして使われていたそうです。ちなみに現在も「うぐいすの粉」などの名前で売られています。
他人から「疲れているな」と思われてしまうクマは、なぜできるのか?目の周囲は他に比べて皮膚がとても薄く、血管などの色が透けてみえる部分です。疲れたり、ストレスが貯まったり、寝不足になった時などは毛細血管の血液がうっ血した状態になり、皮膚が薄いゆえに黒味を帯びてみえる・・・それがクマの正体。さらに紫外線やこすりすぎなどによって、皮膚にメラニン色素が沈着した場合にもクマとなります。
そのため、クマを解消するためには血の巡りをよくしてあげることが必要となります。温めたタオルで目を被い、しばらくしたのちに今度は冷やしたタオルで目を被う・・・温めることと冷やすことを交互に行なうことによって血行がよくなり、クマが解消されやすくなります。これは「むくみ」にも効果的です。
また、目の周りのマッサージも効果的。1分程度、目尻から目の下を通って眉間まで、指をあててやさしく揉み解してください。先ほど述べたように「こすりすぎ」もクマの原因となりますので、あくまでも「やさしく」マッサージするようにしてくださいね。これは目のメイクを落とすときにも同じことがいえます。