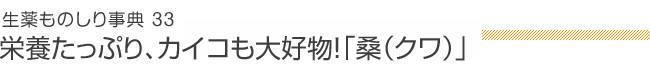今回の「生薬ものしり事典」は、過去にご紹介した生薬百選より、ポリフェノールや必須アミノ酸も豊富な生薬「桑(クワ)」をピックアップしました。
|
感冒薬から老化防止にも役立つ生薬 |
|||||||
|
子ども時代、5月の下旬頃になると、黒く熟した桑の実をもいで食べたことがある人も少なくないのではないでしょうか。桑は昔からそのさまざまな部位が薬として利用され続けています。
桑は薬用に使用する部位が多くあります。「日本薬局方」には、冬に根を掘り、皮部を剥いで天日乾燥した「桑白皮(そうはくひ)」が収載されています。民間では、葉や実なども薬用とされ、11月頃の葉を採取して天日乾燥したものを「桑葉(そうよう)」といい、4〜6月頃に若い枝を刈り取り、天日乾燥したものを「桑枝(そうし)」、実の部分(果穂)を集めて乾燥したものを「桑椹(そうじん)」と呼んでいます。
●「桑白皮」は漢方では消炎性利尿、緩下、去痰、鎮咳、鎮静などに処方されます。 ●「桑葉」はお茶として、フラボノイドの抗菌作用のほか、感冒などの発熱、頭痛、結膜炎、口渇、咳嗽など用途は数多くあります。 ●「桑枝」は漢方では去風湿の効果から、主に関節の痛みや四肢のひきつり、浮腫などに用います。 ●「桑椹」はポリフェノールやアントシアニン、ビタミン、ミネラルが多いほか、必須アミノ酸もバランスよく含まれており、補養薬や、補腎として老化防止に使われています。
桑は、実が付いて初めて気付くほど、花が咲いていることに気付きにくい地味な花です。花期は4月から5月の春先で、新しい枝の基部に淡黄色の小花が密集した楕円形の花序をつけます。1本の木に雄花と雌花をつける雌雄同株と、雌花だけ、または雄花だけをそれぞれつける雌雄異株の両方があります。雄花がたくさん集まった雄花序は円柱形になって垂れ下がり、オシベが4本、雌花がたくさん集まった雌花序(写真)は長楕円形で、花柱のないメシベが1本あります。雄花、雌花ともに花弁が無く、がくは4枚あります。 | |||||||