

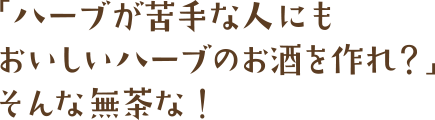
 の件は、ダメになった」
の件は、ダメになった」
所長からそう伝えられたとき、Aの頭の中は真っ白になった。
ここは養命酒製造の研究室。Aはその研究員の一人である。
あの件とは先の、ハーブで作ったお酒『ハーブの恵み』の後継商品開発のことだ。
ハーブの恵みがヒットしたのを受け、養命酒製造ではハーブで作ったお酒の第二弾の開発に着手していたのである。
次は名酒にも勝る製品にして市場の勢力図を塗りかえてやる、という意気込みで研究員一丸となり試作品を開発。鼻息荒く市場テストに送り出したのが数日前のことだった。
しかし大きな期待とは裏腹に評価は芳しくなかった。正確にいうと散々だった。
その結果を受け、上層部は後継商品の開発を気持ちいいほど潔く諦め、冒頭の言葉に至ったのである。
ハーブには独特の香りと味がある。その香りと味を、Aはこよなく愛していた。
できればハーブと結婚したい。ハーブと俺が子どもを作ったらきっとかわいいはずだ。ちょっと変質的なくらいハーブに惚れ込んでいたのだ。
だからこそ第二弾製品は、ハーブの魅力を存分に楽しんでもらえる物ができたと絶対の自信を持っていた。
しかし世の中にはハーブ好きな人もいれば、ハーブの香りや味に抵抗を感じる人もいる。その人たちを納得させられなかったことに、Aは激しい悔しさを覚えた。
(こんなことでは、ハーブと結婚できない!)
だいぶんズレた感傷に浸る間もなく、所長は言葉をつづけた。
「ハーブだけでつくる酒には限界があるな。
もう一度ゼロから考えよう。
ハーブのお酒がもっとおいしくなるために、あらゆるアイデアを試すんだ!」
Aは飛び上がった。
「それは…たとえばハーブに何かを配合するということですか!?」
「それもアリだ。おいしくなるなら、ラー油でも唐辛子でもなんでも試せ」
「唐辛子って…いや、そんなことをしたらハーブの味や香りが飛んじゃいますよ!」
「そこだよ。ハーブの香りや味は『ハーブの恵み』で味わえるんだから、
 次はハーブの魅力を生かしつつ、
次はハーブの魅力を生かしつつ、
ハーブの味や香りをまろやかにしたお酒を作るんだ。
そうすればハーブが苦手な人も飲めて万々歳じゃないか」
「ハーブの成分を生かしつつ、
ハーブの香りや味をまろやかに?カンタンに言わ…」
反論が終わらぬうちに、所長の分厚い手がAの両肩をがっしりとつかんだ。
「お前ならできる!いや、これはハーブを誰よりも愛しているお前しかできん!」
中身のない説得である。勢いだけである。
しかし、Aは感銘を受けた。
なんてことだ。所長がそこまで俺を買ってくれていたとは!
単純な男である。Aの奥底に眠っていた男気が久しぶりに目を覚ました。
ここまで言われてやらなきゃ、男じゃねぇ!
「任せてください所長!」
「やってくれるか!」
二人の男は、はっしと手を取り合った。
大丈夫か、A! 丸めこまれているぞ、A!
とにもかくにも、こうしてAの新たな試練の日々が幕を開けたのである。


 は頭を抱えていた。アイデア会議の当日である。
は頭を抱えていた。アイデア会議の当日である。
ハーブの成分だけを生かして味や香りをまろやかにするという難題をどうしたものかと、ずっと悩みつづけていたのだが、結局なにも思いつかなかったのだ。
(そもそもハーブの味や香りを生かした商品こそがウチらしさじゃないのか?)
ハーブの味と香りをいかに引き出すかに心血を注いできたAにとって、今回のミッションは味噌味のしない味噌ラーメンをつくれと言われているようなものだった。
そんなAの苦しみをよそに、意外にも会議ではさまざまなアイデアが出てきた。
なかでもS美という研究員が放った
「お茶をベースにしたらどうでしょう」
というアイデアに、Aはハッとした。
なるほど。ハーブもハーブティーにするくらいだ、お茶と相性がいいかもしれない。
うむ、悪くないアイデアだ。Aは心の中でうなった。さすがウチの研究所には、有能な人材がひしめいている。
同僚たちを頼もしく思うと同時に、Aは自分を恥ずかしく思った。ハーブの味や香りを生かすお酒で研究してきたのはみんな同じだ。しかしその開発の方針が180度変わっても仲間たちは文句を言わず、課題をクリアしておいしいお酒を作ろうと意見を出し合っている。それなのに自分だけが、ノーアイデアだとは…。
Aの新たな苦悩をよそに、その後も活発に意見がだされた。しかしどれも面白い発想ではあるものの、これという決め手に欠け、次第に発言が減り、会議室の空気が重くなりだした。しょう油やカレー粉を配合したらどうか、というアイデアが出たあたりからは、ここはなんの会社なのかすら見失いはじめたようだった。
Aは焦った。
(こんな時こそ、俺が打開策を見つけなければ!)
所長の視線も痛いことだし。なにか考えろ…何か…
(だめだ! ハブ酒を配合する、ハブハーブ酒しか思いつかない!)
ハーブの次にダジャレを愛するAであった。
しかし人間、本当に追いつめられると、なんとか道を切り拓くものである。その時のAにも、天啓のようにヒラメキが降りてきた。
(フルーツだ! 女性はフルーツが好きだし、ハーブにもきっと合うに違いない!)
これしかない、という確信が湧いた。
Aはゆっくりと口を開いた。
 「フルーツはどうでしょう」
「フルーツはどうでしょう」
会議室がとたんに静まり返り、全員の視線が集まった。
……S美に。
タッチの差で同じ発想を発言したのはS美だったのである。
「たとえばレモンなら、ハーブと相性がいいと思います。
フルーツなら、きっとおいしくなると思います」
おお! 全員が、一瞬でピンときた顔になった。
「それだ! それしかない!」
所長の声がひときわ大きく響きわたる。
「さすがはS美くんだ! こういうアイデアを待っていたんだよ!」
所長、それはいま僕も言おうと……
しかし所長はAが必死に訴える視線に気づかない。
「Aも見習えよ、はっはっは!」
しょちょぉおおお……
気を確かに持て、A! きっと誰かが見ててくれるぞ!
Aの評価とテンションだけが微妙に落ち、ハーブにフルーツを配合するお酒の開発が決まったのである。


 ーブやフルーツと格闘する日々が始まった。
ーブやフルーツと格闘する日々が始まった。
試作品の開発である。商品はひとつのハーブで作るのではなく、数種類のハーブをブレンドする。さまざまなハーブの成分がおりなすハーモニーが、言いようもない味を生み出すのだ。
しかし、そこにフルーツをブレンドするのは未知の領域である。ハーブ同士の相性に加えて、フルーツとの相性も考慮しなくてはならず、生薬やハーブを扱うことなら俺に並ぶ者はいないと自負するAも少々不安だった。勘で組み合わせる訳にはいかないので、世界中の文献やレシピなども山ほど読みあさった。
そうした研究のすえ、無数にあるハーブから、まずはフルーツと香りの相性がよさそうなハーブを20種ほど選びだした。その20種のハーブの抽出液を、レモンやリンゴ、桃、ぶどう、グレープフルーツ、カシス、ウメなどのフルーツの果汁とブレンドし、もっとも香りの相性がよいフルーツ&ハーブのカップルを探す。
「香りのカップル」探しが終わると次に、体によいと言われるハーブを、これまた20種類ほど選びだす。それを「香りのカップル」にブレンドしていく。
こうしてブレンドにブレンドを重ねる、ブレンドスパイラルな日々がつづくのである。
香りと味、成分がパーフェクトなバランスで保たれた試作品ができるまで。
たいていは納得するような味ができず、やり直すことになる。
ハーブの抽出液同士の配合はもちろん、ときには「香りのカップル」自体の組み合わせから考え直し、何度も、何度も。もっとおいしく、もっとまろやかに。全員が研究者魂を発揮して、試作は毎日、何週間もつづけられた。
その時間でAの舌は、ハーブやフルーツの繊細な味や香りをハッキリと感じられるまでに研ぎ澄まされていった。まるで、あらゆるワインの味を知るソムリエのように。
そしてついにAは、自分のソムリエ舌を唸らせる試作品をつくりあげた。
 Aが発見した、フルーツとハーブの至高の配合。
Aが発見した、フルーツとハーブの至高の配合。
それが「桃とペパーミント」を配合したお酒である。
(これこそ、俺の血と汗と涙とハーブ愛の結晶だ!)
自信がある。これは必ず売れる。社員生命を賭けてもいい。
一片の疑問も持たず、Aはさっそく研究所内の官能試験で披露した。
はたして。
「なにこれ? こんな歯磨き粉みたいな味、ダメに決まってるじゃない」
最初に発したS美の言葉で、Aの自信は木っ端みじんに吹き飛んだ。
「うん、歯磨き粉を飲んでるみたい」
「クセがありすぎるから、万人ウケはしないわね」
「わたしはムリ」
その後も、女性陣から容赦ないコメントが雨あられとつづいた。
「……」
言葉がでなかった。俺の、血と汗となんやかんやの結晶を、歯磨き粉だとぅ!?
(俺の味覚っておかしいのかな…)
一時は打ちひしがれたAであった。しかしそうした屈辱を味わったのはAだけではない。
研究員のほとんどが自信作を否定され、心の中で涙をながしながら、それでも次こそは最高においしいお酒をと開発に取りくんでいるのである。
そうした苦しみの日々が、丸2ヶ月つづいたのち。
ようやく、レモン、リンゴ、グレープフルーツにそれぞれ5種のハーブを配合した試作品が、全員の厳しい味覚を納得させるに至った。
しかしAよ、安心するのは百年早いぞ!
製品化に向けた、最後の闘いが待っているのを忘れたわけではあるまいな!
(そうだ、ここからが正念場だ!)
これから待ち受ける試練を思い起こし、改めて気を引き締めるAであった。

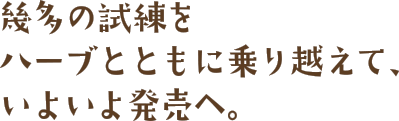
 いしい試作品ができたからといって、
いしい試作品ができたからといって、
すぐに商品化というわけにはいかない。実はこれからが、研究員たちにとっても試作品にとっても本当の苦難のはじまりなのである。
出来あがったときにどんなにおいしくても、店頭や家に置かれている間に味や見栄えが悪くなっては商品として失格である。
特にハーブの中には、風味が変化しやすいデリケートなものがあるのだ。数週間置いておくだけで、とても飲めないシロモノになることも珍しくない。そのため、時間が経っても味が変わったり濁ったりしないかなど、商品化に向けての厳しいテストを行うのである。
テストで試作品は、さまざまな過酷な環境に置かれる。
高温下に何日も放置しておいたり、直射日光に何日もさらしてみたり。あるいは強い光をずっとあててみたりと、試作品の根性を試すかのような試練がいくつも課されるのである。
そして、テスト後の試作品の味や香りにどんな変化が起こっているかを、研究員自らの舌で確かめる。
これが恐怖の瞬間なのである。なにしろ、どんな味になっているのかは、口に入れてみるまでわからないのだ。もはや軽い罰ゲームである。
しかし苦労して育て上げたわが子のような試作品である。今度こそうまくいっていてくれ!毎回、心からそう願いながら、口に含む。
「ぐはぁぁぁぁ!」
無情にも、Aが丹精込めてつくりあげた今回の試作品はプラスチックのような風味に変わり果てていた。くそ、また失敗か!
失敗するごとに、ハーブの配合量を変えてみたり、組み合わせるハーブを変えたりなど、違うレシピをつくっては官能試験にかける。
「あひゃあぁぁぁ」
その度に、誰かの舌が今まで味わったことのない珍妙な味を体感することとなった。
研究員全員が体を張って、こうした辛酸を舐めながら、いつ終わるともしれないレシピ作りに取りくむこと、なんと8ヶ月。試したレシピのパターン数が軽く100を超え、上層部や営業部から「早く完成させろ」と叩かれつづけた尻がヒリヒリするのも感じなくなった頃。
ようやく、すべてのテストを耐えぬいた「フルーツとハーブのお酒」が完成した。
開発が決まってからおよそ1年2ヶ月のことである。
 前作では散々だった市場テストでの評価も上々。
前作では散々だった市場テストでの評価も上々。
正式に商品化が決まったと所長から告げられた時、
研究室は歓びと安堵の空気に包まれた。
大きなプレッシャーから解放された瞬間だった。
(ついにやったのだ!)
思い返せば、大変なことばかりだった。試作品のレシピのメモをうっかり間違え、官能試験でとんでもない味を同僚に飲ませたりもした。その他にも書けない苦しみや大人の事情が山ほどあった。しかし、そんな苦い思い出たちも、いまとなっては懐かしい。
早くこの新たな自信作を、一人でも多くの人に味わってほしい。そして『ハーブの恵み』に負けないくらいのヒット商品になってほしい。
Aは心からそう思った。
そうしたら……
(次こそ「桃とペパーミント」をラインナップに加えてやるぞ)
はやくも次の野望をたぎらす、懲りないAであった。
※(所長注:あくまでA個人の願望です。)
![]()
このストーリーは、事実を基に制作されています。
登場人物は架空ですが、開発〜発売にいたる苦労のほとんどが真実です。