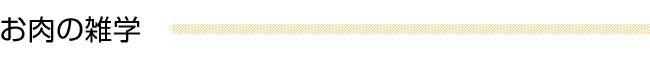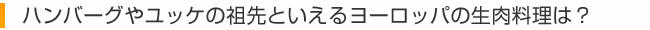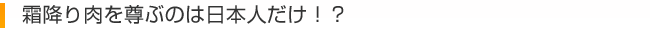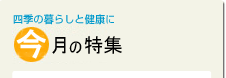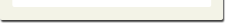HOME > 健康の雑学 > 【2012年9月号】 お肉の雑学
うさぎを「1羽2羽」と数えるのは食いしん坊の発案?ハンバーグの祖先といえる生肉料理とは?“霜降り”のお肉を尊ぶのは日本人だけ?
 日本で獣の肉を食べることが普及したのは、明治時代のこと。政府が肉食を奨励し、明治5年に明治天皇が初めて牛肉を食べたことがきっかけとなりました。もともと日本には仏教の影響もあって「肉食は避けるべきもの」という風潮がありましたが、その一方で、肉の美味しさに魅了された人も少なからずいました。なんとかして食べたい…その切なる思いが、さまざまな“ことば”を生み出しました。単刀直入にいえば“言い逃れ”といえるかも!?
日本で獣の肉を食べることが普及したのは、明治時代のこと。政府が肉食を奨励し、明治5年に明治天皇が初めて牛肉を食べたことがきっかけとなりました。もともと日本には仏教の影響もあって「肉食は避けるべきもの」という風潮がありましたが、その一方で、肉の美味しさに魅了された人も少なからずいました。なんとかして食べたい…その切なる思いが、さまざまな“ことば”を生み出しました。単刀直入にいえば“言い逃れ”といえるかも!?
たとえば、うさぎ。獣なのに「一羽、二羽」と数えることに違和感を覚えませんか?これは、肉食の中では比較的寛容だった、鳥肉になぞらえてのこと。うさぎを鳥に見立て、コレならOKとみなして食べたお坊さんもいたそうです。さらに、肉が食べたいあまりに鳥の「鵜(う)」と「鷺(さぎ)」を足して「うさぎ」と名付いたという説も!当のうさぎからすると、ハタ迷惑はなはだしいですね。
次に、猪。山の猟師にとっては馴染みの食材でしたが、江戸の街でも「猪は美味しいらしい」という噂が一部で広まり、晴れて猪鍋の店がオープンします。しかし、おおっぴらに看板を掲げるとなると、嫌がらせを受けるかもしれない…そこで考案されたのが「山くじら」ということば。くじらの食感と似ているということで、猪は「山くじら」と呼ばれ、開店が相次ぎました。
そもそも、猪や鹿などの獣肉は、山間部に暮らす人びとにとっては貴重なタンパク源でした。特に冬場は滋養強壮のために、獣の肉をよく食べたそうです。こうしたことから生まれたことばが“薬喰い”。肉を薬になぞらえることで、肉食のタブーを回避しようとしたわけです。そのため、俳句の世界でも“薬喰い”は冬の季語になっています。
『客僧の 狸寝入りや くすり喰ひ』
これは江戸中期の俳人、与謝蕪村の句です。旅の僧侶が、狸寝入り(要は、仮病)を使ってでも肉を食べようとするさまを、おもしろおかしく皮肉っています。なんとか肉を食べるために、それこそ一休さんのとんちのような機転を次々と繰り出した日本人。その滑稽ぶりも含め、面白い歴史の一幕といえますね。
 日本では「レバ刺し」や「ユッケ」など、食の安全の観点から、生肉を使った料理の規制が相次いでいます。生肉料理が苦手な人にとっては「焼く、煮る、蒸す。なんでも美味しくなるのに、なぜ生で食べるの?」と思われるかもしれません。しかし世界には、さまざまな生肉料理が存在しています。
日本では「レバ刺し」や「ユッケ」など、食の安全の観点から、生肉を使った料理の規制が相次いでいます。生肉料理が苦手な人にとっては「焼く、煮る、蒸す。なんでも美味しくなるのに、なぜ生で食べるの?」と思われるかもしれません。しかし世界には、さまざまな生肉料理が存在しています。
ヨーロッパにおいて代表的な生肉料理といえば、タルタルステーキ。「タルタル」とは、13世紀頃にヨーロッパへ攻め込んだモンゴル帝国の「タルタル人(タタール人)」のことを指し、その調理法も彼らから伝わったという説が一般的です。牛や馬の生肉をみじん切りにして、オリーブオイルやこしょう、塩などで味付けし、刻んだ玉ねぎやパセリなどの薬味と卵黄をのせて食べます。ゴマ油を加えていないだけで、限りなくユッケに似ていますね。それもそのはず、実際に遊牧民によってこの料理が朝鮮半島へ伝わり、ユッケが生まれたといわれています。さらにもうひとつ、タルタルステーキから発展した有名な料理といえばハンバーグ。ドイツのハンブルグでタルタルステーキを焼いて食べる習慣があったことから、「ハンブルグ」が訛って、その名がついたそうです。
アフリカのエチオピアにも、昔から生肉を食べる習慣があります。ミンチにした牛などの生肉に、スパイスとケべ(バター)をかけて食べる「クトフォー」という料理は、結婚式や接待の席で振る舞われるご馳走の一種。庶民にとっては高嶺の花ですが、彼らは彼らで生肉のかたまりを注文し、ナイフで削ぎながらワイルドに食べたり、価格の安い生の内臓料理を楽しんでいます。
当然ここで「暑い国なのに大丈夫?」という疑問が湧いてきます。結果からいうと、お腹を壊すケースも多々あるようで、生肉を避けるエチオピア人もいるようですが、多くの人は“新鮮な肉が卸される市場の開催日しか食べない”と決めて、生肉料理を楽しんでいるようです。エチオピアでは、宗教(エチオピア正教)の戒律で、水曜と金曜は肉や卵、乳製品を食べてはいけないことになっています。生肉を食べたい人は、土曜に開かれる食肉市場へ足を運び、市場の食堂で舌鼓を打ちます。“肉の解禁日”を存分に楽しんでいるというわけです。
 お肉に細かいサシ(脂肪)が入った“霜降り”の牛肉は、いわずもがなの高級食材。とろけるような食感と美味しさを誇るサーロインや肩ロースなどの霜降り肉は、贈答品としても最高ランクに位置付けられています。
お肉に細かいサシ(脂肪)が入った“霜降り”の牛肉は、いわずもがなの高級食材。とろけるような食感と美味しさを誇るサーロインや肩ロースなどの霜降り肉は、贈答品としても最高ランクに位置付けられています。
しかし欧米諸国では、日本ほど霜降り肉を尊ぶ風潮はなく、脂肪がふんだんに入った牛肉よりも赤身を好む傾向があります。その理由のひとつは、料理の違いにありそうです。
しゃぶしゃぶやすき焼きなど、日本の料理の中には、薄切りにしたお肉を使うものが多々あります。脂肪の少ない赤身だと、すぐに縮まって硬くなってしまうため、多少なりとも脂肪を含んだお肉のほうが向いています。一方、欧米諸国の料理は分厚い肉を使うことが多く、フランス料理などは、「お肉の味とは、脂肪の味ではなく、赤身の味」という理念のもと、ソースに工夫を凝らして赤身とのマッチングを楽しみます。
なにより、欧米諸国の料理に霜降りなどのお肉を使ったとしたら、肥満が大問題になっているはずです。2009年、日本人一人当りの牛肉消費量は5.9kgでした。かたや、世界一の牛肉消費国と呼ばれるアルゼンチンでは、なんと73.1kg!日本人は豚や鶏などもまんべんなく食べているとはいえ、その差は歴然です。彼らは、バーベキューのような炭火焼きにして食べる「アサード」が大好物。その際、脂肪部分はそぎ落として赤身だけを楽しみます。
最近は日本でも、赤身牛肉のヘルシーさが注目されるようになりました。では、このまま霜降り肉の人気が落ちていくのかというと…そうはならないと思います。やはり、その美味しさはなかなか否定できませんよね。先ほど、欧米では赤身を好む傾向があると述べましたが、そもそも霜降り肉を食べたことがない、という方も多いことでしょう。いったん口にするやいなや、その美味しさにとりつかれて熱烈なファンになる欧米人もいます。
ハリウッドの映画俳優たちの間でも、サシが入りやすい日本産の牛肉はかなりの人気だとか。さらに興味深いのが、全米プロバスケットボールのスーパースター、コービー・ブライアント選手。彼の名前のつづり「Kobe(コービー)」は、父親が大の「Kobe-Beef(神戸牛)」ファンだったことが由来となっています。