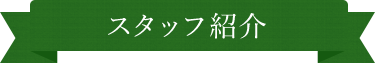駒ヶ根工場敷地内にある「健康の森」は、豊かな清流・緑の木々、澄んだ空気が育んだ貴重な自然を多くの人々と分かち合う、癒しの森。
駒ヶ根工場で働くスタッフから、健康の森の自然をご紹介します。
-
花の形はほとんどアザミですが、葉や茎にとげがありません。
葉っぱはこんな感じです。
「タムラソウ」の名前の由来は図鑑でも不明でした。
私は、田村さんという人が命名したのかと思っていました。こちらは、
「アキノキリンソウ(キク科)」(撮影日:9月24日)です。
林内のあちらこちらで見かけます。こちらは、
「シラネセンキュウ(セリ科)」)」(撮影日:9月17日)です。
この「シラネセンキュウ」などセリ科の野草には、
蝶の「キアゲハの幼虫」がよく集ります。
写真は、同じセリ科の「ノダケ」に集っていたところです。こちらは、アザミの仲間(キク科)(撮影日:9月17日)です。
山野草コースなど、構内のあちこちに沢山咲いています。
「ナンブアザミ」かと思っていましたが、図鑑と見比べると、ちょっと
違うみたいです。アザミは、種類が多くて同定が難しいのですが、
名前はもう少し調べてから、またご報告したいと思います。野草の花も、なんだか秋らしくなってきました。
" alt="">-
花情報 9月26日
- 2012.09.28 森林担当 やっしん
- 花情報をお知らせします。 お客様受付の道路沿いで、ひっそり咲いていたこの花は、 「タムラソウ(キク科)」(撮...
-
-
登山道沿いには、様々な高山植物の花を見ることができました。
こちらは、「タカネグンナイフウロ(フウロソウ科)」(撮影日:9月12日)です。
その他にも、
ミヤマアキノキリンソウ、ウメバチソウ、トウヤクリンドウ、ハクサンボウフウ、
ハクサンイチゲ、ムカゴトラノオ、ヤマハハコ、ミヤマキンポウゲ、ウサギギク、
ヨツバシオガマ、ミヤマリンドウ、クロトウヒレン、トリカブトの仲間などなど、
今年はいつもより、多くの花を見ることができました。参加者全員で5~10kg程度の荷物(椰子マットや金具など)を、
分担して背負子で背負って運びました。
今回の作業場所は、伊那前岳の八合目付近です。
普段は立ち入り禁止の場所に、作業の為、特別に入れていただきました。
右から島田娘の頭、檜尾(ヒノキオ)岳、空木(ウツギ)岳といった、
中央アルプスの峰々を遠くまで見渡すことができました。感激です。
作業風景です。
あらかじめ設計された場所に、椰子マットを敷いて、石を元あった場所に戻し、
さらに金具を打ち込んで固定して行きます。色のきれいな新しいマットが、今回の作業分です。
尾根の登山道沿いでは、「ウラシマツツジ」の紅葉が始まっていました。
今年は、天気や花に恵まれ楽しく作業することができました。
これは参加賞です。山小屋の有料トイレの利用手形になっています。
富士山では、先日、初冠雪の便りがありましたね。
中央アルプスの紅葉も間もなく、上の方から始まります。中央アルプス千畳敷の紅葉を楽しんで、ロープウエイを降りられましたなら、
少しだけ足を延ばして、是非、養命酒健康の森へお立ち寄りください。
疲れた体をオリジナルティー&スイーツと、スタッフの素敵な笑顔が
皆様をお待ちしております。健康の森の営業時間は、9:30~16:30です。
" alt="">-
養命酒の水源の峰を行く2012
- 2012.09.27 森林担当 やっしん
- 養命酒を製造する水は、中央アルプスに育まれた地下水を使っています。 だからという訳ではありませんが、 私にと...
-
-
「ミズカマキリ」は、カメムシ目タイコウチ科に分類される
水生昆虫です。カマキリの仲間ではありません。私も子供の頃、よく採りましたが、最近では田んぼでも
あまり見かけなくなりました。ところで、普段は水の中で生活するこの「ミズカマキリ」ですが、
空を飛ぶって知っていますか?昆虫で、羽があるから当たり前と
いうかもしれませんが、、、。
でも、目の前で飛んでもらうには、ちょっと、コツがあります。
子供の頃、父親に教えてもらって、よく遊びました。そのコツは、またの機会に、写真付きで紹介したいと思います。
今回は、「ゲンゴロウ」らしきものも2匹見つけましたが、
残念ながら、捕捉できませんでしたので、また挑戦したいと思います。お楽しみに。
" alt="">-
ミズカマキリを捕捉
- 2012.09.15 森林担当 やっしん
- ミズバショウ池で、「ミズカマキリ」を捕捉しましたので、紹介します。 写真撮影のため、ちょっとだけ我慢してもら...
-
-
樹木にとって葉っぱの役割は、
光合成によって二酸化炭素と水からブドウ等を生成することや、
呼吸、また水分を空気中に放出(蒸散:じょうさん)して、
その吸引力によって、根から水分を吸い上げています。ですから、日陰の葉っぱは光合成の生産効率が悪くなるので、
早めに落としてしまいます。
夏も過ぎて、樹木もそろそろ生産調整に入ったようです。もう一か月近くも、まとまった雨が降らず、
森がカラカラに乾いているのも、落葉が早い原因かもしれません。カスミザクラの紅葉は、いつもかなり早めで、
もう少しずつ色付いてきました。
今年の秋も、健康の森の紅葉がきれいだといいですね。
" alt="">-
道路に落葉
- 2012.09.14 森林担当 やっしん
- 私たちは毎朝、お客様を迎える前に、 道路や駐車場の落葉などの掃除をします。 最近、桜(カスミザクラ)の葉っぱ...
-
-
名前の由来は、花が穂になってつくからです。
ツツジの仲間としては、花の時期が8~9月と遅い方です。こちらは、
「ワレモコウ(バラ科)」(撮影日:9月10日)です。
葉っぱをすり潰すと、スイカの香りがします。
最近、ワレモコウという歌がありましたが、
歌詞は思い出せず、悲しい感じの歌でした。こちらは、
「ツリガネニンジン(キキョウ科)」(撮影日:9月10日)です。
私の好きな花の一つです。
我が家の田んぼの土手には、割と普通に生えていて、
春先、新芽を山菜としていただきます。
なぜか、うちの家族は「ツリガネニンジン」を「三つ葉」
と呼んでいます。
茎の葉が3~4枚で輪生するからでしょうか??
一般的には、「ととき」という名の山菜として親しまれている
そうです。こちらは、
「ツルリンドウ(リンドウ科)」(撮影日:9月10日)です。
リンドウなのに、つる性です。
花の形は確かにリンドウです。
つるなのに、リンドウの仲間です。そういえば他にも、
「ツルアジサイ」や「イワガラミ(以前、登場)」のように、
つるなのに、アジサイの仲間というのがありましたね。
案外とそういうのあるんですよ。「ツルリンドウ」は林内の遊歩道沿いに、よく見られます。
" alt="">-
花情報 9月10日
- 2012.09.13 森林担当 やっしん
- 花情報をお知らせします。 今、カフェテラスのデッキの前で咲いているのは、 「ホツツジ(ツツジ科)」(撮影日:...
-
-
こちらは、ミズナラの枝。
よく見ると、ドングリの帽子の部分に黒っぽい
穴のようなものが見えます。
これは、「ハイイロチョッキリ」という虫が、
ドングリに卵を産みつけて、葉の付いた枝ごと切り落としたものです。
「ハイイロチョッキリ」は、オトシブミ科の甲虫で、
姿はゾウムシでわかっていただけますか??幼虫はドングリの中身を食べて成長し、その後、
土にもぐってサナギになるそうです。残念ながら、いまだ成虫の姿を確認できずにいる私です。
ドングリだけ切り落としたら、ストンと落ちますが、
" alt="">
葉っぱの付いた枝ごと切り落とすと、ひらひらとゆりかごの
様にゆっくり落ちてきます。
そんなところに、お母さんの愛情を感じます。-
チョッキリの仕業
- 2012.09.06 森林担当 やっしん
- 最近、森の中を歩いていると、あちらこちらに 若いドングリの付いたコナラの枝が落ちています。 こちらは、ミズナ...
-
-
駆除は容易ではありませんが、
花は以外ときれいです。
また、花は良い香りがします。
私の子供の頃(昭和40年代後半)から良く飲まれていた、
グレープ味の炭酸飲料の香りに似ています。万葉の人たちは、こんな「クズ」の花にも、
秋の情緒を感じていたのですね。私は、そんな情緒を感じつつも、景観整備の為なら
" alt="">
容赦なく刈り払います。-
秋の七草 その6「クズ」
- 2012.08.24 森林担当 やっしん
- 秋の七草 その6は「クズ」です。 あの、葛粉(くずこ)になる、あのくずです。 「クズ」はマメ科のつる性多年草...
-
-
イネ科の一年草、「エノコログサ」<狗尾草>です。穂の部分を切り取って、手のひらで軽く握り、
小刻みににぎにぎすると、手の中からにょきにょき
出て来るなんて、他愛もない遊びしたことありませんか?
穂の向きを変えて持つと、逆方向に出てきます。よく見ると、毛色の違うのがいます。
こちらは、「キンエノコロ」<金狗尾草>です。
穂の剛毛が黄金色で、穂が金色に輝いて見えます。こちらは、「ムラサキエノコログサ」<紫狗尾草>です。
穂の剛毛が紫褐色で、穂が紫色に輝いて見えます。まあ、エノコログサに秋の情緒を感じつつも、
雑草として、容赦なく刈り払っています。信州では、朝晩はすっかり涼しくなって、
" alt="">
寝るときは窓を閉めないと、朝方は風邪を引いて
しまうかもしれません。
夕方にはコオロギなどの秋の虫も鳴き始め、
信州では夏もそろそろ終わりです。-
雑草にも秋の気配
- 2012.08.23 森林担当 やっしん
- 残暑の中、夏休みの間に伸びてしまった あちこちの草刈作業に追われています。 同じ場所でも、生えている草の種類...
-
-
去年までは、、、、。しかし、今年、大きくリニューアルしました。
年明けから、周辺の森林を間伐整備し、池を拡張し、
間伐した丸太を使って橋を作り、新たな散策路を
開設しました。弥生式復元住居の近くから、チップ舗装された
新しい散策路を歩いて行きます。
20m程歩くと、小川を渡ります。
すぐに、水芭蕉池の橋にたどり着きます。
この橋は、土台は、森林整備で伐り倒したカラマツの株を使い、
梁や桁は、同じく切り倒したカラマツの丸太を使っています。
また、橋板は、製材してもらったカラマツの板を使い、手すり
の杭はヒノキの間伐材です。
橋の板面は少し波打っていますので、足元に注意しながら
渡ってください。
立っているときはそれ程気にならなかったのですが、
橋桁にしてみると、そのカラマツは以外と曲がっていました。森林整備で伐採した木を、何とか構内で利用したいとの思いから
作った木橋ですので、是非、自然素材の趣きをお楽しみください。橋の上からは見下ろした池は、橋作製に関わった私たち
にとっても新鮮な景色になりました。
池の周りでは、シオカラトンボやムギワラトンボ、
オニヤンマが盛んに飛び交っています。
水中にはヤマアカガエルのオタマジャクシや、
稀にミズカマキリやゲンゴロウも見ることができます。是非、記念館から少し足を延ばして、
" alt="">
水芭蕉池周辺の散策をお楽しみください。-
水芭蕉池2012年夏
- 2012.08.22 森林担当 やっしん
- 養命酒健康の森、西側の奥まった所には、 春、水芭蕉が咲く池があります。 しかし、夏になると夏草が生い茂り、 ...
-
-

- カフェ担当のんたん
- 食べることが大好き!!
毎日スイーツに囲まれて
幸せです。
-

- 案内担当みっき~
- 毎日自然に囲まれて
いるせいでしょうか。
・・・のんびりやの私です。
-

- 記念館担当ヨメ子
- 森の小さな変化を探し
ながら、四季を楽しんで
いるナチュラル派の私です。
-

- 森林担当やっしん
- 美しい森づくりに
情熱を注ぐ、
森のエキスパートです。