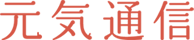生薬ものしり事典
- HOME >
- 生薬ものしり事典 >
- 【2017年5月号】大輪の花に生命力を秘めた「ボタン」
生薬ものしり辞典 56
大輪の花に生命力を秘めた「ボタン」
「牡丹皮」は解熱や鎮痛の生薬
4月から5月にかけて、華奢な木に大輪の豪華な花を咲かせる「ボタン」は、不思議な生命力を秘めています。ボタンはボタン科の落葉低木で、高さは50~180cm位になり、幹は直立して分枝します。1年に10cm程度しか成長しないのは、全精力を花にかけているからではないかといわれています。葉は柄があり、互生します。花茎は15~25㎝の大形で非常に美しく、色は紫、紅、淡紅、白色などさまざまです。
ボタンは観賞用花木として庭園で栽培されていますが、中国から渡来した当初は薬用植物として伝えられました。『延喜式』(927年)には、ボタンの根皮が各地から献上されていたことが書かれています。『枕草子』(1004~1092年)や『栄華物語』(1028~1092年)、『詩花和歌集』(1151年)などにもボタンが詠まれていることから、平安時代の中期以降に渡来したと思われます。
原産国の中国でも、薬用植物として利用されており、中唐(713~766年)の頃から観賞用に栽培され始めたようです。当時のボタンの花は小さく、色も紫赤の系統だけで、決して高級な花ではありませんでした。その頃から、花といえばボタンを指すようになり、満開の時節ともなれば、貴賤を問わず、ボタンを中心に遊楽にふけったという記録が残されています。
北栄の詩人蘇東波(1036~1101年)は、「牡丹を見るのは巳刻(午前10時)宜し巳より後は開き過ぎて花の精神衰えて力なく麗しからず、牛の刻(正午)より後に見る牡丹は知らざる俗客なり」といった観賞法も残しています。その頃から品種改良も進み、花の色も淡赤、真紅、紫、暗紅、黄など多種多様になり、花の大きさも直径15~25㎝の大輪も生まれるようになりました。
日本では、江戸時代になってからボタンの栽培熱が高まり、栽培の参考書である『紫陽三月記』(1691年)が出版されるほどでした。その頃、ドイツ人のケンペルがボタンをヨーロッパに紹介しています。その後、幕末から明治にかけて、日本産のボタンの苗は、ヨーロッパにたくさん輸出され、各地に広がりました。

ボタンが詩歌の対象にとして多くの歌人に詠まれるようになったのは、江戸時代以降。花の姿、散り際の見事さなどが詠まれました。
君に似る 白と真紅と 重なりて
牡丹散りたる 悲しきかたち
与謝野晶子
くれないの 大きな牡丹の 咲く見れば
花のおほきみ 今かかがやく
斎藤茂吉
虹を吐いて ひらかんとする
牡丹かな
与謝蕪村
侍が 傘さしかける ぼたん哉
小林一茶
ボタンの漢名は「牡丹」で、春に芽が雄々しく出ることから、盛んな意味として「牡」の字が当てられ、中国では丹色(赤)を上乗(仏教の最高の教え)としていることから「丹」の字が当てられたようです。別名も多く、「花王」「木芍薬」「花神」「宝相花」「貴客」「百両花」「富貴花」「天香国色」「洛陽花」「名取草」「深見原草」など、花の咲く姿から多様な名が付けられています。「花王」の名は、中国で百花のうちボタンが第一であることに由来します。ボタンの学名はPaeonia suffruticosaで、薬用であったことから属名がギリシア神話の医神Paeonに由来しています。
薬用としては、根皮に「牡丹皮」という生薬名が付けられており、解熱、鎮痛、消炎、月経不順などに用いられます。
花言葉は、「王者の風格」「高貴」「恥じらい」「壮麗」などです。
出典:牧幸男『植物楽趣』